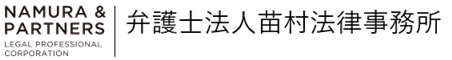アーカイブ
フラダンスの振付に著作物性を認めた判決について
弁護士 倉本 武任
1.はじめに
2018 年9 月20 日に、大阪地方裁判所で当事務所が原告代理人を務めた裁判において、原告のフラダンスの振り付けに著作物性を認める判断が下されました(以下「本判決」といいます)。舞踊は、著作権法上、著作物の一つに例示されており(著作権法10 条1項3 号)、振り付けを創作した者は、著作権、著作者人格権を有します(同法2 条1 項2号、17 条1 項)。著作物として認められるには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要であり、過去の裁判例では、社交ダンスについて、振り付けの創作物性が否定されるなど(以下「Shall we ダンス?事件判決」といいます)※1 ダンスの振り付けについて通常より高度の創作性が求められているとも考えられていました。しかし、本判決は、フラダンスの振り付けの著作物性の有無を判断するにあたり、Shall weダンス?事件判決が示した枠組みではない、新たな判断を示しました。
2.事案の概要について
ハワイ在住のクムフラ(フラダンスの師匠ないし指導者)である原告は、従前フラダンス教室事業を営む被告と契約を締結したうえ、被告やその会員に対してフラダンス等の指導、助言を行っていました。原告は、フラダンスの各楽曲を作詞作曲するとともに、それら又は他者が作詞作曲した楽曲について、フラダンスの振り付けを作り、被告の会員に対してそれらの振り付けを指導、助言し、会員は当該振り付けを、被告主催のイベントで上演したり、イベントに参加するための練習として教室で上演していました。
その後、両者の契約関係が解消され、原告は、以後は自ら作ったフラダンスの振り付けを被告の会員が上演することを禁止する意向を示しましたが、被告は、契約関係解消後も、少なくとも、原告作成の振り付けの一部を使用することがありました。そこで、原告が被告に対して、著作権侵害に係る請求として、そのうちのさらに一部を取りあげて(以下、「本件各振り付け」といいます)、著作権法112 条1 項に基づき、その上演の差し止めおよび損害賠償請求を求めました。
3.本判決における主要な争点
本件各振り付けのうち、原告が著作権を有する著作物であると被告も認める振り付け※2 を除く振り付け(以下、「対象振り付け」といいます)について著作物性が認められるかが主要な争点となりました。
4.本判決の判断について
(1)作者の個性の表れと認めることができるか否かについて
本判決は、フラダンスの特殊性は、楽曲の意味についてハンドモーション等を用いて表現することにあるとしたうえ、ハンドモーションとステップのそれぞれについて、作者の個性の表れと認めることができる場合とできない場合を示しました。
そして本判決は、ハンドモーションについて、①ある歌詞に対応する振り付けの動作が、歌詞から想定される既定のハンドモーションでも、他の類例に見られるものでも、それらと有意な差異が(ある)場合、②たとえ動作自体はありふれたものであったとしても、それを当該歌詞の箇所に振り付けることが他に見られない場合、③歌詞の解釈が独自であり、そのために振り付けの動作が他と異なるものとなっている場合には、作者の個性が表れていると認めるのが相当であると判断しました。
(2)舞踊の著作物性が認められる範囲
本判決は、楽曲の振り付けとしてのフラダンスは、作者の個性が表れている部分やそうとは認められない部分が相まった一連の流れとして成立するものであるから、そのようなひとまとまりとしての動作の流れを対象とする場合には、舞踊として成立するものであり、その中で、作者の個性が表れている部分が一定程度にわたる場合には、そのひとまとまりの流れの全体について舞踊の著作物性を認めるのが相当であると判断しました。
(3)著作権侵害の成否の判断基準
本判決は、振り付け全体を対象として検討すべきであるとしたうえで、フラダンスに舞踊の著作物性が認められる場合に、その侵害が認められるためには、
①侵害対象とされたひとまとまりの上演内容に、作者の個性が認められる特定の歌詞対応部分の振り付けの動作が含まれることが必要なことに加えて
②作者の個性が表れているとはいえない部分も含めて、当該ひとまとまりの上演内容について、当該フラダンスの一連の流れの動作たる舞踊としての特徴が感得されることを要すると解するのが相当であると判断しました。
(4)具体的あてはめ
本判決は、対象振り付けについて振り付けごとに、一定の歌詞に分け、分けた歌詞に対応する振り付けの動作について、原告の個性が表れているかそれぞれ検討したうえで、振り付け全体について、完全に独自な振り付けが見られるだけでなく、他の振り付けとは有意に異なるアレンジが全体に散りばめられていることから、全体として見た場合に原告の個性が表現されており、対象振り付けについて各振り付け全体としての著作物性を認めるのが相当であると判断しました。
5.本判決に対する検討
(1)求められる創作性について
Shall we ダンス?事件判決は、既存ステップの組み合わせを基本とする振り付けが著作物に該当するには、単なる既存のステップにとどまらない顕著な特徴を有するといった独創性※3 を備える必要があるとし、その理由として振り付けの自由度が過度に制約されることになりかねないことをあげます。
しかし、本判決は、創作性については、独創性までは求めず、作者の個性の表れと認められるか否かという観点から判断し、原告の対象振り付け全てについて曲全体の振り付けに著作物性を認めています。
舞踊の振り付けについては基本動作※4 であっても組み合わせには個性が発揮され、身体を使った動きも多様で、表現の選択の幅は広く捉えることができるとも考えられ、Shall we ダンス?事件のような独創性まで求めず、個性の表れで足りるとした点は、創作性の要求水準を下げつつある判例※5 の潮流にも乗ったものとして、権利者側には十分評価されるものと思われます。
(2)振り付け全体の著作物性を問題とする点について
本判決は、振り付け全体の著作物性を問題としていますが、楽曲の振り付けとしてのフラダンスは、ひとまとまりとしての動作の流れを対象として初めて、舞踊として成立するものであることからすれば、振り付け全体が対象となるのは当然と思えます。
そして、フラダンスの特徴からすれば、著作者としても個々のハンドモーションやステップではなく、上演内容たる振り付け全体が自身の著作物と考えるものと思われます。また、実際に振り付けを創作するにあたっても、振り付け全体との関係で、個々の振り付けの動作を考える以上、振り付け全体の著作物性を問題とした本判決は、創作活動の実態を踏まえたものとも考えられます。
※ 1: 東京地裁平成24 年2 月28 日判決
※ 2: 当該振り付けについては、被告は契約関係解消以降、当該振り付けの使用をしていないと主張しています。
※ 3: 上野達弘 コピライトNo.686/vol.58 2018 年6 月号 13頁~15頁ではそもそもこのフレーズは、タイプフェイスの著作物性が問題となったゴナU 事件最高裁判決(最高裁平成12 年9 月7 日第一小法廷判決)が示したフレーズであり、あくまで印刷用書体に限って妥当すると理解すべきとされています。
※ 4: 上野達弘 法学教室 2018 年2 月号「舞台芸術と知的財産法」29 頁 注釈11 では、古典フラとは異なり、現代フラにおいては、多種多様なハンドモーションやステップ、身体の向き、顔や目線の向き、重心の位置、ターンの仕方等の選択と組み合わせが行われるものであるとして、フラダンスの創作性を肯定することに好意的な意見を述べています。
※ 5: TRIPP TRAPP という赤ちゃん用椅子のデザインに著作物性を認めた知財高裁平成27 年4 月14 日判決、ピクトグラムに関する大阪地裁平成27 年9 月24 日判決など。
欧州GDPRの概要と対応にあたっての注意点
弁護士 田中 敦(たなか あつし)
1 はじめに
本年5月25日から、EUにおけるGDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)の適用が開始されました。
GDPRは、欧州経済領域(EEA)域内の新たな個人情報保護の枠組みを定めたものですが、EEA域内に所在する者の個人情報の移転を伴う取引を行っている事業者にも幅広く適用されるため、多くの日本企業がGDPRへの対応を求められます。
以下では、GDPRの概要をご紹介し、欧州に関連する取引を行うわが国の事業者に求められるGDPRへの対応の注意点について簡単に述べます。
2.GDPRの概要
(1) GDPRとは
EUでは、1995年に個人情報保護に関する法制度の共通化のためにデータ保護指令(96/46/EC指令)が採択されました。当該指令は、加盟国に対して直接には適用されず、加盟各国が自国の法令により個人情報保護の枠組みを定めていました。
その後、近年の急速な技術進歩や個人情報取扱いのグローバル化を受け、新たな態様での個人情報の取扱いに対応すべき必要性が生じるとともに、国家を超えたデータ保護法制のさらなる均一化が求められるようになり、国内法の制定を経ずとも加盟国を直接拘束する統一的な法規範として、2016年4月27日にGDPRが採択されました。
(2) GDPRの適用対象
GDPRで保護対象となる「個人データ」とは、EEA域内に所在する自然人(データ主体)を識別し得る情報をいい(4条)、データ主体は国籍や居住地を問いません。そのため、海外赴任や出張でEEA域内に所在する日本人従業員等の情報も、GDPRにより保護される個人データに含まれ得ます。また、日本からEEA域内へ個人データを送付した場合には、当該個人データについても、EEA域内においてGDPRに従って適切に処理されなければなりません。
仮に事業者がEEA域外に所在しているとしても、当該事業者がEEA域内のデータ主体に対して商品やサービスを提供する場合には、GDPRの適用を受けます(3条)。そのため、インターネット取引等で日本企業がEEA域内の顧客等に商品やサービスを提供する場合、たとえ当該企業がEEA域内に拠点等を有していなくても、GDPRが直接適用されることとなります。
また、わが国の個人情報保護法では「個人データ」に直ちには該当しない可能性のあるIPアドレスやCookieといったオンライン識別子が、GDPRでは保護対象の「個人データ」に挙げられていることにも注意が必要です。
(3) 個人データの処理・移転に関する義務とデータ主体の権利
GDPRの適用対象となる個人データについて、その処理等を行う事業者(管理者及び取扱者、以下「管理者等」といいます。)には、法令上、適切なセキュリティ措置の実施(32条以下)、データ保護責任者の選任(37条)等の様々な義務が課せられます。
また、GDPRでは、多くのデータ主体の権利が明記されており、わが国の個人情報保護法における本人の権利よりも広い範囲で、個人データにより識別される個人の権利が認められています。例えば、GRPRにおいては、わが国の個人情報保護法と異なり、自己の個人データの削除を求めることができる削除権(「忘れられる権利」、17条)、自己の個人データのコントロールを可能とするデータポータビリティ権(20条)等が明記されています。
(4) GDPRの違反者への制裁
GDPRの大きな特徴の一つが、違反者への厳しい制裁金が定められていることです。違反類型に応じて、違反企業に対しては、最大で2000万ユーロ又は前年度の全世界年間売上の4%を上限とする制裁金が課せられるおそれがあります(83条)。
欧州においては、過去に競争法違反により多くの日本企業に対し巨額の制裁金の支払いが命じられており、将来にはGDPR違反により日本企業に対し制裁金が課されることも十分想定されます。欧州でビジネスを行うわが国の企業としては、制度上、GDPRに違反した企業には数十億円を超える制裁金が課せられるおそれがあることに十分注意すべきでしょう。
3.GDPRへの対応の注意点
本稿では、GDPRにより求められる対応を網羅的に説明することは字数の制限上困難ですが、GDPR対応にあたっての基本的な方針を最初に述べ、その後、特に注意すべき点をいくつかご紹介します。
(1) GDPR対応への基本的な方針
まず、GDPRへの対応には、社内の現状を把握し、GDPRの要求事項と現状のギャップを分析することで、対応方針を策定することが重要となります。
社内の現状把握としては、各拠点や部署への質問票送付やインタビューなどにより、どの拠点又は部署が、どのような目的で、どのような流れでEEA域内のデータ主体の個人データを取り扱っているのかを正確に理解することが必要です(いわゆる「データマッピング」)。
その上で、GDPRの要求事項に照らし合わせ、対応すべき課題を洗い出すとともに、それら課題に優先順位をつけながら対応方針を策定しなければなりません。
(2) EEA域外の第三国への移転の原則禁止
まず一つ目の注意点として、GDPRでは、EEA域外への個人データの移転が原則として禁止されています。例外的に、欧州委員会が個人データの保護の「十分性」を認定した国については適法に移転できます。日本は、長らく「十分性」認定を受けるための取組みを続けてきましたが、平成30年7月、EUとの間で「十分性」の認定を受けることの最終合意に至ったことが報じられました。
もっとも、「十分性」の認定の手続が完了するまでの間は、EEA域内のデータ主体の個人データを日本国内へ移転するには、たとえ親子会社間であっても、下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。各要件の詳細については割愛しますが、当該個人データの量、性質、移転の目的、利用の態様、移転事業者間の関係性等を個別具体的に考慮して、最もふさわしい手続を選定することが求められます。
①本人からの個別の同意の取得
②標準契約条項(Standard Contractual Clauses)の締結
③(グループ会社間での)拘束的企業準則(Binding Corporate Rules)の策定
(3) データ保護責任者の選任
個人データの管理者等の中心的業務が、大規模なデータ主体の定期的かつ系統的な監視を要する業務であったり、又は、機微情報(人種、思想、遺伝データ、生体データ、犯罪歴等)を大規模に取り扱う業務であるなどの一定の場合には、当該事業者には、高い独立性を有する「データ保護責任者」(Data Protection Officer)の選任が義務付けられます。データ保護責任者の任務には、他の従業員への助言や事業者の監視等が含まれます(39条)。
(4) データ保護影響評価
個人データの処理が個人の権利又は自由に対して高度のリスクをもたらす危険がある場合、当該個人データの管理者は、個人データの処理に先立ち、これにより個人データの保護にどのような影響を及ぼすかを評価しなければなりません(35条)。
(5) 侵害発覚時の通知義務
個人データの滅失、サイバー攻撃による漏えい等、個人データの侵害行為が発覚した場合、当該個人データの管理者は、侵害を認識してから72時間以内に監督機関へ通知しなければなりません(33条)。9月11日の日経新聞では、このGDPRの適用後初めての例として、ブリティッシュエアウェイズの顧客情報約38万件が盗まれたとして個人情報保護当局や警察に届け出たと報じています。情報の取得は8月21日から9月5日まで続いたとしており、当局が今後どのような措置をとっていくかが注目されます。
以 上
有期雇用契約に関する2つの最高裁判所第第二小法廷平成30年6月1日判決について
弁護士 倉本 武任
1.はじめに
非正規社員が不当な賃金格差を訴えた2つの労働事件について、平成30年6月1日、同日に2つの最高裁判決が下されました。1つは、横浜市の運送業者のトラック運転手3名が、定年前と同じ仕事なのに賃金を引き下げられていたのは不当として訴えた事件(以下「N運輸事件」といいます。)、もう1つは、正社員と契約社員で手当の支給に差をつけることが違法かどうかが争われた事件(以下「HL社事件」といいます。)です。
労働契約法20条は、期間の定めがある労働者の労働条件が、期間の定めがない労働者の労働条件と比較して、不合理な労働条件となることを禁止していますが、同条において、①「期間の定めがあることにより」との文言解釈、②不合理か否かの判断、③不合理と認められた場合の法的効果について、これまで判断・解釈が分かれるなかで、両最高裁判決は、最高裁として初めて、各賃金項目の趣旨を個別に考慮したうえで、一部について不合理性を認め、無効であるとの判断を示しました。また、近時、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」[1]が成立し、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の是正を図るため、有期雇用労働者の均等待遇規定を整備することとされるなど同一賃金同一労働が叫ばれる状況において、注目すべき裁判例となります。
本稿では、両判決の事案の概要、最高裁判所の判断を紹介し、両判決による影響について検討いたします。
2.事案の概要について
(1)N運輸事件について
会社を定年退職した後に、期間の定めのある労働契約を会社と締結している労働者(以下「有期契約労働者」という。)が、期間の定めのない労働契約を会社と締結している労働者(以下「無期契約労働者」という。)との間で、能率給及び職務給、精勤手当、住宅手当、家族手当、約付手当、超勤手当、賞与といった労働条件の相違があることが、労働契約法20条に違反するかどうかが争われた事案です。
高齢者雇用安定法に基づく定年後の継続雇用措置[2]として有期労働契約で再雇用された労働者について、無期契約労働者と有期契約労働者との処遇の相違が労働契約法20条の不合理な労働条件に当たるか否かが問題となりました。
(2)HL社事件について
有期労働契約を締結して会社に勤務する労働者が、無期労働契約を会社と締結している正社員と当該労働者の間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金に相違があることは労働契約法20条に違反するかどうかが争われた事案です。正社員と契約社員との間の格差が、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の相違を禁止した労働契約法20条に違反するか否かが問題となりました。
3.両最高裁判決で共通する主要な争点
①「期間の定めがあることにより」の文言解釈
②労働契約法20条違反の判断基準(労働条件の不合理性の判断基準)
③労働契約法20条違反の効果
4.裁判所の判断について
(1)①「期間の定めがあることにより」についての文言解釈
同条の解釈について「期間の定めがあることにより」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものとしました。それまで、同解釈によれば、労働契約法20条が適用される場面はかなり広くなると考えられます。
(2)②労働契約法20条違反の判断基準
労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件が相違する場合、当該労働条件の相違は、①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲、③その他の事情の3つの観点から判断して、不合理と認められるものではあってはならない旨を定めているとし、不合理性の判断基準を示しました。そのうえで、両判決においては、有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものとしています。すなわち、各賃金項目の趣旨によって、その考慮すべき事情や考慮の仕方も異なるという理解を前提としています(ただし、N運輸事件判決においては、両者の賃金の総額の比較や、ある賃金項目の有無および内容が、他の賃金項目の有無および内容を踏まえて決定される場合もあり得るので、そのような事情も考慮するとされています)。
N運輸事件の第一審判決[3]では、①及び②の事項について、有期雇用労働者と無期雇用労働者の間で同一性を有する場合には、③が存在しない限り、不合理性が認められるとする枠組みでしたが、控訴審[4]及び最高裁は、全ての要素を総合的に判断するという枠組みによっており、仮に①、②の事項について、有期雇用労働者と無期雇用労働者の間で違いを設けたとしても③の事項によっては、労働条件の相違が不合理であると判断される可能性もあるということになります。また、N運輸事件の最高裁判決は、控訴審判決と同様の基準によりつつ、会社を定年退職した後に、有期労働契約により再雇用された者であるという事情を、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たると解し、各賃金項目の労働条件の不合理性の判断において考慮事情としています。
(3)③労働契約法違反の効果について
両判決においては、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合であっても、同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと判断し、上告人が有期契約労働者に関する就業規則等が適用される地位にあることの確認を求める請求を排斥しました。
5.検討
両判決において、例えば、皆勤手当については、出勤するものを確保する必要性から、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであり、有期契約労働者と無期契約労働者の職務の内容が異ならない場合、出勤する者を確保することの必要性は、職務の内容によって差異が生ずるものではないことから、皆勤手当に関する労働条件の相違は不合理であると評価しています。このように、各賃金項目の趣旨から、その支給の有無や内容の違いは、職務内容あるいは変更の範囲の相違から、不合理でないと説明できるのか、それが説明できない場合には、他の賃金項目で優遇している等のその他の事情から企業として不合理でないことが説明できるかを検討する必要があります。
上記、2つの最高裁判決において、労働契約法20条の解釈が示されたことで、企業経営者にとっては、無期契約労働者と有期契約労働者の間で設ける労働条件の検討にあたっては、各賃金項目ごとの目的や、支払基準、金額等について、慎重な検討が求められることとなります。
以上
[1] 働き方改革関連法案の内容について、詳細は厚生労働省のHPを参照ください。
[2] 60歳定年を超えた労働者について、企業に、原則65歳までの雇用保障をすべきことを求めるものです。
[3] 東京地裁平成28年5月13日判決
[4] 東京高裁平成28年11月2日判決
~営業秘密と認められるための秘密管理性―刑事事件では?~
東京高裁平成29年3月21日判決
弁護士 立川 献
1.はじめに
不正競争防止法上の営業秘密に該当するには、
①秘密として管理されている〔秘密管理性〕
②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報〔有用性〕
③公然と知られていない〔非公知性〕
との3 つの要件を満たす必要があります。
被害者が不正競争防止法上の救済を受けることができるかどうかを決する意味で、また違反者に刑事罰を受けさせられるかについても、被害者の実施する秘密管理体制が、法にいう〔秘密管理性〕を満たすものであるかどうかは、非常に重要な問題となります。
〔秘密管理性〕が要件とされている趣旨は、「事業者が秘密として管理しようとする対象(情報の範囲)が従業員や取引先に対して明確化されることによって、従業員等の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確保すること」にあり※1、保有者の特定の情報を秘密として管理しようとする意思が、保有者の実施する具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があるされています。
かかる指針のもと、営業秘密の保有者としては、どのような具体的措置を採っていなければならないのでしょうか。
この度、東京高裁にて、営業秘密侵害罪(ただし平成27 年の改正前の法21条1 項3 号ロ、同条1 項4 号)に関する判決が下されました。
2.本件の事実関係
(1)起訴事実等
通信教育等を業として行う株式会社Oが、システム開発会社P に対して、情報システムの開発を委託した。被告人AはP 社の3 次下請人である。A は、開発作業のため、O 社のデータサーバにアクセスできるID 及びパスワードを貸与されていた。A は、① P 社貸与の業務用パソコンでO 社のサーバにアクセスし、1000 万件以上の顧客情報をダウンロードして保存、その後自ら所有するスマートフォンに当該データを保存して領得し、②大容量データ送信サービスで、同顧客情報をアップロードし、株式会社D社(名簿業者)代表取締役に、同顧客情報をダウンロードするためのURL 等を送信し、同顧客情報をダウンロードさせ、顧客情報を開示する等して起訴された。
第一審(東京地方裁判所立川支部平成28 年3 月29 日判決)は、秘密管理性について、「①当該情報にアクセスできる者を制限するなど、当該情報の秘密保持のために必要な合理的管理方法がとられており、②当該情報にアクセスした者につき、それが管理されている秘密情報であると客観的に認識することが可能であることを要する」との民事上の差止請求権が認められる場合の一般的基準と同様の基準を挙げ、「それを超えて、…外部者による不正アクセス等の不正行為を念頭においた、可能な限り高度な対策を講じて情報の漏出を防止するといった高度な情報セキュリティ水準まで要するものとはいえない」としました。
①につき、
・当該情報にアクセスできるかは、開発中の本件システムのアカウントを利用できたか否かによるが、O 社とP 社は、業務上の必要性を吟味し、不要な部署や従業者に対してはアカウントの使用を許していなかった/・アクセスできる従業員の数が限定されていた/・情報にアクセスできる端末が錠付きチェーンロックで固定され持出しが不可能とされていた、/・セキュリティソフトによりUSB メモリ等によるデータの持出しが禁止されていた(ただし、このソフトは一定の機種のスマートフォンへのデータ移転に対しては機能しない)/・秘密情報の管理についての社内規程、研修等が整備されていた
②に関しては、
・本件システムの内容と目的、顧客情報の性質/・A 自身も研修を受講のうえ、秘密保持に関する同意書を作成していたこと、等を認定し、秘密管理性を認めました。
(2)控訴審(本件)
判決 原判決破棄自判懲役2 年6 月及び罰金300 万円
控訴審は、「顧客情報へのアクセス制限等の点において不備があり、大企業として採るべき相当高度な管理方法が採用、実践されていたといえなくても、当該情報に接した者が秘密であることが認識できれば、全体として秘密管理性の要件は満たされていたというべきである」とし、セキュリティ研修の実施、秘密保持に関する同意書の提出を求め、本件システム及び本件顧客情報の性質等を併せ考慮すると、秘密管理性の要件は満たされていた、としました。
ただし、①データベースにアクセスするアカウント情報が共有フォルダに保存されていた、②私物スマートフォンの執務室への持込が禁止されていなかった、③アラートシステムが機能していなかった、④ A が3 次派遣の労働者に該当し、上長においてもA の所属先会社を知らなかった、との秘密管理上の不備を指摘し、被害者O 社側の落ち度も大きいとの点を量刑判断に反映させました。
3.検討
本件は、システム開発を委託した先の下請人が、開発の便宜のために貸与されたアクセス権限を悪用したというものです。
秘密管理性については、一定の厳格な基準を設け、事案に関係なく、この基準を当てはめるる客観説に立脚し、秘密管理性を厳格に考える裁判例※2 が続きましたが、ポリカーボネート樹脂製造装置事件(知財高裁平成23 年9 月27 日判決)以来、秘密管理性を秘密情報の希少性や企業の規模や状況等と勘案して、必要な管理体制を認定する相対説に裁判例が登場してきています※3。
本件においては、データベースにアクセスするためのアカウント情報が共有フォルダ内に保存されていたことが認定されており、客観説的な考え方に立脚すれば、秘密管理性が認められないと考えることもできそうです。しかし、秘密管理性が認められるための要件の②秘密情報であることの(客観的)※4 認識可能性こそが重要であり、①(秘密管理措置)と②を独立した要件とみるのは相当でなく、「当該情報に接した者が秘密であることが認識できれば、全体として秘密管理性の要件は満たされていたというべきである」と明示した点に特徴があります。
今後は、秘密情報にアクセスできる者に対して、いかなる情報が秘密情報であるか、確実に認識することができる措置(同意書作成、研修等の受講報告等)の整備を行い、アクセス者の認識を文書化しておくことも、疎かにすることができない重要な要素となると考えられます。
※ 1:経済産業省知的財産政策室著『逐条解説不正競争防止法』41 頁、http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/full.pdf
※ 2:例えば東京高裁平成13 年3 月19 日決定など、知財管理Vol.52,No.9,2002 にて苗村が評釈。
※3:知財管理Vol.62 No.10,2012
※4:本判決は、客観的認識可能性と述べていますが、本来は当該接触者の認識可能性が要件と考えてよいところです。
依頼者と弁護士の通信秘密保護制度
弁護士 苗村博子
はじめに
1以下でご紹介しているのは、2017年に執筆したものですが、以後、様々な紛争やテロ事件、米国で議会が襲撃され、はては本年には、ウクライナ侵略が起こりました。12月7日には、ドイツで議事堂襲撃を画策していたとして25名(一人は裁判官とのこと)が逮捕されるなど、国家のまさに物理的な安全が脅かされる事件が相次ぎました。また、FTXの創業者が詐欺罪やマネーロンダリングの罪でバハマで逮捕されるなど、巨額の不正事件も起こり、これらの資金がテロリストに行きつくのではないかとの懸念も高まっています。そんな中、刑事事件や、民事罰に関する法的問題も含め、弁護士への相談も増えていますが、弁護士の広い意味での防御権を狭めてでも、国家が様々な情報を得たいという要求が高まり、この弁護士依頼者間の通信秘密が脅かされているのではないかとの懸念が、これらの制度を生み出してきた国ですら高まってきています。ただ、このようなマネロン等以外では、まだ他国でしっかり機能しているということも同時にご理解いただければと思っています。(2022年12月16日追記)
1 通信秘密保護制度って何?
まだ耳慣れないこの言葉、Attorney Client Privilegeまたは弁護士依頼者間秘匿特権と言った方が、分かって頂き易いかと思いますが、日本語のこの表現は、どうも弁護士の特権といった誤解を生みやすく、私が参加している日弁連のWGでは、ご依頼者の権利であることを分かって頂けるよう、タイトルの言葉を用いています。通信秘密として保護され、行政当局、刑事司法当局、民事事件の相手方に対して、依頼者と弁護士の間の通信内容を記した書類の提出を拒むことができ、またその通信内容に関する証言を拒否できるというものです。コモンローの国では、この保護が明確ですが、日本では、十分な保護があるとは言えない状況です。
現在この問題が最も先鋭化しているのが国際カルテルの分野です。日本で通信秘密保護が十分でないことから、米国の弁護士等は自分たちの意見書を依頼者に渡さないよう私たちに指示をしてきます。米国では必ず後で起こるクラスアクションなどの民事賠償請求の際に、依頼者の手元に意見書があれば、ディスカバリでこの提出が求められるからです。日本の弁護士は、これをどうご依頼者に説明するか苦慮します。違反行為を認めざるを得ない場合に、違反があると考えざるを得ないと言うことは口頭でも理解して貰えますが、何が問題だったのか、どうすれば、事案に即した再発防止策を立てるのが難しい状況となっています。事務所には意見書を置いているので見に来て下さいとは言っていますが、やはり、企業としては、身近に意見書をおいて分析するのは重要だと思います。
2 通信秘密を保護する理由
依頼者は、弁護士に包み隠さず事実や状況を伝えられて初めて、適切な弁護士のアドバイスが受けられるという依頼者の広い意味での防御権、そして適切な意見により、適切なコンプライアンス体制がとれるという効果の二つが期待されています。
3 何が保護の対象か-コモンローの国での保護要件
①まず、依頼者と弁護士の間の通信であることが必要です。従って、弁護士に法的アドバイスを求めるための相談内容や弁護士からの回答、また弁護士の意見書などがこれに含まれます。企業のご依頼者の場合、法律相談と、ビジネス相談が一緒になることがありますが、通信秘密制度の保護対象となるのは、法律相談が主な場合に限られます。またその相談のために、過去に作成された従業員のメールなどを添付して送られる場合がありますが、このような過去に作成された書類まで秘密保護の対象となるわけでは有りません。かつては、弁護士をCCに入れておけば全て秘密にできるなどまちがった用いられ方が推奨されたことがありますが、これは誤解です。
②弁護士は、その国の弁護士だけでなく、外国の弁護士も対象となります。但しその外国で通信秘密保護制度が認められていない国の弁護士は、弁護士として認められない可能性があります。日本では東京高裁が通信秘密保護制度は現行の法制下では保護されていないとして、独禁法違反事件に関し、弁護士の意見書を公取委が押収した事案で、同意見書の押収について取消請求を認めませんでした。現在アメリカではいくつかの州で日本の弁護士への相談も通信秘密保護の対象だと認めてくれていますが、今後、この点が争われるのではないかが懸念されます。
またイギリスを除くヨーロッパでは、組織内弁護士は、必要な独立性を満たしていないとされ、通信秘密保護の対象となる弁護士とはされていません。
③この通信の秘密が保たれていることが必要です。社内で保管されていれば秘密ということではなく、関係者をあまり限らず、多くのCC先に送ったりすると、秘密性が失われてしまう可能性があります。
④弁護士への相談が、犯罪の示唆や、証拠隠滅に関わっていないことが要件です。過去に起こした犯罪行為に関する相談自体は、通信秘密保護の対象ですが、これから犯罪を企てるための相談や、過去の犯罪行為をどう隠蔽するかといった相談は対象外です。よく濫用防止が必要といわれますが、濫用というより、このような相談はそもそも保護の対象となりません。
⑤また、放棄されていないことも必要です。かつて米国司法省では、犯罪捜査に協力して減刑を求めるには、この通信秘密の保護を放棄するように求めることがありましたが、この保護を重視する議会がこのような放棄の強制を認めない法案を策定するとの動きをしたことにより、司法省も実務を変えた様です。それだけ重要な制度と考えられています。
4 審査手続
ある書類が通信秘密保護の対象かどうかについては、第三者的な判断が必要となりますが、刑事、行政の分野では捜査、調査を遅延させないため、まずは当局の担当者以外の者による判定がなされ、不服がある場合、また民事の場合は、裁判所による判断が成されています。
5 2017年LAWASIA東京大会での議論
「弁護士との相談は秘密か?」というタイトルで、一つのセッションが行われ、私がモデレータを勤めました。オーストラリアの州最高裁判事、元の米国司法省反トラスト部局次長の弁護士、日本企業の社内弁護士、韓国の弁護士のスピーカーを迎え、様々な角度から、討論をして貰いました。通信秘密保護制度が事実解明を阻害することにならないか、また、秘密性がどのような時に失われてしまうのか等、この保護制度が日本でも法制度として構築されるための多くの示唆を得ました。どこかでご紹介できればと思っています。
公益通報者保護法以外の内部通報の保護
弁護士 苗村博子
1. はじめに
日本では文科省、米国では FBI と、公務員からのマスコミへの通報が内部告発として許容されるのかどうかに関心が集まっています。内部告発といえば、「公益通報者保護法」を思い浮かべる方も多いと思いますが、この法律は、それまで外部に告発した通報者への解雇、不利益取扱いに関する判例の基準に明確性を与えるために作られた法律で、 その適用の射程が狭く、この法律だけでは、保護が必要と思われる内部通報をすべてカバーすることができません。同法 6 条自体が、他の法律による保護を妨げないと明記しています。したがって労働基準法や民法に基づく解雇権濫用法理などで、解雇を無効とする実務は、公益通報者保護法施行後も続けられており、様々な方策で通報者保護が図られています。
2.公益通報者保護法の保護範囲
まず、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図るために、公益通報者を保護する法律であることから、通報対象事実は国民生活に関わる限定列挙された法律で、①直接刑事罰の対象となるか、②違反行為に対する処分への違反が刑事罰の対象となるものに限られています。また、外部への通報ができる場合は、権限のある監督官庁に対して行う場合でも、「信じるに足りる相当の理由がある場合」に限られます。マスコミ等、通報することで発生や被害の拡大を防止するために必要と認められる者に対する場合は、①内部や監督官庁に通報すれば不利益取扱をされると信じるに足りる相当の理由がある場合、②内部に通報すれば証拠等が隠滅されると信じるに足りる相当の理由がある場合、③労務提供先から正当な理由なく通報を止められた場合、④書面によって内部に通報してから 20 日を経過しても調査をする旨の通知がないか、正当な理由がないのに調査しない場合、⑤個人の生命身体に危害は発生する急迫した危険がある場合に限られているのです。
ちなみに公務員も公益通報者に該当するのですが、アメリカの FBI 前長官の例などは、日本に司法妨害罪がないだけでなく、国民の生命、身体などに直接関わらないので、日本では、仮に解雇前に例のメモをマスコミに開示していたとして、公益通報者保護法では前長官を保護することは難しくなります。
3.民法等による保護
(1) トナミ運輸事件
公益通報者保護法施行前の内部通報に対する不利益取扱いが債務不履行、不法行為とされた事件で有名なのはヤミカルテルに関するトナミ運輸事件(富山地裁平成 17 年 2 月 23 日判決)でしょう。裁判所は、告発者(原告)が告発したヤミカルテル行為は現実に行われていたとし、告発者(原告)が内部で副社長や営業所長に直訴したものの受け入れられなかったことから新聞社に通報をしたと認定しました。報道機関は是正を図るに必要な者ではあるものの、一方で会社の違法行為が不特定多数に広がり、短期的には会社に打撃を与え得ることから信頼関係維持のため会社の不利益にも配慮する必要があったとしながらも、告発者が会社内部で是正のため努力しても会社の状況から何らかの是正措置が執られる可能性は低かったとして、告発は法的保護に値するとしました。告発者はその後、退職を強要されたり、個室に入れられ、格別の仕事もないまま、昇進もなく過ごすしかないような不利益な取扱いを受けたとして、会社の不法行為、人事権の逸脱による債務不履行を認めたというものです。この判決の判断方法は、まさに今も公益通報者保護法のモデルとなったともいえるような事件でした。
(2) 大阪市河川事務所職員懲戒免職事件
こちらは、大阪地裁平成 24 年 8 月29 日の判決で、行為自体も公益通報者保護法施行後の、公務員に関わる事件です。河川事務所職員が清掃時に収得した現金等を分配する映像を撮影し、自らも分配を受けた原告が、この映像をマスコミに提供したところ、この領得等を以て、懲戒免職処分を受けたため、免職処分の取消を求めたというものです。公益通報者保護法では、河川事務所による物色・領得行為は同法が認める法律違反といえるか微妙で、通報対象事実に該当しない可能性があります。この映像はテレビで放送され、調査チームによる調査がなされ、大量の処分者が出ました。判決は、原告も 5 万円の分配を受けてはいるものの、原告の内部告発により、河川事務所の違法または不適切な取扱いの実態が明らかになってその是正が図られており、これは原告に有利な事情として考慮すべきであるとし、懲戒処分として免職としたのは裁量権の逸脱であるとして、免職の無効を言い渡しました。通報行為についても、内部への通報をしないまま直ちにマスコミに映像とともに通報することは公益通報者保護法では認められないとされる可能性が高い行為ですが、裁判所は、この法律を離れ、懲戒免職処分の相当性から、判断をしたのです。
4.おわりに
大阪河川事務所事件からすると、FBI前長官の行為が仮に解任前になされていたとしても、これを以て解雇されていて、日本で裁判になれば、その解任が無効となる可能性は十分にあるといえるでしょう。公益通報者保護法は、内部通報制度を構築する際の参考にはなりますが、社内の通報制度を構築する場合には、この法律の枠組みにとらわれることなく、通報者の保護範囲をより広い制度にしておくことが重要と思われます。
クロレラチラシ配布差止訴訟と消費者契約法上の「勧誘」の意義
弁護士 田中 敦
1. はじめに
本年1 月24 日、最高裁が、サン・クロレラ販売株式会社(以下「サン・クロレラ」といいます)による広告チラシの配布について、消費者契約法上の「勧誘」に該当し得るとの判断を下しました。当該判断は、不特定多数に向けた広告であっても、消費者契約法に基づく差止請求等の対象となり得るとする点で、従前の行政解釈を実質的に変更するものであり、今後の広告の在り方に大きな影響を与えるものと考えられます。
2.事実の経緯
サン・クロレラは、昭和48 年頃からクロレラ(単細胞の緑藻類)を原料とした健康食品を販売している会社です。
平成25 年8月、「日本クロレラ療法研究会」の名義で、クロレラには免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある旨の記載や、クロレラの摂取により高血圧等の様々な疾病が快復した旨の体験談等の記載がある折り込みチラシ(以下「本件チラシ」といいます)が配布されました。本件チラシには、具体的な商品名の記載はなく、本件チラシに記載された研究会の連絡先への問合せがあれば、サン・クロレラから問い合わせた者へ商品カタログが送付されていました。
消費者契約法に基づく認定を受けた適格消費者団体(特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク)は、本件チラシの配布は消費者契約法上の「勧誘」にあたり、サン・クロレラが実質的な配布主体であるところ、本件チラシには消費者に対する不実告知が含まれると主張して、その配布の差止めを求めて提訴しました 。
原判決(大阪高裁平成28 年2 月25日判決)は、景品表示法に基づく差止請求※1 を認めた第一審判決(京都地裁平成27 年1 月21 日判決)を破棄した上、消費者契約法に基づく差止請求についても、同法上の「勧誘」には「事業者が不特定多数の消費者に向けて広く行う働きかけ」は含まれず、本件チラシの配布は「勧誘」にあたらないとして、適格消費者団体の請求をすべて棄却したところ、これに対し同団体が上告しました。
3.最高裁の判示した内容
(1) 本件における争点
(消費者契約法上の「勧誘」の意義)消費者契約法4条各項は、事業者による消費者契約の締結の「勧誘」に際して、不実告知(重要事項について事実と異なることの告知)や不利益事実(重要事項について消費者の不利益となる事実)の不告知を禁止し、これに違反した場合の消費者の取消権を定めています。また、同法12 条1項及び2 項では、適格消費者団体は、消費者契約の締結の「勧誘」に際し、事業者が上記の各禁止行為を現に行い、または行うおそれがあるときには、当該事業者に対し、それら行為の差止め等を求めることができると定めています。
本件の最高裁判決では、本件チラシの配布が、消費者契約法上の「勧誘」に該当し、適格消費者団体による差止めの対象となるか否かが争点となりました。
(2) 最高裁の判示
最高裁は、本件チラシの配布が「勧誘」にあたらないとした原判決の判断を是認することができないと判示しました。
その理由として、最高裁は、消費者契約法は消費者の利益の擁護を図ること等を目的とするところ、事業者が「その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは、当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得る」として、不特定多数に向けた働きかけを一律に「勧誘」から除外することは同法の趣旨目的からして相当でないことを挙げました。
もっとも、最高裁は、サン・クロレラは本件チラシを現に配布しておらず、また配布するおそれもあるとはいえないとして、結論としては適格消費者団体の請求をいずれも棄却した原判決を是認しました。
4.本判決が今後の広告実務に与える影響
どのような消費者への働きかけが消費者契約法上の「勧誘」にあたるかについて、従前の消費者庁の見解※2 では、不特定多数の消費者に向けて広く行う働きかけは「勧誘」には含まれないと解されていましたが、これに対する根強い反対意見もありました。
この点、本判決は、不特定多数に向けた働きかけであっても「勧誘」に該当し得ると判示し、従前の行政解釈を実質的に変更したものといえます。現に、本判決翌日の消費者庁の会見※3 では、消費者庁長官から「昨日出されました最高裁の判決は、大変重要なものと考えております」と述べられ、その後消費者庁が改定した消費者契約法の逐条解説では、本判決に関する記載が新たに設けられるに至りました。
本判決は、今後の広告実務にも大きな影響を与え得るものです。例えば、事業者のウェブサイト上での商品紹介が「勧誘」にあたるとすれば、当該サイトでの商品内容、価格、取引条件等の説明中に不実告知や不利益事実の不告知があると判断された場合、当該商品を購入した消費者による取消権が発生し、また、そのような広告は適格消費者団体からの差止請求の対象となります。そのため、事業者としては、不特定多数の消費者に向けた広告チラシやインターネット広告であっても、その記載内容から消費者に誤認を生じさせることのないよう、より慎重な検討が求められることとなります。
5.おわりに
消費者契約法に関する規制以外でも、昨年4月に景表法の不当表示への課徴金制度が導入され、本年1 月には自動車メーカーに対し4 億8000 万円程の課徴金納付が命じられるなど、広告表示への規制は近年さらに厳格化しています。各事業者においては、広告規制への違反が重大な経済的リスクや信用棄損につながり得ることを認識した上、自社広告のチェック・管理体制の整備への意識を高めることが重要となります。
※ 1:消費者契約法に基づく差止請求と合わせて、本件チラシの記載内容が優良誤認表示に該当するとして、景品表示法に基づく差止請求がなされました。第一審判決は、サン・クロレラと本件チラシ作成者の一体性、及び、本件チラシの優良誤認表示該当性を認め、同法に基づく配布の差止めを命じました。しかし、原審判決では、サン・クロレラが本件チラシを今後配布するおそれが認められないとして差止めの必要性が否定され、同法に基づく適格消費者団体の請求が棄却されました。
※ 2:消費者庁消費制度課『逐条解説消費者契約法[第2版補訂版]』(商事法務・2015 年)109 頁
※ 3:消費者庁ウェブサイト「岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29 年1月25日(水))」の「2.質疑応答」
忘れられる権利~最高裁判所第三小法廷平成29年1月31日決定について
弁護士 立川 献
1.はじめに
いわゆる「忘れられる権利」に関する判断が下されるものとして注目されていた「投稿記事削除仮処分申立事件」に関して、平成29 年1 月31 日、最高裁が決定をしました。
「忘れられる権利」は、特にインターネット上の情報の拡散防止の観点から、「個人が自己に関する情報の削除又は非表示を求める権利である」等と説明されています。「忘れられる権利」との用語は、平成26 年5 月13 日欧州連合司法裁判所の判決によって注目を浴びるようになったものです。検索事業者最大手である本仮処分の相手方(グーグルインク。ここでは「Y」とします)も、当該判決を受け、EU 領域内のドメインに限定されるものの、検索結果からの削除要請を受け付けるという対応を行っています。
第一審であるさいたま地裁は、過去の犯罪について、その性質によるものの、ある程度の期間が経過した後には、社会から「忘れられる権利」があり、本仮処分申立人(ここでは「X」とします)はこれを有すると述べ、X の申立てを認めました。しかし、最高裁は「忘れられる権利」との表現を用いることを避け、検索結果の削除請求については「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益」に関する問題と捉えたうえ、判示を行いました。
本稿では、事案の概要、最高裁決定の判断をご紹介し、今後の展望等について言及したいと思います。
2.事案の概要
① X は、児童買春をしたとの被疑事実により、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(改正前)違反の容疑で、平成23 年11 月に逮捕され、同年12 月に罰金刑に処せられた。
② ①の本件事実が、X の逮捕当日に報道され、インターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれた。
③ Y は、インターネット利用者に対して、ウェブサイトの検索結果であるURLを当該利用者に提供することを業として行う「検索事業者」である。
④インターネット利用者が、X の居住する県の名称とX の氏名を条件として検索すると、本件事実が記載されたウェブサイトのURL 等の情報が、インターネット利用者に提供される。
⑤そのため、X がY に対し、人格権ないし人格的利益に基づき、本件検索結果の削除を求める仮処分命令の申立てを行った。
3.最高裁決定
最高裁は、「忘れられる権利」という表現を用いることなく、結論としては、Xの抗告を棄却しました。
(1)個人のプライバシー上の利益と検索結果の提供行為の性質
まず、最高裁は、「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきである」と述べました。一方、検索事業者であるY の「検索結果の提供」行為の性質について、「情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」し、「公衆が、インターネット上に情報を発信したり、インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するものであり、現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」としました。
(2)検索結果提供行為の違法性を判断する枠組み
そして、「検索事業者による特定の検索結果の提供行為が違法とされ、その削除を余儀なくされるということは、…表現行為の制約であることはもとより、検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約でもあるといえる」としたうえで、検索結果の提供行為が違法とされるか否かについては、諸事情(当該事実の性質・内容、プライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、その記事の目的・意義、記事等が掲載されたときの社会的状況とその後の変化、記事等において当該事実を記載する必要性等)を踏まえた「当該事実を公表されない法的利益」と、「URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情」を比較衡量して判断した結果、「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」には、「検索事業者に対し、当該URL 等情報を検索結果から削除することを求めることができる」としました。
(3)本事案におけるX の削除要請権
児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は、他人にみだりに知られたくないX のプライバシーに属する事実であるが、児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえ、検索結果は、X の居住する県の名称とX の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると、本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる、として、抗告人が妻子と共に生活し、罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることが伺われることなどの事情を考慮しても、本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない、としました。
4.まとめに代えて
本最高裁決定は、「忘れられる権利」との表現を採用してはいませんが、「忘れられる権利」という考え方が登場したのも、インターネットが広く普及し始めた頃からであり、これを巡る国際的な情勢も未だ流動的な現状において、現時点で判断を行うことなく、将来の判断に委ねたものと考えることができるように思います。
今後、検索結果からの削除請求については、最高裁の定立した比較衡量論に従った判断が蓄積されていくと考えられます。最高裁は明示していないものの、一体どの程度の期間が経過すれば、個人のプライバシー情報が「公共の利害に関する事項」とはいえなくなるのか、という「時間の経過」という要素も、本決定後の裁判例においては重要視されていくのではないかと考えられます。