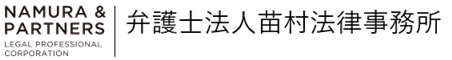アーカイブ
M&Aにおける 表明保証条項の法的意義
[2023年1月 近年の動向と令和以降の各裁判例の概要を追記]
弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村博子
第0 2023年の追補
眠れる日本といわれた平成期、各企業は、それでもM&A等も取り入れて、選択と集中の努力を重ねてきた。M&Aの手法も英米でなされているデューディリジェンス(DD)等の精度を増し、また契約条項も、売り手はなるべく表明保証条項に、「知る限り」とか、せめて「最大限知る限り」と限定しようとし、買い手は、表明保証条項になるべくこのような前提を付さず、さらにDD資料に表明保証違反を示すような資料があった、またインタビューなども行ったとしても、それが表明保証違反に対する補償請求権に影響を及ぼさないとする条項(プロ・サンドバッグ条項)を付加したいと考え、交渉時には攻防が繰り広げられたであろう。しかし、すべてのM&Aがウィンウィンに終わるわけではなく、その後発覚する表明保証違反について、売り手と買い手の妥協が図れず、訴訟になったものも相当数に上り、令和になってからでも10件近い判決が出されている。
その中で相応に重要と思われる6件を添付の表にまとめた。地裁判例しかないため、これが先例だとは言えないものの、2011年に紹介した以下の判例が、いわばデファクトスタンダードして機能していて、上述の契約条項があるか否かにかかわらず、裁判所は、表明保証違反を主張する当事者が善意・無重過失の場合には、補償を認めている。表の6番目の東京地裁2020年10月26日判決は、その補償額の算定方法がDCF法でよいと述べていて参考になる。
アメリカのNY州でも似たような判例が並び、善意・無重過失であれば、買い手は補償請求できるが、売り手の表明保証違反を知っていたはずといえる場合には、補償請求できない。
だからといって契約条項をおろそかにしていいとかDDをいい加減なものにした方がむしろ得ということではない。裁判には多額のコストと労力がかかる(ただ認められている額を見ると訴訟に踏み切るべき場合も相当数あると思われるが)。
この後の第1以降は2011年の執筆であるが、その内容は今も活用いただけるものと考えている。
第1 表明保証条項とは?
M&A の際の、事業譲渡契約、株式譲渡契約など、一定の時点における契約当事者や目的物の内容等について、表明保証する条項が設けられる事が多い。表明保証とは、一定の時点における契約当事者に関する事実や契約目的物の内容等に関する事実について、当該事実が真実かつ正確である旨を、一方当事者が他方当事者に対して表明し、かつその内容を保証するものである※ 1。
英米法では、Representations and Warrantiesと言われ、免責条項(Indemnity Clause)とセットで、表明保証した事項が誤っている際に、それを信じた相手方に生じた損害を補償することとなっているが、日本法上その法的意義、効力については、確たるものがない。
しかし、M&A や欧米流のプロジェクトファイナンスの浸透に従い、表明保証条項の法的効力が争いになった裁判例も出てきた。これらの裁判例を通して、その法的意義を検討する。
第2 近時の表明保証に関する裁判例の概要
① 東京地裁平成18 年1月17 日判決
〔事実関係〕
X が、Y1 ~ Y3 との間で、監査法人に委任してデューディリジェンス(DD)を実施した後、Y らが保有する消費者金融会社全株式を約2 ヶ月前の時点の貸借対照表に基づく財務状況から評価された株価で買い取るとの株式の譲渡契約を締結した。その後A が評価時前の期において赤字決算回避のため、元本に充当していた和解債権について、利息へ充当したことにして、元本につき貸倒引当金の不計上が判明した。
X は、本件株式譲渡契約におけるAの財務諸表及び貸出債権の残高が完全且つ正確だとの各表明保証条項に違反を理由に、不当に資産計上された利息充当額の損害金を求め、訴えを提起した。
〔判旨〕 判決は、本件和解債権処理に関して、表明保証条項違反を認め、損害賠償請求を認容した。本判決は、「XがY らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることについて善意であることがX の重大な過失に基づくと認められる場合には、公平の見地に照らし、悪意の場合と同視し、Y らは本件表明保証責任を免れると解する余地があるというべきである。」とも判示しながら、本件では、DD は買主の権利であって義務ではなく、買収交渉の限られた期間に行われること、和解債権の精査方法について特段の問題がなく、A の作成した財務諸表等が会計原則に従って処理がされていることを前提としてDDを行ったことは通常の処理であって、それ自体は特段非難に値しないとして、重過失を認めなかった。
②東京地裁平成19 年7 月26 日判決
〔事実関係〕
X は、Y1 から、飲食店の経営等を行うY1 の子会社A に関する業務提携やM&A による買収を持ちかけられて交渉の後、Y ら(Y1 ~ Y3)との間でA の株式譲渡に係る基本契約を締結した。
X は、A の資産は、契約前のY らの説明よりはるかに価値の低いものであり、原告が合計3 億円あまりの損害を被ったとして、Y らに損害賠償請求を求め、出訴した。
〔判旨〕 判決は、本件が企業買収に関することを理由に、表明保証条項は、「企業買収に応じるかどうか、あるいはその対価の額をどのように定めるかといった事柄に関する決定に影響を及ぼすような事項について、重大な相違や誤りがないことを保証したもので、」免責条項は、その保証に違反があった場合に損害補償に応じる旨を定めたものであると解するべきであり、財務諸表の内容が「重要な」点において正確であることを、同条〔6〕が「重大な」不利益が存在しないこと、「重要な事項」について記載が欠けていないことを、それぞれ保証する旨を定めているものと解されると判示した上で、Aの一店舗の中途退去に伴う違約金について、Y2 は賃貸人として、違約金発生を十分判断できたはずで、違約金が発生しないとX に説明した上で、後に違約金があるとするのは、真実保証に反するとし、Yらが中途解約による違約金の存在を説明しなかったのは説明義務違反だとして、損害賠償の一部を認容した。
③東京地裁平成19 年9 月27 日判決
〔事実関係〕
X はY1 と、資本提携に関する基本合意し、翌月に業務提携に関する基本合意を締結した(両者を併せて、「本件各提携契約」という)。
本件各提携契約に基づき、Y1 は、新株発行の第三者割当により、X の株式のうち、発行済株式総数の51%を有するに至った。翌年Y2 は、証券取引法違反で逮捕され、Y1 は上場廃止になった。X は、Y らの行為により、16 億円の損害を被ったとして、Y1 社・Y2 らに対しては、損害賠償請求を求め、出訴した。
〔判旨〕 判決は、企業買収において資本・業務提携契約が締結される場合、企業は相互に対等な当事者として契約を締結するのが通常であり、私的自治の原則が適用され、「特段の事情」がない限り、上記の原則を修正して相手方当事者に情報提供義務や説明義務を負わせることはできないとした。そして、「特段の事情」の有無について、本件資本提携契約の契約書7 条は、X の表明保証責任の内容が財務状況を含めた多数の項目にわたり定められているのに対し、Y1 の表明保証責任の内容はわずか3項目にすぎず、かつ、財務状況における表明保証責任は定められていないことが認められる、X とY1 とは、本件資本提携契約について、Y1 の財務状況を買収対象会社であるX に対し表明保証する必要がないと理解していたものと認定するのが相当であって、本件資本提携契約を承認した原告取締役会の審議においても、Y1 の財務状況を問題とした質疑等は見当たらないことからも裏付けることができるとして、『特段の事情』を認めず、損害賠償責任を否定した。
④東京地裁平成22 年3 月8 日判決
〔事実関係〕
X が、被告Y ら(Y1 ~ Y8)との間でY らから被告A の発行済株式すべてを譲り受ける旨の株式譲渡契約を締結した。そして、譲渡代金の一部を支払った。
X は、Y らが上記株式譲渡契約における株価算定と企業価値についての重要な点についての虚偽がないことの表明保証条項に違反していたため、上記株式譲渡契約を解除した旨主張して、Y らに対し、支払済みの譲渡代金約6 億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め出訴した。さらに、Xは、A に対し、X からY1 ~ Y4 に、それぞれA の株主名簿の名義を戻すよう求め、出訴した。
〔判旨〕 本判決は、本件株式譲渡契約の解除権(解除原因)の有無について、その認定事実を踏まえ、Xの表明保証違反の主張について子細な検討を加えた結果、本件株価算定書の重要な点に虚偽があった旨及びA の財務状況に悪影響を及ぼす重要な事実が生じた旨のXの主張はいずれも採用できないとして、解除権(解除原因)を前提とするXの本訴請求は、いずれも理由がないとして、これを棄却した。
第3 ①~④の裁判例から読み取れる表明保証条項の法的意義
以上の裁判例を踏まえると、M&A において、表明保証条項を設けた場合、基本的に、条項どおりの法的効果が認められ、これに違反する場合には債務不履行として民法415 条が適用されている。ただし、中には、買主側の事例であるが、ある事項に関し、表明保証条項がなかったこと等を理由として、表明保証条項に記載のない事項については、責任を負わない趣旨であると判断するものがある(③)。
以上からすれば、表明保証条項が、売手に責任の内容を特定する機能を有しているといえよう。買手の側としては、売手に責任を負わすべき事項すべてについてできるだけ詳細に表明保証条項を設ける必要がある。
裁判例の中には、企業買収の特殊性や公平の見地を理由に、表明保証条項が限定的に解釈されたり、表明保証条項違反の不知について重過失があれば表明保証責任が免責されると判断しているものがある(①、②)。表明保証条項は、できるだけ解釈の余地のないように、一義的な文言で条項を作成することが必要である。また、表明保証条項の対象となった事項について一応のDDを実施し、表明保証条項の前提となっている事実や計算書類について、調査をすることも必要であるといえよう。
※1 江平亨「表明・保証の意義と瑕疵担保責任との関係」弥永真生ほか編・現在企業法・金融法の課題82貢
住宅地図の著作物性を認めた裁判例
-東京地裁令和4年5月27日判決(ゼンリン住宅地図事件)-
弁護士 田中 敦
1 はじめに
令和4年5月、東京地裁により、住宅地図が著作物にあたると判断し、無断複製・譲渡等の差止めを命じるとともに、多額の損害賠償請求権を認めた判決(東京地裁令和4年5月27日判決、以下「本判決」といいます。)が下されました。
本稿では、いかなる場合に地図への著作権による保護が認められるのかを中心に、本判決の判示内容をご紹介し、本判決を踏まえて、日常的に行われている地図の利用にあたり注意すべき点を検討します。
2 事案の概要
原告である株式会社ゼンリンは、住宅地図を作成・販売する事業者です。
被告らは、長野県内を中心に、広告物の各家庭ポストへの投函(ポスティング)や住宅購入相談を業とする有限会社及びその代表取締役です。被告らは、原告作成の住宅地図(以下「本件住宅地図」といいます。)を購入し、これを適宜縮小して複写し、集合住宅名や配布禁止宅名等の必要な情報を書き込んだポスティング用地図を作成して、これをポスティング業務に利用していました。また、被告らは、ポスティング用地図の画像データをフランチャイジーに対し交付したり、自社のウェブサイトに掲載したりしていました。
原告は、被告らによる行為が本件住宅地図の著作権(譲渡権、公衆送信権)の侵害にあたると主張し、これら行為の差止めを求めるとともに、被告らに対し、著作権法114条3項に従った使用料相当額の一部として3000万円の損害賠償を請求しました。
3 争点及び判示内容
(1) 争点
本件の争点は多岐にわたりますが、中心的な争点は、本件住宅地図が著作物として保護されるか否かでした。本稿では、本件住宅地図の著作物性、及び、原告に生じた損害額の争点に絞って検討の対象とします。
(2) 本判決の判示内容
被告は、本件住宅地図は機械的に作成されたものであり創作性が発揮される余地は乏しいと主張しつつ、「都市計画基本図において・・・著作権法上の保護の対象となる部分は極めて限定的である」などと述べた国土地理院の見解[1]を引用するなどして、本件住宅地図の著作物性を争っていました。しかし、裁判所は、本件住宅地図につき、イラストを用いることにより施設がわかりやすく表示されたり、道路等の名称や建物の居住者名・住居表示等が記載されたり、建物等を真上から見たときの形を表す枠線である家形枠が記載されたりするなど、長年にわたり、住宅地図を作成販売してきた原告において、住宅地図に必要と考える情報を取捨選択し、より見やすいと考える方法により表示しているとして、その創作性を認めました。他方で、被告が指摘する都市計画基本図についての国土地理院の見解は、本件住宅地図のような住宅地図一般について述べられたものではないとして、被告の主張を排斥しました。結論として、裁判所は、本件住宅地図が著作物にあたることを認め、ポスティング業務の対象地域、期間、頻度等から、被告らが、合計96万9801頁の本件住宅地図を複製したことを認定しました。
そして、裁判所は、本件住宅地図の複製の許諾には原告に対し1頁あたり200円を支払う必要があったことから、被告の複製行為による使用料相当額(著作権法114条3項)が1億9396万0200円に上り、これに弁護士費用1900万円を加えた計2億1296万0200円の損害が原告に生じたと判示しました。(ただし、本判決は、原告が請求した3000万円の範囲で損害賠償を命じました。)
4 解説
(1) 地図の著作物の創作性
地図の著作物は、著作物を例示した著作権法10条1項各号のうち、同項6号(地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物)に定められた著作物の類型です。
過去の裁判例では、地図は、一般に、「地形や土地の利用状況等を所定の記号等を用いて客観的に表現するもの」であって、創作性を認め得る余地が少ないのが通例であるとされつつ、それでも、「記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験、現地調査の程度等が重要な役割を果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表われ得る」ために、これらの情報の取捨選択及び表示方法を総合的に検討して著作物性が判断されるべきと判示されていました(富山地裁昭和53年9月22日判決・無体集 10巻2号454頁、東京地裁平成13年1月23日判決・判時1756号139頁)。このように、地図については、素材の選択及び配列における創作性の有無によって著作物性を判断する編集著作物(著作権法12条1項)と同様の判断基準によって、その著作物性が検討されてきました。
(2) 本件住宅地図の著作物性
本件住宅地図の著作物性について、本判決は、「地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して判断すべきものである」と述べ、上記の過去の裁判例に沿った判断基準に従って検討しました。
本判決は、本件住宅地図の著作物性を認めるにあたり、原告が、住宅地図をより見やすくするために、長年にわたって、記載すべき情報の取捨選択や表示方法についての検討作業を行っていた点を重視しています。特に、建物を真上から見た形を表す家形枠については、調査員の現地調査をも踏まえて作成されたものであることが指摘されています。その他にも、本件住宅地図には、表示方法の工夫として、目盛りや地図番号の記載により検索を容易にしている点、信号機やバス停等をイラストで表示している点、居住者名や店舗名を家枠内に記載して住所表示を分かりやすくしている点といった特徴があるとされ、これら特徴を組み合わせることで、地図全体として創作性を獲得すると判断されたものと考えられます。
なお、前述のとおり地図の創作性については限定的に解されることもあり、類似の表現について翻案権侵害の成立の余地が一定限られる可能性がありますが、本件については、被告らが本件住宅地図を切り貼りするなどしてポスティング用地図を作成したことにつき、複製権侵害が認められていることから、デッドコピーに近い態様で本件住宅地図が複製されていたものと思われます[2]。
(3) 使用料相当額の損害
本判決は、著作権法114条3項の使用料相当額として、原告には2億円近くもの損害が生じたことを認めています。当該金額は、一般的な相場に従ってではなく、原告が設定していた実際の使用料額に従って算定されたものであり、この使用料相当額の算定方法について考え方は、過去の裁判例(知財高裁平成21年9月15日判決・裁判所ウェブサイト等)の判示に沿うものです。
従来は損害賠償額が少額にすぎることが問題視されることもあった著作権侵害の事件に関して、本判決が、原告の一部請求(3000万円)の範囲で支払いを命じたものの、高額の賠償額が認められる可能性を示したことは注目に値します。
5 地図の利用にあたり注意すべき点
現在、ウェブ上の地図サービスの機能がさらに充実してきたことで、PCやスマートフォンによる地図利用は、個人・企業を問わず、日常的に行われています。
市販されている住宅地図だけではなく、ウェブ上で提供されている地図サービス(Google Map、Yahoo!地図、マピオン、MapFan等)についても、各事業者が、記載すべき情報を取捨選択し、その表示方法に工夫を凝らして地図を作成したものと考えられ、本件住宅地図と同様に、地図の著作物として保護される可能性が相当高いものと思料します。
本判決を機に、各企業としては、日常的に利用されている地図が著作権で保護される可能性があり、無断での複製・配布やアップロードが権利侵害にあたり得ることを、地図サービスを利用する従業員らに理解してもらうことが重要であるといえます。
以上
[1] 地理空間情報活用推進会議「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン」(平成22年9月)23頁 https://www.mlit.go.jp/common/000124117.pdf
[2] 本判決中では、複製行為の立証のために、訴訟提起に先立ち、被告らの地図の検証を求める証拠保全が申し立てられ、検証が実施されたことが記載されています。
わが国における競争法によるフリーランスの保護の現状と今後
弁護士 田中 敦
1 はじめに
最近、フリーランスとして働く人々を契約上保護するための新法制定に向けた動きが活発化しています。その背景には、働き方の多様化やリモートワークの普及による近年のフリーランス人口の増加、フリーランスへの現行法の適用の限界が問題視されたことがあります。
本稿では、主に競争法の適用を念頭に置いて、わが国におけるフリーランスの保護に向けた近年の議論と法改正の動向をご紹介します。
2 フリーランスとは
フリーランスとは、後述の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」では、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者のことをいう」と定義されています。
フリーランスとして働くことが多い業種としては、工事請負業(いわゆる一人親方)、エンジニア、作家、俳優、通訳、スポーツ選手といった職業が挙げられます。令和2年5月に発表された内閣官房による調査では、わが国において、フリーランスとして働く者の試算人数は、462万人に上るとの結果が報告されています[1]。
3 法令によるフリーランスの保護
フリーランスについては、委託元の事業者との情報量や交渉力の格差から、一方的な契約条件を強いられたり、代金不払や理不尽なやり直し要請がなされたりすることが問題となる場合があります。
フリーランスは、特定の企業等と雇用関係にないことから、原則として、労働基準法や労働契約法の適用対象とはならず、労働条件の不利益変更の禁止や賃金全額払いの原則等の労働法上の保護を受けることができません。(なお、委託元が提供する設備等を利用して役務提供をする場合には、委託元がフリーランスに対し安全配慮義務に基づく責任を負う可能性があります(最判平成3年4月11日・判時1391号3頁)。)
フリーランスと委託元の事業者との取引については、独占禁止法(優越的地位の濫用等)や下請法による規制の対象になり得ます。しかし、フリーランスへの発注を行うのが小規模な事業者であることも多く、そもそも資本金1000万円以下であるとして下請法の適用対象(下請法2条7項の「親事業者」)に該当しなかったり、フリーランスに対して必ずしも優越的地位にあるとはいえなかったりする事情から、これら法令の規制が及ばない場合もありました。加えて、フリーランスの取引についてはその金額が比較的小さいこともあり、フリーランスとして働く者が、法令違反を理由に救済を求める事例はそれほど多いとはいえませんでした。
4 競争法によるフリーランス保護の議論の発展
(1) 人材と競争政策に関する検討会報告書
平成30年2月15日、公取委は、事業者による個人の役務提供者に対する行為への独占禁止法適用の考え方をまとめた報告として、「人材と競争政策に関する検討会報告書」を公表しました。
同報告書では、個人の役務提供者への行為が優越的地位の濫用の適用対象になり得ることが明記された上、フリーランスとの取引で問題となることが多いと思われる類型(役務提供者の専属義務、成果物の利用制限、事実と異なる取引条件の提示等)を挙げて、それぞれについて、優越的地位の濫用に該当するか否かの考慮要素を示しています。例えば、個人の役務提供者に対し専属義務を課すことについては、専属義務の内容や期間、これにより役務提供者へ与える不利益の程度、代償措置の有無、役務提供者との協議の有無、他の取引条件と比べて差別的かどうか等を考慮して判断されることとなります。
同報告書は、フリーランスとの取引が独占禁止法の適用対象になることを明確化したものですが、後述のとおり、現在の運用としては、下請法を適用した取締りが中心となっています。
(2) フリーランス保護のためのガイドライン
令和3年3月26日、内閣官房、公取委、中小企業庁及び厚生労働省の連名により、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表されました。
同ガイドラインでは、フリーランスとの取引につき、「下請法と独占禁止法のいずれも適用可能な行為については、通常、下請法を適用する」との方針が記載されています(同ガイドライン3頁)。また、同ガイドラインでは、フリーランスとの取引において締結すべき契約書のひな形が添付されるなど、フリーランスとの間の契約内容について一定の踏み込んだ見解が示されています。
(3) 法改正の検討と法執行の現状
令和4年9月13日、内閣官房により、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」が公表され、意見募集が行われました。当該資料は、あくまで法整備の方向性を示したものにすぎませんが、下請法の適用対象とならないフリーランスとの取引についても、業務委託時の書面交付義務、役務提供から60日以内の代金支払義務、受領拒否や返品等の禁止といった下請法と同種の規制を適用する方針が示されています。また、遵守事項の違反があった場合には、その違反事実をフリーランスが行政機関へ申告することのできる制度を創設することも検討されています。当初は、下請法を改正する方向での検討がなされているとの報道もありましたが、その後の公取委の事務総長の会見によれば、下請法改正ではなく新法を制定する方向で検討されていると述べられています[2]。
また、公取委による法執行の現状として、同年5月に公表された令和3年度の運用状況では、フリーランスに関連する下請法違反の実例として、事業者名は明記されていませんが、多数の違反事例が報告されています[3]。さらに、同年10月に公取委が公表した活動報告によれば、令和4年度の体制の強化として、「下請取引及びフリーランスやスタートアップとの取引に係る執行体制の強化」のための人員を14名増員したことが報告されています[4]。
5 さいごに
以上のとおり、下請法の適用を中心として、フリーランスとの取引に対する法執行が活発化しており、公取委による取締りは今後もさらに拡大していくことが予想されます。
また、フリーランス保護のための新法が制定され、委託元の事業者の資本金額にかかわらずフリーランスとの取引が下請法と同様の規制の対象となれば、サプライチェーンの全体を通して、委託契約の見直しとコンプライアンス確保のための体制構築が求められる可能性があります。現時点では、法令の形式や具体的内容は全くの未定であるものの、新法制定に向けた今後の動向を注視することも重要となります。
以上
[1] 内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」(令和2年5月)25頁。https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/report.pdf
[2] 公正取引委員会「令和4年10月19日付 事務総長定例会見記録」https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2022/oct_dec/221019.html
[3] 公正取引委員会「令和3年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」(令和4年5月31日)別紙2 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/may/R3_honbun.pdf
[4] 公正取引委員会事務総局「公正取引委員会の最近の活動状況」(令和4年10月)62頁https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/katsudou_R4_10.pdf
弁護士 苗村博子
皆さん、今回は、少し趣向を変えて、新人をご紹介したいと思います。と申しましても、新しい弁護士さんでも秘書さんでもありません。
アバターとまでは言えないのですが、商子(しょうこ)さんと来人(らいと)君というウェブ上のキャラクターです。
製造会社に新入社員として入社したしょうこさんは、知的財産部に配属されました。T弁護士の後輩なのですが、大学で知的財産権を学んだことはなく、T先輩にいろいろ質問してきます。すぐに仲間に入りたがるN弁護士も加わって、知的財産とはどのようなものなのか、どんな種類のものがあるのか、重要判例などもご紹介しながら、T弁護士、N弁護士としょうこさんの会話形式でのレクチャー?が展開していきます。
らいと君は、かつてN弁護士の個人情報保護法のクラスで講義を受けたそうです。今の若者らしく、果敢に起業をしたというらいと君もいろいろ知的財産のことを聞きたいようで、N弁護士の事務所にやってきては様々な知的財産法の質問を投げかけます。
N弁護士やT弁護士は時に二人の鋭い質問や、基本的な質問だけれど、答えるのがとても難しい質問にたじたじとする場面もありつつも、秘密保持義務に反しないように気を付けながら、これまでの取り扱った事件の苦労話も交えて二人に話をしていきます。
まだまだ、おはなしは始まったばかりで、
https://www.chizai.info
にアクセスいただけるとその内容がご覧いただけます。
新入社員のご研修や、いまさら聞けない・・・という中堅の皆様にも楽しんでいただけるようなウェブサイトにしたいと考えております。
ご推察のとおり、N弁護士編は苗村博子が、T弁護士編は田中敦が執筆しております。なお、しょうこさん、らいと君、N弁護士、T弁護士の作画は、当事務所の職員で、職務著作ということで、著作権は事務所のものとなり、万が一に備え、著作者人格権の不行使も約束してもらっています。こんな話もT弁護士が、らいと君に教えていく内容の一つとなると思います。
末永く、可愛がってもらえるキャラクターに育ってくれるといいなと思っております。ぜひ、一度アクセスしてみてください。
ブランド名のハッシュタグ使用につき商標権侵害が認められた事例
弁護士 田中 敦
1 はじめに
SNS 上の投稿で用いられるハッシュタグは、フリマアプリ等で商品紹介のためにも使われることがあります。ところが、令和 3 年 9 月、商標登録されたブランド名をハッシュタグとして無断で使用する行為につき、商標権侵害に該当するとの判決が下されました(大阪地裁令和 3 年 9 月 27 日判決・判時 2523 号 117 頁、以下「本判決」といいます)。
本稿では、本判決の判示内容をご紹介した上、商標的使用についての考え方を踏まえて、他人の商標を表示するにあたり注意すべき点について検討します。
2 本判決の判示内容
(1)事案の概要
原告は、指定商品を「かばん類」等とする標準文字商標「シャルマントサック」(以下「本件商標」といいます)の商標権者です。被告は、みずから製造するかばん等の商品をフリマアプリの「メルカリ」に出品して販売していた個人です。
被告は、メルカリの商品紹介ページ上で、被告の商品(巾着型バッグ)の紹介をするにあたり、検索用のハッシュタグを付した「# シャルマントサック」との表示をしていました。ただし、被告は、同ページ上の商品説明として、商品がハンドメイド品であると明記していました。また、被告は、「# シャルマントサック」や「# ドットバッグ」等の多数のハッシュタグを上下に並べた直下に、「好きの方にも…」という文章を記載していました(写真1 及び2 参照)。ただし、同ページ上では、被告の商品が、原告が販売する「シャルマントサック」のブランドの真正品か否かについては記載がありませんでした。原告は、上記の被告によるハッシュタグの使用が、本件商標の商標権侵害にあたると主張して、その差止めを求めました。
(2)争点
本判決で争点とされたのは、①「業として」の使用の有無、②商標的使用の有無及び③差止めの必要性の 3 点であり、本稿では争点②の商標的使用の問題を中心に論じることとします。
(3)裁判所の判断
争点①のうち「業として」使用されたか否かについて、被告はバッグの製作・販売が単なる趣味であると主張しましたが、裁判所は、被告が少なくとも 1 年以上にわたり複数商品を販売していたことから、「業として」商品を譲渡する者(商標法 2 条1項1 号)であると判断しました。
また、争点②の商標的使用の有無について、被告は、ハッシュタグとは、「#」に続く文字列が表す特定の情報を結び付けるものであり、そのような情報のウェブサイト上の所在場所を表すものにすぎず、また、被告がハッシュタグに続いて「好きの方にも…」との文章を記載していたことなどからも、被告による「# シャルマントサック」の表示は、メルカリユーザーの検索の便宜を図ったものであって、商品の出所を表示する態様により使用したものではないと主張しました。しかし、裁判所は、本件商標と「# シャルマントサック」との類似性を端的に認めた上、標的使用の有無について、ハッシュタグは、原告の商品やブランドの情報を検索する利用者を被告のサイトへ誘導するために用いられたのであり、当該サイトの商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものであると認識させると指摘しました。その上で、本判決は、ハンドメイド品であることや「好きの方にも…」との各表示について、被告の商品が被告みずから製造したものであることや、「シャルマントサック」の商品そのものではなく、同商品を好み又はこれに関心を持つ利用者に推奨される商品であることを示すとも理解し得ることを認めつつ、被告の商品が「シャルマントサック」との商品名又はブランド名であるとの認識を失わせるに足りるものではなく、これと両立し得る表記であるとして、被告によるハッシュタグの表示が、商品の出所を表示する態様により使用されたものであると判示しました。
そして、裁判所は、被告がメルカリのアカウントを維持していること、被告のフォロワー数(636 名)から、争点③ の差止めの必要性を認めて、原告の請求を認容しました。
3 解説
(1)ハッシュタグとは
ハッシュ記号(#)と特定のワードを一体化させたハッシュタグは、Twitterや Instagram 等の SNS を中心として2010 年頃から急速に広まったものであり、「#」に続くワードをタグ付けし、SNS の利用者が当該ワードに関連する投稿を検索することを容易にする機能があります。ハッシュタグを活用することで、閲覧者としては、関心のあるワードに関連する投稿を簡単に見つけ出すことができ、また、投稿者としては、多くの同じ関心を持つ閲覧者を集めることで閲覧数を増やすことができます。
メルカリ等のフリマアプリが広まってからは、出品者による商品紹介のページでもハッシュタグが用いられるようになりました。フリマアプリでのハッシュタグは、閲覧数を増やすとともに、「#20 代 # スカート # カジュアル」のように、商品の特徴を伝える目的でも使用されます。
(2)商標的使用
商標権侵害が成立するためには、商標が、需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができる態様、言い換えれば商品又は役務の出所を明示する態様で使用されていなければなりません(商標法26 条1 項6 号)。このような態様による使用を、商標的使用といいます。
出所を明示する態様ではなく、意匠的・装飾的に用いられたり、説明的・記述的に用いられたりする場合には、商標的使用にはあたらず商標権侵害が成立しません。過去の裁判例では、被告が「煮物万能だし」等の容器に「タカラ本みりん入り」と表示した行為につき、「タカラ」の登録商標を有する原告が商標権侵害を主張した事案において、裁判所は、被告の商品の「タカラ本みりん」との表示は原告の商品が素材として入っていることを示す記述的表示であって、出所を示す態様(商標的使用)での表示ではないとして、商標権侵害を否定しています(東京地裁平成 13 年 1 月 22 日・判時1738 号 107 頁)。
(3)本判決の解説
まず、フリマアプリでのハッシュタグが商品の特徴を示すために用いられることからすれば、ハッシュタグにブランド名を付することが、商品の出所を示す態様での表示にあたり得るという本判決の判示は、説得力があるものと考えます。ただ、本判決の被告は、商品紹介ページで、ハンドメイド品であることを明記し、ハッシュタグに続いて「好きの方にも…」といった表示をしていました。しかし、本判決は、これらのいわば「打ち消し表示」は、被告の販売する商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名であるとの利用者の認識と「両立し得る」ものであると述べ、出所の誤認のおそれを打ち消すには足りないと判断しました。
そうすると、ハッシュタグにブランド名を表示しつつ、「本商品は〇〇(ブランド名)の商品ではありません」などと、販売商品がブランドの真正品であることと明らかに両立し得ない表示をした場合には、本判決の射程が直ちに及ぶとはいえず、さらなる検討を要するようにも思えます。もっとも、過去の裁判例上、裁判所が、出所表示機能を否定するための打ち消し表示の効果を限定的に解している例もあり(大阪地裁平成 29 年 1 月31 日判決・判時 2351 号 56 頁)、一定の打ち消し表示があるからといって、商標的使用が直ちに否定されると考えるべきではありません。
(4)他人の商標を表示する上での注意点
SNS やフリマアプリでは、現在もハッシュタグが多用されており、商品の出品者が、商標権侵害を特に意識することなく、他人のブランド名をハッシュタグ化してしまう場合も少なくありません。本判決を前提とすれば、他人の登録商標を無断でハッシュタグとして用いることは、商標権侵害のおそれが大きい行為であるといえます。
このことは、フリマアプリでの商品販売のみならず、SNS での商品やサービスの紹介であっても同様です。各企業において SNS を利用した販売促進が一般的になっており、企業アカウントであっても個性的な投稿をするアカウントが注目されていますが、SNS 担当者としては、本判決の判示を踏まえ、他社の社名やブランド名の表示には十分注意すべきことを理解しておくことが重要です。
(写真1[1])

(写真2[2])
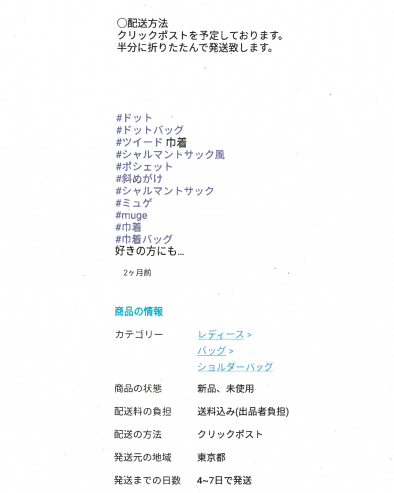
[1] 裁判所ウェブサイト・知的財産裁判例集・大阪地裁令和3年9月27日判決・添付文書2(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/090606_option2.pdf)6頁目より引用。
[2] 裁判所ウェブサイト・前掲注1・7頁目より引用。
国際契約に関する紛争解決手段-訴訟?仲裁?
弁護士 苗村博子
紛争解決条項(Dispute Resolution)
国内の企業間での契約では、紛争解決条項はもっぱら専属管轄、すなわちどの裁判所で紛争を解決してもらうかを定めることがほとんどですが、国際契約となりますと、紛争解決を訴訟で行うか、仲裁機関に判断を委ねるべきか、からまず検討することになります。
また、第三者の判断を求める前に、当事者間での協議を前提条件としたり、調停を前置させることを定める場合もあります。以下にそれぞれの違いを表にまとめています。
| 調停 | 仲裁 | 訴訟 | |
| 機関 | JIMIKなど私的機関 | ICC,AAA,SIAC,JCAA,JAMSなど様々な私的機関 | 裁判所 |
| 費用 | 低廉 | 高額 | 低廉 |
| 強制執行のための
手続 |
執行国がシンガポール条約に加盟していれば、調停内容が執行可能となる。日本は未加盟。 | 執行国が、NY条約に加盟していれば、仲裁判決の執行が可能となる。日本は、加盟国で、仲裁判決の執行については、仲裁法45条以下に定める。 | 外国判決の承認執行手続は各国の民事訴訟法や規則が定める。日本での執行は、民事訴訟法118条以下に定める。 |
| 公開性
|
非公開 | 非公開 | 多くの国で公開 |
| 上訴の可否 | 双方の合意によるので上訴は考えられない。 | 一審制、上訴不可
|
多くの国で上訴可能。日本は三審制 |
国際契約の専門家はこれまで仲裁を勧めてきましたし、また現在日本では、日本国際紛争解決センター等を通じて[i] 政府自体が仲裁制度をもっと活用しやすくしようとしています。ただ世界ではすでに仲裁の問題点である、上訴ができないこと、高額の費用や判断までの時間の長さ、判断者が私人であることなどから、仲裁離れが進んでいるといわれています。私もある事件でこの仲裁の問題点を実感しております。
したがって、今契約上のアドバイスを求められたら、被告地での訴訟を中心に検討するようお伝えすることになるかと思います。こちらが訴訟を起こす場合には、日本の裁判所の方が、勝手がわかっていてよいというものの、いざ判決を執行するには、被告地の裁判所の関与が何らかの形で必要となるうえ、中国のように日本の裁判所の判決の執行を認めてくれない国もあるため、結局は被告地の裁判所で裁判をする方が早い解決に結びつくように思います。もちろん、被告地の裁判所は、自国の被告に有利な判断を下す可能性がありますが、それはそのような国の相手方と契約を結ぶ際のいわばカントリーリスクといわざるを得ません。ただし日本と違い裁判所でも賄賂が横行している国や、第一審に 10 年かかると言われるインドのような場合は、仲裁の方がよいかと思われます。
欧米の国では、日本の裁判所の判断は予測可能性がないとして、日本の裁判所に専属管轄を持たせようとすると大いに反発されますが、被告地の裁判所を選ぶというのは、紛争解決手段の基本中の基本なので、契約相手もなかなか文句が言えないと思われます。ちなみに、私自身は日本の裁判所の判断の予測可能性は相応に高いものと思っています。選挙で選ばれ、あまり法知識がない裁判官がいる国や陪審員に事実認定を任せている米国の多くの州に比して、日本の裁判所の判断は、はるかに予測可能性は高いものの、そもそも日本語で全ての手続きが進むこと、日本の法令は若干英訳が進められているものの、日本の判例が英訳されているという話はなく、かような言語的な障壁から予測が困難と考えられているものと思われます。
コモンローの国の契約相手であれば、被告地の裁判手続きもコモンローに従いますので、その規模感はともかく、手持ち文書の相手方への開示(Production of Documents) や 供 述 録 取 手 続 き(Deposition)といったディスカバリの制度があり、これが実施されます。したがってこちらが訴える場合には、相手方の手元にある証拠を日本の訴訟では考えられないくらい広範に獲得することができることになります。被告地管轄の紛争解決条項にしておくと、契約相手は日本で裁判をしなければなりません。証拠収集方法の拡充については、弁護士会からも再三提案しているのですがなかなか実現できず、したがって、契約相手は当方の手持ち資料へのアクセスに苦労することになるのです。かようなことから、被告地の裁判所を選択するのも一定の合理性があるかと思う次第です。仲裁を選ぶのは、よほど秘密性を高く保つ必要のある場合に限ることとなりそうです。
ここからは余談となりますが、今になって国際紛争の解決に仲裁手続きを推そうとする日本と違って、米国は、仲裁での解決を望ましいとする傾向にあるといわれてきました。確かに仲裁手続きはすべて私的機関が担当し、その費用も各当事者が負担します。訴訟は、日本もですが、国民の基本的な権利としての裁判を受ける権利に対応するもので、国民の税金で運営されています。この運営にかかる費用は、訴訟に対して当事者が払う裁判費用だけでは到底まかないきれません。契約に関することは、なるべく仲裁で解決してもらう方が、裁判所の負担を軽くできてよいというのが、これまでの米国連邦裁判所の考えであったと思われます。しかし 2022 年になって 5 月 23 日[ii]、6 月 15 日[iii]と相次いで、このArbitration Favorable という考えを否定する連邦最高裁判決が出されています。これらの判断は、いずれも労働者が使用者に対して残業代等の不払に対し、自分に対する未払金の支払いだけでなく、(クラスアクションとは異なりますが )、他の従業員を代表して支払いを求め、または州政府がかような未払いを行っている企業に対して民事罰を下すための訴訟(Qui tam Litigation といいます)を提起したものです。5 月 23 日の Morgan 判決の事件では、原被告間の労働契約には紛争解決手段として仲裁に付すとされていたにもかかわらず、その点を主張せず、提訴から半年くらいたってから被告が仲裁への移行申し立てをしたという事案でした。最高裁は、それまで第 8 巡区連邦高裁が出していた、仲裁への移行を認めないのは、その時点で仲裁に付すことが、原告に不利益を及ぼす場合に限るとする要件について、かような要件は連邦仲裁法(Federal Arbitration Act)が予定するものではないとして、この要件を排し、仲裁への移行を認めませんでした。
6 月 15 日判決は、Qui Tam 訴訟は本来州が行うべきところ、その原告(Relator と呼ばれます)が代わりに起こしたものであり、州には被告との間でかような仲裁に付すとの合意はないとして、やはり仲裁への移行を認めませんでした。第 8巡区連邦高裁が出していた、「相手方の不利益がある場合のみ」という要件は、それまでできるだけ紛争は仲裁で解決すべきする考えを具現化したものととらえられていたもので、また仲裁は仲裁合意をした当事者間でなされるものというのは、仲裁の基本ですから、その基本に忠実にすべしとの連邦最高裁の新しいポリシーを示したものとされています。
折角センター等も作って仲裁を勧めようとの日本政府の判断ではありますが、これまで仲裁が基本だったからとの理由で、安易に仲裁を紛争解決手段に選ばないことも重要かと考えます。ただどうしても仲裁を選ばざるを得ない場合、どの仲裁機関を選択するかも重要な問題となってきます。費用感や信頼の高さ、日本からの距離、相手方の応じてくれやすさなどを総合的に考えるとシンガポールのSIAC となるのでしょうか。
[i] https://idrc.jp/
[ii] Morgan v. Sundance
[iii] Viking Cruise Lines, Inc. v. Moriana
雇用機会均等法9条4項の違反等が争われた事件
弁護士 倉本武任
1.はじめに
女性労働者が妊娠、出産、育児等に関連して職場でハラスメント行為を受けることや、妊娠、出産等を理由として、使用者から不利益な扱いを受けることを、マタニティ・ハラスメント等(以下、「マタハラ等」といいます)と呼ぶこと[1] は広く浸透しているかと思います。このようなマタハラ等に該当する労働者の妊娠、出産、育児休業取得を理由とする解雇・雇い止めに対しては、法令等において個別に禁止規定等が置かれています。労働者に対する解雇の有効性は、労働契約法(以下、「労契法」という)16 条において、解雇権濫用法理が定められていますが、実際に労働審判や訴訟になった場合には、労働者側から個別の禁止規定に該当するとの主張が行われる場合もあります。
本稿では、かかる個別の禁止規定の中でも、妊娠中の女性労働者及び出産後 1 年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇について、事業主は、当該解雇が、妊娠または出産等に関する事由を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とする旨を定める、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下、「均等法」といいます)9 条 4 項違反が争点となった、裁判例(東京地裁令和 2年 3 月 4 日判決〈以下「原審判決」といいます〉、東京高裁令和 3 年 3 月 4 日判決〈以下「控訴審判決」といいます〉を合わせて、以下「本判決」といいます) を取り上げ、本判決の意義等について検討いたします。
2.事案の概要及び争点について
原告は、被告が運営する保育園にパート保育士として就職後、正規職員に登用され、勤務していました。原告の妊娠が判明したことから、原告が平成 29 年 3月末まで勤務し、同年 4 月 1 日以降は、産休に入ることで原告と被告は合意し、その後、原告は出産しました。原告が、平成 30 年 3 月 9 日に復職時期を示して、時短勤務を希望する旨の書類を提出したところ、被告はその後の原告との面談時に、原告に対し、復職させることができない旨を伝え、その際、原告は被告に対して解雇理由証明書の交付を求めました。被告は、「保育園施設長と保育観が一致しないことにより同園への復帰希望をかなえることができず、被告都合による解雇に至った」旨が記載された解雇理由証明書を原告に交付しました(以下、「本件解雇」といいます)。
原告は、本件解雇が客観的合理的理由及び社会通念上相当性があるとは認められず、権利の濫用にあたり、また、均等法 9 条 4 項に違反することから無効であると主張し、被告に対して、労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、賃金支払請求、不法行為に基づく損害賠償請求等を求めました。
本件の争点は、退職合意の成否、本件解雇の有効性、賃金請求権及び賞与請求権の有無、不法行為に基づく損害賠償請求の有無と多岐に渡りますが、本稿では、本件解雇の有効性に関する争点及び不法行為に基づく損害賠償請求の有無について、検討します。
3.本判決における判断
(1)客観的合理的理由及び社会通念上相当性の有無について
被告は、原告の解雇理由として、原告の園長等に対する反抗的、批判的言動が、単に職場の人間関係を損なう域を超えて、職場環境を著しく悪化させ、被告の業務に支障を及ぼす行為であり、就業規則に定める「その他前各号に準ずるやむを得ない事由があり、理事長が解雇を相当と認めたとき」に該当する旨、主張しました。
原審判決は、原告が批判的言動を繰り返したという事実を認めず、質問や意見を出したことや、保育観が違うということをもって、解雇に相当するような問題行動であると評価することは困難であると判断したうえ、認定できる原告の言動等を前提とした場合に、これらが就業規則に定める「その他前各号に準ずるやむを得ない事由があり、理事長が解雇を相当と認めたとき」に該当するとはいえないことから、本件解雇は、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認めることはできず、権利の濫用として、無効であると判断し、控訴審判決も同結論を維持しています。
(2)本件解雇の均等法9条4項違反
原審判決は均等法 9 条 4 項について、
「妊娠中及び出産後 1 年を経過しない女性労働者については、妊娠、出産による様々な身体的・精神的負荷が想定されることから、妊娠中及び出産後 1 年を経過しない期間については、原則として解雇を禁止することで、安心して妊娠、出産及び育児ができることを保障した趣旨の規定」として、その趣旨を明示しています。そのうえで、原審判決は、同項の趣旨を踏まえると、均等法 9 条 4 項ただし書きの「前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」との文言に関して、使用者は、単に妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを主張立証するだけでは足りず、妊娠・出産等以外の客観的に合理的な解雇理由があることを主張立証する必要があると明示しました。そして、原審判決は、前記(1)のとおり、本件解雇には客観的合理的理由があると認められないため、被告が、均等法 9 条 4 項ただし書きの「前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明した」とはいえず、この点においても本件解雇は無効であると判断しています。なお、控訴審では、被告から、本件ではたまたま本件解雇が原告の出産日から 1 年経過しておらず、これにより均等法 9 条 4 項違反とされることは被告にとってあまりに酷である等、主張しましたが、控訴審判決は原審判決の結論を維持しています。
(3)不法行為に基づく損害賠償請求の有無
原判決は、本件解雇が、権利の濫用で無効であるだけでなく、均等法 9 条 4 項違反で違法であることから、被告に不法行為が成立することを認め、また、慰謝料の算定にあたり、均等法 9 条 4 項に違反した事実を考慮しています。控訴審判決も、原審判決の結論を支持しています。
4.本判決の意義等について
労契法 16 条について、解雇に客観的合理的理由があり、社会通念上相当であることの立証責任はそもそも使用者側にあります。本判決の結論だけを見ると、均等法 9 条 4 項ただし書きについて、使用者側で妊娠・出産等以外の客観的に合理的な解雇理由があることを主張立証する必要があると明示した部分は、労契法 16 条において解雇に客観的合理的な理由があることを使用者側で主張・立証しなければならない点と重複し、均等法9 条 4 項ただし書きについて個別の判断を求めているのかは明確ではないように思われます。事実本判決以前、均等法 9 条 4 項違反が問題となった事件[2] では、就業規則所定の解雇事由があり、労契法16 条に違反しない以上、妊娠を理由とする解雇でないことは当然として、労契法 16 条に該当するかどうかだけを問題として、均等法 9 条 4 項に意味を持たせていませんでした。
しかし、原審判決が、あえて均等法 9条 4 項の趣旨について女性労働者が安心して妊娠、出産及び育児ができることを保障する趣旨である旨、明示している点を捉えれば、原審判決は、同趣旨を踏まえて、均等法 9 条 4 項ただし書きが求める使用者側の立証はより厳格なものが必要であることを言わんとしているようにも思えます。均等法 9 条 4 項が、妊娠中等の解雇を原則無効としているのは、同期間中の解雇は、妊娠や出産を理由とするとの推認を前提としていると思われ、そうであれば、使用者側による妊娠・出産等を理由とするものでないことの立証は、かかる推認を覆すような高度の立証を求めているとも考えられます。
本判決の事案は、被告が本件解雇の理由として挙げた事実がほとんど認められておらず、そもそも、本件解雇自体が解雇権の濫用として認められる事例であったため、均等法 9 条 4 項を問題とする実益が乏しく、この点が際立ちませんでしたが、均等法 9 条 4 項ただし書きが、高度の立証を使用者側に求めているとすれば、解雇理由によっては、労契法 16 条の解雇権の濫用にあたるか否かと均等法 9 条 4 項ただし書きに該当するかの判断を異にすることはあり得ると思われます。なお、本判決は、均等法 9 条 4 項に違反した事実自体を理由に不法行為が成立することを認めており、均等法違反が認められた場合には、使用者側には不法行為責任を負うリスクもあります。使用者としては、均等法 9 条 4 項が女性の出産、育児に関する重要な権利を定めたものであることを、十分に理解する必要があると思われます。
[1] 妊娠・出産等については、女性労働者のみが対象ですが、育児休業については、男性労働者も対象となり、パタニティ・ハラスメント(パタハラ)と呼ばれています。
[2] 東京高裁平成28年11月24日判決
憲法の人権規定の私人(特に企業)への直接適用
弁護士 苗村博子
1.今なぜ憲法か?
この事務所報で憲法を取り上げるのは初めてかと思います。ちょうど最高裁による在外邦人の国民審査について投票権がないという立法の不作為は、違憲であり、かつ国家賠償も認めたという判決 [i] が出たところで、また参院選でも憲法改正論が論点とされ、今年は憲法が何かと話題になる年ですね。憲法論というのは堅苦しいので、読む気がしないという方も、この記事はいささかエッセイのようなものなので、気楽にご覧いただければと思います。
実は、このトピックを選んだのは、この最高裁判例に接したからではありません。5 月は学会の大会が多く開かれる月で、最高裁判決の出たその週末は、土曜日に著作権法学会、土曜日、日曜日に民訴法学会が開かれました。そのいずれにおいても、「憲法適合的」という、言葉が取り上げられたことが、この記事を書こうと思った動機です。
2.著作権VS表現の自由
5 月 21 日土曜日の著作権法学会の個別報告では著作権が人権なのか、また表現の自由との衝突をどのように考えるかについて、欧州人権裁判所、欧州司法裁判所の判断を元にご報告がなされました [ii] 。このご発表の中心の一つが、表現の自由という憲法論を持ち出す意義でした。著作権と表現の自由の対決が問題となっているのですから、そこで問題となるのは、著作権者という私人と表現を行う私人の両者における対立です。30 年前の憲法の教科書には、私人間には憲法は直接適用されず、民法 1 条や 90 条を介在させたうえでの間接的効力しかないと説明されていました。
しかし、ご発表を伺って、現在では通説かどうかはともかく、憲法適合的解釈により法律を解する、従って、憲法論は、法律の解釈をする際に、その法律が適用される場面で、いわば直接検討されるというように「憲法適合的解釈」を理解しました。著作権は、日本では一種財産権のように思われていますが、著作者人格権という著作権周辺の権利なども含めると、むしろ表現の自由や幸福追求権といった精神的自由に近い権利、即ち基本的人権のうちでもいわば、より高度の保護が求められる精神的な自由権であるとも考えられそうです。著作権法を憲法適合的解釈によって解釈し、著作権法が、内在的に表現の自由その他の人権を侵害しないように考えられるべきものとして制度設計されていると考えるか、表現の自由は外在的制限根拠となると捉えるかはさまざまな見解があるようです。いずれにしても、これらの憲法に規定されている人権が、ストレートに私人間においても、それぞれの権利の限界はどこかという形で議論されているのだと知ったこと(今までが不勉強なのを自白しているようなものですが)は私のように 30 年間まっとうに憲法を勉強してこなかった者には衝撃でした。
3.民事訴訟と憲法
翌日の日曜日は民訴法学会のシンポジウムにウェブ参加しました。そこでは、裁判官の裁量は、羈束裁量で、憲法の諸原則に拘束されるということが論じられました。裁判官の権限行使は国家権力の発動の最たるものの一つですから、憲法に拘束されるのは当たり前といえば当たり前ですが、多くの法律実務家は、その諸原則はすべて、訴訟法に反映されていて、裁判官は訴訟法にさえ則っていればよいと考えているように思っているのではないでしょうか。しかし確かに、民事訴訟法にもいわば隙間があり、それを埋めるのはより上位にある憲法だということに今一度思いをいたせというのが、ご発表の趣旨の一部であったかと思いました。
民事訴訟は、三権分立という権力間の相互牽制の下、国民の主権を揺るぎなきものにする、そのために裁判官の独立を認めるという国の統治機構制度の一部を構成するとともに、国民の基本的人権の一つである裁判を受ける権利を制度的に保障するものでもあります。そこでは、裁判官は、時に三権分立や自らの権限行使の独立性に甘んじ、この権限行使が自らの自由裁量だと考えて、後者の国民の裁判を受ける権利を侵害しかねないということも考えられてのご発表だったようにも思いました。ドイツでは、裁判官の訴訟指揮権の行使が羈束裁量であって、決して、自由な裁量権が裁判官に許されているわけではないと考えられているとも指摘されていました。
4.今なぜ憲法か-再論―
刑事訴訟法などと違い、著作権法学会や民訴法学会といったあまり憲法と親和性がないと思われる二つの学会で憲法論が発表課題として取りあげられたのか ? 私のような一実務家にはわかりませんが、一つは、複雑化する社会、権利構造、GAFA のようなその存在の外延がはっきりしない、巨大な企業というか、国を超えるような存在が社会に出現し、企業と個人の関係が、双方とも私人であるとのくくり方ができなくなっていること、企業を人権の保護主体としてみる必要があるほど、企業活動が国家行為を凌駕するような状況が生まれていること、国家行為というより、経済活動を直接行う企業にこそ、人権侵害を止める能力があるのではないかと思う事例が増えていることなどがあげられるのかと思います。何度か触れた、英国の現代奴隷法や、我が国の「ビジネスと事件に関する調査研究」にもあるように、企業は、21 世紀にあっては、違法でなければ、利益だけ追求してよいとは、もはや考えられず、他国での事象も含め、直接人権問題を是正するのに役立ちつつ、利益を追求すべきとの考えが強まっていることが影響しているのかと思います[iii] 。
また、裁判官の訴訟指揮といった裁量権行使について憲法論が議論されたのは、それだけ、司法への信頼を高める必要性が増している、そんな社会状況があるのかとも思います。2 割司法と言われて久しいですが、この割合はもしかするとさらに減っているのかも知れず、日本では訴訟は紛争解決手段となっていない、そこには裁判官の裁量に対する不信感も生まれているのではないかとのアカデミズムからの危機感があるようにも思いました。
そして私たち弁護士は、憲法論を主張するときは負けを覚悟しているとき、などと言わず、法律の基礎は憲法にあり、訴訟においても憲法論が必要な際には、ためらわず、これを主張して、裁判官に憲法を土台にした法律解釈をしてもらうこと、それによって、裁判官の守るべき裁判を受ける権利の保障をより明確なものにしてもらう必要があるのだと、2 つの学会に参加して思った次第です。
近頃沈黙して久しく、最高裁の行政見解への追従した判決が目立った今般、立法の不作為について、違憲を宣言した上述の判決は画期的なものといえるかと思います。
[i] 令和4年4月20日最高裁判決
[ii] 京都教育大学教育学部講師比良友佳理科先生ご発表「著作権と表現の自由-調整アプローチに関する国際比較と日本法への示唆-」
[iii] 話が若干それますが,ウクライナ侵略を止める実効性を持っているのは現在では残念ながら,国際法でも外交術でもなく,経済制裁といういわば兵糧攻めです。それは,ロシアと交易のある各国際的な企業に同国の企業との取引を,ウクライナの人々の命や健康の保護のため,止めるという決断をせまる事になっています。