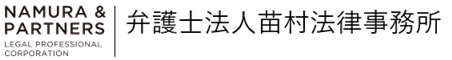アーカイブ
独占的販売代理店契約の更新拒絶について
不法行為の準拠法が問題となった事例
弁護士 中島康平
【はじめに】
今回は,化粧品の独占的販売代理店契約の更新拒絶に関連して,不法行為の準拠法及び共同不法行為の成否が問題となった東京地裁平成22年1月29日判決・判タ1334号223頁をご紹介します。第18号でご紹介しました東京地裁平成22年7月30日判決・判時2118号45頁(18年にわたって継続した販売代理店契約の解消が問題となった事例)とは異なり,本件は,契約書が取り交わされていた独占的販売代理店契約の解消に関する紛争です。
【事案の概要】
化粧品の製造,販売,輸出入等を目的とする日本法人であるXが,昭和61年3月からフランス法人であるAとの間で,化粧品(以下「本件商品」といいます)の独占的販売代理店契約を締結し,その後,契約を更新あるいは新たに締結して取引を継続しました。平成14年12月に締結された独占的販売代理店契約(以下「本件契約」といいます)では契約期間は4年とされ,本件契約及び本件契約に伴う合意事項には,手続及び審理についても,フランス法が適用され,供給品及びその決済に関して紛争が生じた場合には,フランス共和国サン・マロの商事裁判所を唯一の管轄裁判所とすることが規定されました。
本件契約は平成18年12月31日に期間の満了を迎えるところ,Aは,同契約の更新を拒絶し,Xからの商品の発注に対して契約が終了したと主張して,本件商品の出荷を拒否しました。一方で,Aは,化粧品の販売等を目的とする日本法人であるY₁と共同で本件商品等を日本国内で販売するY₂を設立し,Y₂が本件商品の日本国内での販売を開始しました。そこで,Xは,Y₁及びY₂に対し,Aとの共同不法行為に基づく損害賠償を求めました。
なお,Xは,Aも共同被告として訴訟を提起しましたが,本案前の問題があるため,Aについては口頭弁論が分離されました。
【争点】
1 XのYらに対する共同不法行為に基づく損害賠償請求についての準拠法
2 共同不法行為の成否
【判旨】請求棄却〔控訴〕
争点1(共同不法行為に基づく損害賠償請求についての準拠法)
法の適用に関する通則法17条本文(不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は,加害行為の結果が発生した地の法による)について,Xが主張するYらの共同不法行為による結果はいずれも日本国内において生じるものであるから,その準拠法は日本法となると判断しました。
また,同法20条が,「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は,不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと,当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして,明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは,当該他の地の法による。」と定めている点について,①Yらはいずれも日本国内に本店を有する株式会社であり,Xが主張するYらの共同不法行為による結果はいずれも日本国内に本店を有するXについて日本国内において生じるものであること,②Xは,Aとの間で,フランス法が適用される旨の条項のある契約等を締結しているが,Yらとの間では,そのような契約を締結していないこと,③Xが主張するYらの共同不法行為には,Yらが,共謀の上,Xを脅迫し,Xの信用を毀損し,業務を妨害したなどのXとAとの間の本件契約とは直接には関連しない行為も含まれていること等から,Xが主張するYらの共同不法行為について,明らかに日本よりもフランスが密接な関係があるということはできないとしました。
さらに, Yらは,XのYらに対する共同不法行為に基づく損害賠償請求は,XのAに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の発生が前提となっており,これがYらに対する損害賠償請求権の発生の要件の一部を構成しているから,XのAに対する損害賠償請求権の発生については,先決問題としてフランス法が準拠法となる旨主張しました。しかし,この点については,Yらに不法行為責任が認められるかどうかは,Yらの共同不法行為とXの損害との間に因果関係があると認められるかどうかが問題となるにすぎず,必ずしもXのAに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の発生が前提となるものではなく,AのXに対する不法行為に基づく損害賠償責任の成立が,Yらの共同不法行為成立の前提となる別個の法律関係を構成するとはいえないから,先決問題といえないとしました。
争点2(共同不法行為の成否)
Xは,XとAの間の長期間の継続的契約を終了させるには,Aは少なくとも2年間の猶予期間か2年分相当の営業補償金を提供すべき信義則上の義務があること等を主張しましたが,本件契約は契約期限までに契約の更新について合意しない限り更新されないことが合意されたと認められることから,Xが主張する信義則上の義務を認めることはできず,Aが提示した契約更新の前提条件を満たしていないとして,本件契約を終了させたことに正当な理由がないとまではいうことができないとして,AがXとの本件契約を終了させたことは,日本法に照らしても,Xに対する不法行為となるとはいえないと判断しました。
その上で,Yらについて,Y₁が,AがXとの契約を終了させる予定であることを知りながら,Aからの提案を受けて,Y₂を設立して,Y₁がAから本件商品を輸入し,Y₂がこれを購入し,日本国内の総販売元として販売することとしたことは, Xと競合商品を取り扱う会社の行為としては通常の自由競争の範囲内にある取引行為というべきであり,Aは,Xが持ち掛けたXの顧客のリストの買取りを断っていること等から,YらがAと共謀の上, Xの日本国内の販売先を奪取したとも認められないとして,共同不法行為の成立を否定しました。
【検討】
本件は,契約当事者間での継続的取引の解消が問題となっただけではなく,販売代理店の変更に際し,新たに販売代理店となった者等に対し,共同不法行為に基づく損害賠償が請求されたところに特徴があります。
また,本件では,自動更新条項が削除されていたことや更新について交渉されたものの前提条件について合意に至らず,更新について合意に至らなかったことから,Aが本件契約を終了させたことに正当な理由がないとまでいうことができないと判断しており,更新拒絶について正当な理由を積極的に認定していません。継続的契約の更新拒絶,解約等につきやむを得ない事由,正当な理由,信頼関係を破壊する事由等の制限を加える従来の多くの裁判例に対し,制限を緩和する近年の裁判例の傾向がみられることを指摘する文献もあり[1],本判決もそのような継続的取引の解消に関する近時の事例として実務上参考になるものと考えます。
なお,XとAの間の訴訟については,Aに対する管轄が日本にはないとして,訴えが却下されています(東京地裁平成20年4月11日判決・判タ1276号332頁)。Xは,Aとの関係でも債務不履行に加え共同不法行為に基づく損害賠償請求を主張していましたが,これについても,管轄合意の範囲内に含まれると判断されています。
[1] 升田純「契約自由の原則の下における継続的契約の実務」NBL993号46頁以下(2013)。
労働者派遣法改正による日雇派遣原則禁止
弁護士 西村真由美
1 法改正の経緯
平成18年頃から,偽装請負・違法派遣問題,違法な給与天引き,労災隠し,ワーキング・プアなどが問題とされ,特に日雇派遣労働者については,派遣元会社による雇用管理が不十分といわれました。そこへ,リーマンショックに端を発する派遣切りが社会問題化し,日雇派遣に対する規制強化の流れが更に強まりました。このような流れを受けて,平成24年3月28日,派遣労働者の保護を目指し労働者派遣法が改正され,同年10月1日より施行されています[1]。
2 日雇派遣の原則禁止
改正労働者派遣法では,原則として日雇派遣を禁止しています。ここでいう「日雇派遣」とは,日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣のことです。これは,あくまで「派遣元と派遣労働者との雇用契約」の期間が30日以内のものを禁止するのであり,派遣先と派遣元との契約期間を縛るものではありません。日雇派遣の一番の問題は,雇用管理責任が曖昧になる点であり,それは「派遣元と労働者との間の関係の希薄さ」に起因するところが大きいからです。
なお,「30日以内」とされた理由は,30日を超える期間を定めて雇用契約を締結した場合は雇用保険加入の対象となることから[2],適正な雇用管理が可能と考えられる点にあるようです。
3 日雇派遣禁止の例外
(1)もっとも,日雇派遣禁止には例外が認められています(改正労働者派遣法35条の3第1項)。
第一は,当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令[3]で定める業務について労働者派遣をする場合です。
第二は,雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合,その他政令で定める場合です。
(2)まず,第一の例外の趣旨は,以下のとおりです。日雇派遣労働者の中には今までどおりの働き方を希望する者も多く,原則禁止にした場合,失職するおそれがあります。また,雇用者責任を果たせない事業者に対しては個別のケースに応じた指導強化で対応することも可能です。そこで,日雇派遣が常態であり,かつ,労働者保護に問題の少ない業務では,政令により限定列挙する形で日雇派遣を認めたのです。
具体的には,改正前の労働者派遣法において派遣期間制限のない業務として列挙されていた“専門26業務”のうち,ソフトウェア開発業務や通訳業務,秘書業務等の“17.5業務”が,日雇派遣原則禁止の例外とされています(政令4条1項)[4][5]。
(3)次に,第二の例外は,政省令[6]に以下のように規定されています。
ア 日雇労働者が60歳以上である場合
イ 日雇労働者が学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む。)の学生又は生徒(定時制の課程に在学する者等を除く。)である場合
ウ 日雇労働者の収入(生業収入)の額が500万円以上である場合
エ 日雇労働者が生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であって,世帯収入の額が500万円以上である場合
上記アが例外とされたのは,禁止すると高齢者の雇用機会確保の点で不都合が生じるためであり,他方,上記イ,ウ,エが例外とされたのは,逆にそもそも雇用確保の要保護性が低いためだとされます。
4 企業にとっての注意点
(1)以上の改正に伴い,企業としては以下の点に注意する必要があります。
まず,改正前の専門26業務については,派遣契約上は形式的には専門26業務とされていながら,実態としてはそれ以外の業務に労働者派遣を行うケースが見られたことから,労働局が,専門26業務への該当性につき集中的に指導監督してきました。さらに,行政機関が,例外業務の該当性に関する解釈を変更することで,これまで17.5業務に該当するとされてきた業務についても,例外には該当しないと判断するおそれがあります。したがって,企業としては,専門業務の該当性についての行政機関の解釈に注意していく必要があります。人材会社の中には,例外規定は運用次第で大きく変わるリスクがあり,それに頼っていては事業の安定性を確保できないという意識のもと,日雇派遣は全て使えなくなるという前提で事業構築しているところもあるようです。
(2)次に,物流業界等,繁忙期のある業界が派遣先である場合,人手不足に拍車がかかることになります。
対応策としては業務請負とすることが考えられますが,偽装請負とならないよう注意が必要です。また,『日々紹介』といわれるシステム(利用者が労働者と直接雇用契約を締結する点に着目し,給与振込を除く労務手続きを代行するシステム)も,対応策の一つとして考えられます。しかし,日々紹介は事実上の日雇派遣とみられるリスクがあり,コンプライアンスリスクは増すといわざるを得ません。さらに,『雇用管理代行』という,求人や雇用管理を代行する仕組みも考えられますが,これも,利用者の直接雇用となりうるため,日々紹介と同様のリスクが生じます。
このように,繁忙期のある企業では,人員を派遣労働者に頼ることができなくなるため,計画的な人員募集が必要です。また,人材調達ができても,個々の仕組みに応じたコンプライアンスリスクに充分な注意を払う必要があります
(3)改正労働者派遣法は施行されたばかりであり,行政がどのような態度をとるかにつき,今後の運用を注視していく必要があります。
[1]本改正により,労働者派遣法の正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され,法律の目的にも,派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
[2]雇用保険法6条3項
[3]改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(以下「政令」とします)第4条
[4]厚労省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html
[5]日雇派遣禁止の例外業務が“17.5業務”と表現されているのは,改正前政令4条1項第16号で,「受付・案内」と並んで「駐車場管理等」が規定されていたところ,今回の改正で,案内・受付は日雇派遣禁止の例外とされ,駐車場管理は例外とされなかったことによるものです。
[6]政令4条,改正後の法施行規則(以下「省令」とします)第28条の2及び第28条の3
取締役による従業員の引抜きと不法行為
【はじめに】
移籍する取締役や競合会社による従業員の引抜きとそれによる技術流出がかねてより大きな問題となっており,移籍する取締役等による従業員の引抜きが不法行為を構成するかという問題も,実務上検討されることが多い法律問題の一つかと思われます。
そこで,今回は,株式会社の取締役が,在任中に,部下である従業員を勧誘し,競業会社へ移籍させた場合における,当該取締役及び競合会社の不法行為責任の有無が問題となった東京地裁平成22年7月7日判決・判タ1354号176頁をご紹介します。
【事案の概要】
原告であるXの事業は,映像事業部とテレコミュニケーション事業部(以下「本件事業部」といいます。)の二つの事業部を基礎としており,本件事業部の売上はXの総売上の約5割を占めていました。
Xは,業績不振のため平成19年度より財務状況が悪化し,主要株主等に増資の引受を中心とする支援を求めていたところ,競業会社である被告Yの代表取締役Aは,Xの大口顧客の執行役員から,Xの破綻回避への協力の打診を受けました。そこで,Aは,X取締役Zに対し,X支援策として,X従業員をZとともにYに移籍させ,YがXのソフトウェア等の保守管理業務を実施し,ソフトウェアの著作権者であるXに使用料を払う形の業務提携を提案し,従業員の人選や移籍のタイミングは,Zに一任しました。
その後,Zは,移籍勧誘の対象とした従業員の雇用条件をYに開示し,Yから同従業員宛の内定通知書の交付を受けるなどした上で,順次,移籍予定の従業員に対して移籍の勧誘を行いました。
その結果,平成19年12月から平成20年1月にかけて,本件事業部に従事する従業員の約3分の1である8名がYに移籍することとなりました。そして,Xが予定していた増資は,全ての引受先が辞退する意向を表明したため頓挫し,Xは本件事業部の維持を諦め,Bに本件事業部を譲渡することとしました。
Xは,Z及びYの行為が違法な従業員引抜行為にあたるとして,Z及びYに対し,不法行為等に基づき,従業員の移籍等により生じた損害の賠償を求めました。
【争点】
1 Z及びYの不法行為等に基づく損害賠償責任の有無
2 損害額
【判旨】一部認容・控訴
1 Zの不法行為について
本判決は,Zの不法行為の成否について,①本件事業部の存続には,自社開発したソフトウェアについての知識・技術を有する人的資源が不可欠であり,その中核を担うZらの移籍は,総売上の50%強を占める本件事業部の存続自体を困難にしかねないものであって,原告の事業全体に多大な影響を与えるものであったこと,②Xは増資等により資金調達を図る意向であったところ,Zは,取締役会における十分な議論を経ずに,従業員の移籍というXの意向とは矛盾する方策を採ったこと,③Zによる勧誘方法は,移籍対象となった従業員に虚偽を含む事実を告げ,Xの内規に違反してX従業員の雇用条件をYに開示し,これを踏まえて作成された内定通知書を移籍対象従業員らに交付するなど,不当なものであったこと等を指摘し,Zによる本件事業部の従業員に対する移籍の勧誘は,取締役としての善管注意義務(会社法330条,民法644条)や忠実義務(会社法355条)に違反し,社会的相当性を欠くものであって,不法行為を構成すると判断しました。
2 Yの不法行為について
本判決は,Yの不法行為の成否について,Yは,Zらの移籍がXに重大な影響を与えることは認識していたが,①Yは,Xの破綻を回避するための業務提携等の打診を受け,Zらに業務提携の提案を行ったのであり,Zの顧客を奪取する等の意図をもって協議を開始したのではないこと,②Yは,専らZを通じてのみ従業員の移籍等に関する協議を行っており,Xの増資の進捗状況等は知らなかったこと,③Yは,Zからの連絡により,移籍の勧誘がX内部である程度肯定的に受け取られていたと認識していたこと,④YはZによる雇用条件の開示がXの内規に違反していたとは知らなかったこと等を指摘し,Yによる移籍の勧誘は,社会的相当性を欠く違法なものであったと評価することはできず,不法行為を構成しないと判断しました。
3 損害額について
本判決は,従業員の移籍により履行不能となった業務のYへの委託費用や,受注が内定していた案件に関する逸失利益,弁護士費用をZの不法行為による損害として認め,Zに約5500万円の賠償を命じました。他方,事業譲渡に関する費用等については,Xが平成19年当初から資金繰りに窮しており,Zらの移籍という事態の有無にかかわらず,本件事業部を譲渡せざるを得なくなる可能性があったこと等を考慮し,Zの不法行為との相当因果関係を否定しました。
【検討】
多くの裁判例は,本件のような取締役による従業員の引抜き工作[1]について不法行為が成立するためには,当該行為が社会的に見て不相当であることが必要であるとしており,本判決と同様に,従業員の引抜きが会社に与える影響の大きさや,引抜き工作の態様を考慮して,不法行為の成否を判断しています[2]。
競合会社による従業員の引抜き工作について,不法行為責任が認められるかについても,同様に,当該行為が社会的に見て不相当であるかにかかっていますが,競合会社の行為に不法行為の成立を認めた裁判例は,引抜き工作を実行した取締役との間に密接な協力関係を認定している場合が多く[3],本件におけるYとZには,そこまでの密接な協力関係が認定されなかったものと思われます。
従業員の引抜きの問題は,職業選択・営業の自由とも関連し,適法違法の線引きが難しい問題ですが,本判決は,不法行為の成否及び損害の範囲について判断した一事例として,実務上参考になるものと考えます。
[1] 取締役による従業員の引抜きについては,取締役の忠実義務(会社法355条)との関係も問題になりますが,忠実義務違反によって当然に不法行為が成立するのかは必ずしも明らかではありません。
取締役の忠実義務違反の成否に関しては,在職中の取締役が従業員の引抜き工作を行えば,それだけで忠実義務違反になるとする見解(吉原和志「判批」ジュリスト920号37頁他)と,取締役による引抜き工作が何らかの不当性を備えた場合のみ忠実義務違反となるとの見解(江頭憲治郎「判批」ジュリスト1081号124頁他)が対立しています。
[2] 東京地判平成17年10月28日・判時1936号87頁,東京地裁平成18年12月12日・判時1981号53頁等。
[3] 前掲東京地裁平成18年12月12日,東京地判平成20年12月10日・判時2035号70頁等
民事再生手続におけるファイナンス・リース契約の取扱い
Ⅰ はじめに
中小企業金融円滑化法が施行された平成21年度以降,企業倒産件数は減少傾向にあり,今年は6年ぶりに企業倒産件数(負債総額1000万円以上)が1万3000件を割り込みました。
しかしながら,慢性的な円高や電力不足など,中小企業,とりわけ製造業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況です。中小企業金融円滑化法が期限切れを迎える平成25年度以降,再建型も含めた法的倒産処理手続を選択する企業数は増加するものと見込まれます。
ところで,再建型の倒産処理手続である民事再生手続においても,債権者であるリース会社から,債務の全額弁済やリース物件の即時引揚げなど,強硬な主張がなされることがあります。これらの要求を受け入れていると,ただでさえ経済的に窮境にある再生債務者[1]は,事業の継続のために必要な資金や設備を失い,事業再生が困難になります。また,再生債務者の事業再生を支援するスポンサーの立場からも,リース債権者への対応の巧拙は,拠出金の額に直結し,場合によっては支援自体の可否をも左右するものとなります。
したがって,民事再生手続を利用した事業再生を成功させるためには,リース債権者に対し,法律に従い適切に対応することが非常に重要になります。
そこで,今回は,問題点の多いファイナンス・リース契約の民事再生手続における取扱いについて,基本的な事項を整理したいと思います(以下では,民事再生法を「法」といいます。)。
Ⅱ リース債権の性質
リース物件のユーザーが民事再生手続開始決定を受けると,一部のリース債権者から,「リース債権は共益債権[2]だから,全額支払ってもらいたい。」との主張がなされることがあります。
こうした主張は,リース契約が賃貸借類似の契約であり,双方未履行双務契約[3]にあたるとの理解を前提に,開始決定時以降も再生債務者がリース物件を使用し続けていることをもって履行選択したと捉え,開始決定時以降に発生した反対債権が共益債権になると主張しているものと理解できます。実際,かつての東京地裁では,リース契約を双方未履行双務契約として扱い,リース債権を共益債権とする運用もなされていたようです。
しかし,ファイナンス・リース契約において,ユーザーは,契約により定められた範囲のリース物件の利用価値[4]を全て使い切ることが予定されており,中途解約は認められていないのですから,リース契約が締結された時点で,リース料債権は全額発生しており,月々のリース料の支払いとリース物件の使用は対価関係に立ちません。したがって,リース契約は双方未履行双務契約にはあたらず,リース料債権は再生債権[5]となります。この趣旨は,会社更生に関する判例[6]でまず示され,その後,平成20年には,民事再生に関する判例[7]でも,リース契約が双方未履行双務契約とならないことを前提とする判断が示されています。
このように,リース料債権が共益債権になるとのリース会社の主張には現在では理由がありませんので,再生債務者としては,リース料債権が全額につき再生債権に過ぎないことを説明し,必要な物件については,後述のとおり,別除権協定[8]の締結を目指すことになります。
Ⅲ 別除権協定
1 別除権者としての取扱い
前述のとおり,リース債権は再生手続開始決定により再生債権となりますが,リース債権者は,リース物件に担保権を有すると考えられるため[9],再生手続において,リース債権者は別除権者として処遇されます(法53条1項参照)。そして,別除権は,再生手続外で行使することができますので(同条2項),リース会社は,リース契約の解除とリース物件の引き上げを主張することがあります[10]。
2 別除権者に対する対抗措置
リース債権者が別除権協定締結に向けた交渉に応じず,問答無用的にリース物件の引き上げを主張する場合,再生債務者にはどのような手段が用意されているのでしょうか。
まず,再生手続開始申立後[11],担保権実行中止命令[12]の申立てをすることが考えられます(法31条1項)。これにより,別除権協定の締結に向けた交渉に必要な一定期間,担保権の実行を凍結させることができます。
また,交渉の結果,別除権協定の締結が不可能となった場合には,リース物件の処分価額[13]相当額の金銭を一括納付して,リース物件に存する担保権を消滅させることの許可を裁判所に対して求めることができます[14](法148条)。
なお,ユーザーに民事再生手続開始申立等の事由が生じたことを理由として,リース契約を解除するとのファイナンス・リース契約における条項(倒産解除特約)は,再生債務者に,別除権協定締結の必要性に関する検討やリース債権者との交渉,担保権実行中止命令・担保権消滅請求等の検討をする時間を与えず,問答無用的にリース契約を解除する点で,民事再生法の強行法的規律に反し,無効であると解されます[15]。
3 別除権協定に向けた交渉
再生債務者は,2で述べたような法制度の存在を前提に,場合によってはその一部を利用しつつ,別除権者と別除権協定締結に向けた交渉に臨むことになります。
ところで,リース債権者からは,交渉の過程で,残リース料ベースでのリース契約の巻き直しや再リース契約締結の提案がされることがあります。
しかし,このような処理を採用すると,契約締結当初に必要とされる資金は少額で済むものの,実質的に再生債権の全部又は一部が共益債権[16]に格上げされることになり,最終的には再生債務者の事業再生の重荷になります。したがって,リース契約の巻き直しによるリース債権の処理は,再生債務者にとって望ましいものではありません。
そもそも,リース債権者が把握している担保価値は,リース物件の処分価額を上限とするものです。そのため,再生債務者としては,リース債権者との交渉に先立ち,リース物件の処分価額を査定した上で,そこから物件の運び出し等に必要とされる費用を控除した価額をベースに,別除権協定の締結を目指すことになります。
さらに,スポンサーによる支援を前提とする民事再生の場合には,別除権協定によるリース債権者への弁済方法については,再生計画認可後の一括弁済によるべきです[17]。したがって,スポンサー支援を検討する企業は,別除権者への支払を考慮した上で,拠出可能な金額を決定する必要があります。
[1]民事再生手続開始の申立をした債務者を再生債務者と言います。
[2] 共益債権は,民事再生手続によらず随時弁済できます(法121条1項)。
[3] 再生手続開始決定時に,双方の債務の履行が完了していない双務契約については,再生債務者に履行か解除かの選択権が認められ(法49条1項),再生債務者が履行を選択した場合には,相手方の債権が共益債権となります(同条4項)。
[4] この点,フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約においては,ユーザーがリース物件の利用価値を全て使い切ることが予定されており,ノンフルペイアウト方式のファイナンス・リース契約においては,リース期間終了後のリース物件に残存価値があることが予定されていますが,契約上予定された利用価値をユーザーが使い切るという点で,両者に差異はないと理解すべきです。
[5] 再生債権は,原則として再生手続外で弁済することができず,再生計画に従って権利変更された額が弁済されることになります(法85条1項)。
[6] 最判平成7年4月14日(民集49巻4号1063頁)。
[7] 最判平成20年12月16日(民集62巻10号2561頁)。
[8] 再生債務者が別除権者に対して一定額を支払い,別除権者が担保権の全部又は一部を放棄することを内容とする,再生債務者と別除権者との合意を別除権協定と言います。
[9] リース債権者が何に対して担保権を有するのかが,別除権の行使方法と関連して問題になります。
まず,担保権の対象をリース物件の所有権と見ることが考えられます。その場合,リース物件の引き揚げ行為そのものが担保権の実行として捉えられることになります。
しかし,ファイナンス・リース契約において,リース物件の所有権が終始リース会社に留保されており,リース契約の終了後もユーザーに移転することが予定されていないことを考慮すると,リース物件の所有権に対してリース会社の担保権が設定されていると考えることには無理があると考えられます。
そのため,ファイナンス・リース契約においては,リース物件の利用権に対して担保権が設定されていると理解されます(大阪地決平成13年7月19日(金法1636号58頁),山本和彦「倒産手続におけるリース契約の処遇」金法1680号13頁)。
このように解しても,リース会社がユーザーからリース物件を取り戻して交換価値を実現し弁済を受けるところまでをリースにかかる担保権の実行手続と評価することは可能であると解され(才口千晴他「新注釈民事再生法」154頁),再生債務者が担保権実行中止命令等の手続を採ることはなお可能であると考えられます。
[10] 特に,リース物件が自動車である場合などのように,リース物件の引き揚げが容易でリース物件としての資産としての劣化が早い場合には,リース会社は強硬に物件の引き揚げを主張します。
[11] 再生手続開始決定後も含みます(前掲才口千晴他145頁)。
[12] なお,担保権実行中止命令は,担保権の実行としての競売に関する規定ですが,ファイナンス・リース契約にも類推適用されると解されます(前掲山本)。
[13] ファイナンス・リース契約においては,リース物件の利用権に担保権が設定されていると考えられるため,「処分価額」(民事再生規則79条1項)とはどのような価額を指すのかが問題になりますが,リース債権者は最終的にリース物件を復帰させることにより担保権の実行を行うので,リース期間満了時のリース物件の残存価値の有無にかかわらず,「処分価額」もリース物件自体を競売により売却した場合の価額と等しくなるものと考えられます。
[14] ファイナンス・リースが担保権消滅請求の対象となることにつき,前掲大阪地判平成13年7月19日,東京地判平成15年12月22日(金法1705号50頁)等参照。
[15] 前掲最判平成20年12月16日,岡正晶「判批」金法1876号44頁。
[16] 再生手続開始決定後にリース契約を巻き直すと,それにより発生するリース料債権は,共益債権となります(法119条2号)。
[17] スポンサー型の民事再生の場合,リース債権者は一括による弁済を期待しており,また,一括弁済であればリース債権者としても低価格での別除権協定締結に応じやすくなります。
「餅」の特許権に基づく侵害差止等請求事件
【はじめに】
今回は,側面に切り込みを入れた「切り餅」の特許を侵害されたとして,「越後製菓」が「佐藤食品工業」を訴えた裁判につき,佐藤食品による特許権の侵害を認めた控訴審の中間判決(知財高判平成23年9月7日・判時2144号121頁)をご紹介します。
【事案の概要】
原告は,切り餅の側面に水平方向の切り込みを入れることで,焼いて膨らんだ際に表面が破れることを防止する,という特許を2002年10月に出願し,2008年4月に登録されていました。一方で,被告は,側面だけでなく上下にも切り込みが入った切餅で,原告に後れて特許出願し,登録を果たしていました。原告は,この製品が自社の特許を侵害しているとして,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品およびその製造装置の廃棄と,約14億8000万円の損害賠償を求めて提訴しました。
【裁判の経緯】
原審(東京地判平成22年11月30日)は,被告製品は,本件発明の構成要件を充足せず,本件発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,請求をいずれも棄却しました。これに対して,控訴審は,本件発明の技術的範囲に属するとして,特許権侵害を認める中間判決を下しました[1]。
【検討】
1 技術的範囲の認定手法
本裁判では,原審と控訴審とで正反対の結論が下されました。もっとも,特許発明の技術的範囲の解釈方法については,原審も控訴審も基本的に同様の立場に立っています。
すなわち,本件の争点は,問題となる被告製品が,原告の特許発明の技術的範囲に属するか否かであるところ[2],特許発明の技術的範囲は,特許出願時の願書に添付する明細書と,特許請求の範囲の記載及び図面を考慮して解釈されます(特許法70条1項,2項)。特許請求の範囲は,「クレーム」と呼ばれ,請求項に区分し,請求ごとに,発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載せねばなりません(特許法36条5項)。このように,文言による解釈が原則となりますが,多義的な解釈が可能な場合には,出願経過等も参考にする場合があります[3]。そして,特許は特許請求の範囲に記載された構成要件によって全体として規定されるところ,特許権侵害が成立するためには,原則として対象製品または方法が構成要件のすべてを満たす必要があります。
2 本事案における判断
本判決で問題になったのは,原告の特許請求の範囲に記載された請求項の「…切餅の載置底面又は平坦上面ではなく…側周表面に,…切り込み部又は溝部を設け」という部分です[4]。
上記請求項につき,載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外する意味を有すると理解した原審に対し,控訴審は,「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は,「側周表面」を特定するための記載であり,被告製品は本件発明の技術的範囲に属するものと判断しました。
3 解釈のポイント
原審と控訴審で解釈が分かれたポイントは,特許請求の範囲の記載中の句読点の位置でした。
本中間判決では,問題となった請求項を上記のように解釈した根拠として,次のように述べています。「『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分の直後に,『この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に』との記載部分が,読点が付されることなく続いているのであって,そのような構文に照らすならば,『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は,その直後の『この小片餅体の上側表面部の立直側面である』との記載部分とともに,「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。」。つまり,『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は越後製菓の技術的特徴ではなく,単なる修飾にすぎず,「側面に切り込みを設けること」だけに技術的特徴がある,という解釈です。
4 均等論
本件では,原告は原審で均等論を主張せず,控訴審において初めて追加し主張したのですが,控訴審は,文言解釈により侵害ありと判断したため,均等論についての判断はなされませんでした。
均等論とは,対象製品に文言侵害がないとされた場合でも,一定の要件[5]を充足すれば,対象製品は特許発明の構成と実質的同一と評価されるとして特許権を及ばせる理論です。特許権の禁止権の及ぶ範囲を拡張する理論として,古くから米国で認められてきた考え方でしたが,日本では最近になって最高裁[6]により認められました。従来,日本では,文言侵害を厳格に妥当させることが要求されていました。クレームには公示機能(特許法70条)があり,クレームを信頼して実施した第三者にとって,予見可能性・法的安定性が高いというメリットがあるからです。しかし,日本の先進化に伴い,パイオニア発明の保護が求められるようになると,保護範囲を文言の範囲内のみとする従来の考えは衡平の原則に反する場合を含むといわれるようになり,こうした意識を背景に均等論が登場しました。
本事例では,仮に文言侵害が否定されたとして,均等論が必ずしも意味を持つかは定かではありませんが,特許権侵害を考えるうえで重要な理論のひとつとなっています。
【終わりに】
均等論は,第三者の予見可能性を退けてまで,特許出願人のクレーム記載不備を救済するかどうかという問題です。均等論による特許発明の保護は依然慎重にならざるをえず,均等侵害が肯定された裁判例[7]は,それほど多くありません[8]。やはり,権利解釈上,クレーム文言が最も重要であることは言うまでもないのです。クレームの記載にあたっては,解釈に幅をもたせず,かつ無用な限定とならないように,簡潔で明快な記載が求められることを,本判決から学ぶことができるのではないでしょうか。
[1] 特許侵害訴訟では,被告製品の製造販売が,原告の特許権侵害に該当するかを審理する「侵害論」と,その侵害行為により生じた損害の額を審理する「損害論」との二段構えで進められるのが一般的で,本中間判決は,前者(侵害の成否)についての判断が示されたものです。中間判決後,越後製菓は59億4千万円に請求額を引き上げ,平成24年 3月22日,知財高裁は,約8億円の損害賠償および差止めを認める控訴審判決を下しています。
[2] 特許権は,発明という無体物を対象としているため,その権利の及ぶ範囲が明確でなく,しばしばその範囲が争われます。
[3] さらに,後述のように,一定の場合には文言を拡張した解釈がなされることがあります。
[4] これは,切餅のどの部分に切り込みを入れるかという問題であり,原告の発明内容は,餅の中身の噴出を防ぐために,製造時に側周に一周するような切り込みを入れるというものでした。これに対し,被告の発明内容は,切餅の側面に加え,上下面に十字形の切り込みを入れるというものであり,このような製品が,上記請求項の特許発明の技術的範囲に属するか否かの解釈において,判断が分かれたのです。
[5] 均等侵害成立の要件として,後述の最高裁判決では,「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,
(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく,
(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,
(3)右のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,
(4)対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,
(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,右対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」と判示しました。
[6] 最三判平成10年2月24日・民集第52巻1号113頁(ボールスプライン軸受事件)。
[7] 均等侵害を肯定した裁判例としては,東京高判平成12年10月26日・例時1738号97頁(生海苔の異物除去機特許侵害事件),大阪高判平成13年4月19日・判工〔2期〕2311の500頁(ペン型注射器事件)等があります。
[8] ボールスプライン最判解説は,第二要件が概括的判断によるものであり,均等が成立する範囲が広範となることに鑑み,まずは第二要件を検討し,次に,いわば『絞り』として第一要件を検討すべきとしました。近年の裁判例では,第二要件を充足しないと判断した上で,更に第一要件をも充足しないとして,均等侵害不成立を明確にしたものがあります(知財高判平成22年 3月30日・携帯型コミュニケータ事件)。
民事裁判の迅速化
弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村博子
民事裁判では、『提出する書面の量で弁護士費用を取っている事務所があることが、民事裁判で、大量の書面が提出され、民事裁判の迅速化を妨げる一因※ 1』、とする高名な学者の発言がなされました。私自身は、そのような弁護士費用の請求方法を取っていないので、そのような事務所があるのか、仄聞にして知りませんが、なかなかショッキングな発言です。この発言は、最高裁が昨年7 月に提出した「民事裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(4)」を受けて、どうすれば、迅速かつ公平公正な民事裁判が行いえるかの提言のための裁判官、学者、弁護士らの座談会で出たものです。
私は、大阪弁護士会の民事裁判の改善に関する協議会という会に属し、訴訟実務の改善等を勉強しています。先日私が発表担当で、「主張、立証方法のあらたな工夫というテーマ」で討論するベースを作成しました。
工夫例として、① PC 用の発達した文書作成アプリを用いて、様々なマーカー機能、色別文字を用い、また注記等の多用、PDF アプリを用いて証拠を主張書面に貼り付けてしまう、などの様々な工夫がなされていることなども報告の対象といたしました。2006 年にTBS 系列で放送された『情熱大陸』の青色発光ダイオード職務発明事件で、中村教授が会社からその発明の対価として受け取るべきは200億円との第一審判決を得た、荒井裕樹弁護士の準備書面などは、当時から話題になったものです。
また、②刑事裁判の裁判員裁判において用いられるようになったパワーポイントを使ってのいわばプレゼンテーションのようなことも、専門化、複雑化する訴訟では、民事裁判でも用いられているようです。
私のようなオーソドックスな弁護士には、これらの工夫例は、裁判官に、こちらの主張をしっかり判ってもらうという大事なポイントをついたすばらしいもので、今後参考にさせてもらおうと考えたのですが、少し翻って考えてみるとこれらの工夫例は、すべて冒頭の、主張書面が長すぎるということを前提に、その長い文章をどうやって裁判所に集中力を持って読み通してもらうか、またその中に記載した主張を理解してもらうかを考えてのもののようです。
私が弁護士になった25 年前は、やっとワープロ専用機が導入された頃、B5 版縦書きの書面は、その大きさでも10 頁も書けばかなり長文の部類でした。それがなぜ、冒頭の座談会でも問題にされ、また長い書面前提で、読みやすさのための工夫がさ
れるようになったのでしょうか。
一つには、専門化、複雑化した訴訟が、一定数増えてきていることにあるでしょう。これまでは、訴訟という形での解決より、他の紛争解決手段(話し合い)で解決できた紛争が、裁判によって、司法による公平公正な判断を受けたいという社会のニーズが高まったため、類型化できない訴訟が増えてきているように思います。知財訴訟が一つの典型ですし、会社と株主間の争い、複雑な金融商品の証券被害訴訟などがこのような訴訟の中に入ると思いますが、それ以外にも、通常の取引を続けてきた会社間での訴訟、売買された製品の瑕疵を巡る紛争なども確かに増えてきています。
最後のような例では、問題となっているのがどんな製品か、どのような製造工程をたどって製品が完成するかなど、裁判官にはバックグラウンドの知識のない内容も伝えないと解決しない事件も出てきています。技術内容を書面で記載すると勢い長くなってしまいますので、それをなるべく短くしようとすると、表や、図などを書面に取り込む工夫は必要です。
もうひとつは、PCソフト等の進化でしょう。先に提出した書面のコピーアンドペーストが簡単にできてしまうのです。先の書面に記載しているけれど、裁判官に読んでもらっていないのではないかとの不安から、我々弁護士は、新しい書面にコピーアンドペーストしてしまうということをしがちです。また、相手方が50 頁、100 頁、200 頁という書面を提出すると、何となく分量で負けそうというような気持ちになって、当方も長い書面を作成してしまうという半ば心理戦のようなものもあります。
こちらについては、証人尋問の前に、確実に双方の主張を整理する機会(争点整理手続といいます)を充実させて、双方の主張をしっかり確認する作業が重要で、それが確実に行える、または行うということが所与の前提となれば、その際に主張の骨子を伝え、詳しくは何番目の準備書面(双方の主張や、証拠の評価を書いた裁判所に提出する書面のことです)のどこに書いてあるときちんと示せれば、裁判所、相手方の争点に対する理解がわかるようになります。この争点整理手続は、多くは弁論準備手続という丸いテーブルを、裁判所、双方当事者代理人が取り囲んでの場所で行われ、そこでは口頭で議論することも可能で、当事者はもちろん、関係者も裁判所の許可があれば傍聴可能です。
裁判を依頼される皆さんも、頁数だけで、弁護士を判断しないでくださいね。それより、中身のぎゅっと詰まった読みやすい書面で、裁判所、相手方を説得し、時々に真意が伝わっているか確認し、証人尋問の前には必ず、争点の確認をするようにしますので、ぜひ傍聴してください!
18年にわたって継続した販売代理店契約の解消が問題となった事例
弁護士 中島康平
【はじめに】
今回は、18 年にわたって継続した販売代理店契約の解消が問題となった東京地裁平成22 年7 月30 日判決・判時2118号45 頁をご紹介します。
【事案の概要】
X は、 Y との間で外国製ワインを日本における独占的に輸入・販売することを内容とする販売代理店契約(以下「本件販売代理店契約」といいます)を締結し、ワインを輸入・販売していましたが、Y は、平成17 年1 月5 日ころ、X に対し同年4月末日限り本件販売代理店契約を解約する旨通知しました(以下「本件解約」といいます)。
X は、本件解約が本件販売代理店契約上の1 年間の予告期間を設ける義務に違反するとともに、X の日本における独占的な輸入販売権を侵害するものであると主張して、 Y に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として8 ヵ月分の粗利益に相当する8280 万円の支払いを求めました。
なお、X は平成11 年12 月に設立され、完全親会社であるA からワイン部門の営業譲渡を受けています。A とオーストラリアのワイン会社であるB は、昭和62 年、B のワインを日本に輸入・販売することを合意し、以後、A はB にB ブランドのワイン(以下「B ワイン」といいます)を発注してこれを日本に輸入し販売してきました。Y は平成13 年にB を買収し合併したオーストラリアのワイン会社です。
【争点】
1 本件販売代理店契約の成否
2 債務不履行、不法行為の成否
3 X の損害
【判旨】一部認容、一部棄却〔確定〕
争点1
本判決は、本件販売代理店契約の成否について、本件販売代理店契約に係る契約書は存しないからB ワインについて継続的な取引関係が存在しただけであって本件販売代理店契約が存在したとはいえないとのY の主張を排斥し、① A は、昭和62 年にB との間でB ワインを日本に輸入して販売する合意をしたこと、② A及びその後にその営業譲渡を受けたXは、通算18 年にわたってB ワインを注文して日本に輸入し販売してきたこと、③この間、B やこれを合併したY は、A又はX との間で日本における販売戦略等について協議してきており、X に対し販売代理権がないことを理由にB ワインの出荷を拒否したことがなく、他の販売代理店を通じて日本においてB ワインを販売したこともないこと、④ Y 作成の文書中にX が販売代理店であることを前提とする記載があることを総合すると、A とB は、昭和62 年、A においてB ワインを日本に独占的に輸入・販売することを内容とする本件販売代理店契約を締結したものと推認されるとしました。
争点2
その上で、本件販売代理店契約の解約に関し、X とY は本件販売代理店契約に基づき18 年という長期にわたり取引関係を継続してきており、その間にX は日本におけるB ワインの売上げを大幅に伸ばしてきたこと等に照らせば、X において将
来にわたって、Y のB ワインが継続的に供給されると信頼することは保護に値するものであるから、Y が本件販売代理店契約を解約するには、1 年の予告期間を設けるか、その期間に相当する損失を補償すべき義務を負うものと解されるとし、予告
期間を4 ヵ月とするY の本件解約はかかる義務に違反するものであって、債務不履行にあたると判断しました。
なお、Y が本件解約に先立ちX に対し販売業績への懸念を表明し、販売代理店を変更する可能性を警告していたことに関しては、本件販売代理店契約の終了を予告したとはいえないし、本件解約で設けた4 ヵ月の予告期間を正当化することもできないと評価しています。
争点3
Y の債務不履行によるX の損害に関しては、予告期間として相当な1 年から本件解約の予告期間4 ヵ月を差し引いた8 ヵ月について、B ワインの売上げがなくなり、売上げにより得べかりし総利益を喪失しているが、その反面、B ワインの売上げに要する販売直接費と共に販売管理費(労務費、経費、広告宣伝費、償却費からなるもの)を免れることができると考えられるから、Xの被った損害とは、総利益から販売直接費及び販売管理費を控除した営業利益の喪失分と解するのが相当であるとし、粗利益相当額を主張するX の主張を退けて、8 ヵ月分の営業利益に相当する590 万4000円を損害として認定しました。
【検討】
継続的取引の解消は実務上検討されることが多い法律問題の一つだと思われます。継続的取引に係る契約書が作成されていることが多いとは思われますが、相当期間にわたる取引の場合、取引開始当初において契約書等が作成されず、また作成されていても非常に簡潔な内容にとどまる事例も見受けられます。本件も契約書が存在しない期間の定めのない継続的契約の解消が問題となった事例です。
長期間にわたり取引関係が継続してきた場合には契約当事者に今後も取引が継続されるとの期待が生じることがあり、取引継続への合理的期待をどのように保護するかが問題となります。判例に関しては、継続的に続いた特約店および販売店契約
については解約あるいは更新拒絶は公序良俗違反あるいは権利の濫用にならない限り契約自由の原則によるとするもの、合理的理由あるいはやむを得ない事由が必要であるとする判例もあり、これを不要とする判例もあり、必要とするものも、結局、
供給者の主張どおりに解約を認めたもの、合理的予告期間が必要であるとするもの等があり、判例の方向は固まったとはいえないとされています※ 1。
本判決は、このような状況の中で継続的取引の解消に関する近時の事例として実務上参考になるものと考えます。
学校法人の再建的な法的手続の検討
弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村博子
第1 はじめに
18才人口の減少が言われてひさしく,私立学校は,生徒,学生の確保に様々な工夫が必要とされています。また一方で,経営の監視については,会社にとっての株主のような存在がなく,放漫経営に陥りやすいのも,私立学校の経営の難しいところです。
学生が集められなかったり,リスクの高い投資や,財産の私的流用により,学校経営が危うくなった場合,民事再生手続などによって,債務の免除を受けることも,学校の閉鎖という事態を防ぐためには,必要な場合があります。
第2 学校の再建手続きの特徴
今回は,学校の民事再生手続きにおける,通常の会社の場合との違いを見ていくことにしましょう。
ア 学校経営の維持
民事再生手続によれば、学校経営を維持し、学生の就学の機会を奪うことなく、また、教職員についても基本的に、手続申立後も就労の継続がなされます。学校が存続することにより,随時学校が行っている、卒業証書や成績証明書の発行といった卒業生への対応も可能となります[1]。
イ 資金繰りの確保の重要性
学校に限らず,再建的な手続において、最も重要ともいえるのが資金繰りの確保ですが,学校法人の場合は、一般の企業の場合よりもさらに、この問題が深刻です。企業の場合,長くても1、2ヶ月の内に倒産前後の売上が、入金し、キャッシュとなって、その後の経営の費用に宛てることが可能ですが,
学校法人においては、収入の中心が,1年ごと,半年ごとに支払われる,学生からの学費であるため,手元に資金がないという中での申立となってしまうことも多いと思われます。
このような学校法人には,必ずといって良いほど,当初からスポンサーの支援によって,資金繰りがつくことが重要です。
ウ 学生の債権の取扱
民事再生手続においては,手続申立前に成立した債権,すなわち金融機関の貸金債権などは,再生債権と呼ばれ,一定額の免除の対象となります。学生の授業料についても,先に前払いして,学校から授業を受けるという性質上,再生債権となるとの考え方もあります。塾などの破綻の場合,前払いした授業料の返還を求めても,全額は戻ってこないというのが通例です。
しかし,それでは,学生の保護に欠けるというような考え方から,学生のこのような債権を共益債権と考え,学生は,他に優先して授業料の返還請求権があるという考え方もあります。
学生と学校の間の契約(在学契約)を,例えば、大学であれば通常4年間で卒業までの授業を提供することになっているということから考えて、学校側にはその間授業を提供する義務があり、また学生にはその間、継続して授業料を支払う義務がある契約であると考えるのです。そのように考えると、民事再生手続の開始という、倒産の時点において、大学側にも学生側にも双方に未履行部分があることになります。かように解した上で、破綻した学校がこれらの在学契約において、履行を選択すると、学生の反対債権、授業を受ける権利は、共益債権となると考えるのです。しかし,全てを共益債権とすると,スポンサーは,半年か一年分の経費を負担せざるを得ず,相当重いものになってしまいます。私は,学生にも一部を負担してもらうというような柔軟な考え方もできる,再生債権説も一理あるのではないかと考えています。
エ 校地、校舎、その他の資産と担保権者の関係
民事再生申立を必要とするような学校においては、校地校舎や、学校の機材や機器などにも抵当権や譲渡担保権などの担保が設定されていることが多いでしょう。
民事再生手続きでは,担保権者は,手続きの枠外にあり,債務者との交渉(別除権交渉)で合意しなければ,担保権実行を行うことが可能です[2]。
学校にとって,校地校舎は,その存続に是非とも必要なもので,文科省の定める設置基準を満たしている必要があるとされています。よって,担保権者との交渉は,是非とも妥結したいところですが,例えば,大都会の一等地にキャンパスがあるような場合,担保権者は,マンション用地としての価値を担保額と考え,学校側は,学校経営により生み出せる,低い収益でしか評価できないとすると,その溝を埋めるのは簡単ではありません。
スポンサーに一旦買い取ってもらって,そのリースバックを受けるなどの方法が,設置基準との関係で問題とされる可能性もありますが,文科省にも事情説明するなどして,理解を求めることも必要となるでしょう[3]。
どうしても担保権者と別除権協定を結べず,担保権者が強制執行の申立をするような場合には,担保権消滅制度(民事再生法148条)を利用して,その物件の価格を裁判所に納めることで担保権を消滅させることで対抗するしかありません。この校舎を失えば,設置基準を満たさなくなるなどの事情があれば,事業継続に欠くことができないとの点は認めてもらいやすくなります。その際に,裁判所に,物件の価値を,学校の経営で生み出される利益から算定してもらえるかどうかは,スポンサーに資金提供してもらう場合も大事な要素ですが,実際の例はまだないようです。
オ 税務上の問題-債務免除益
次に、再生計画により,債務免除を受ける場合に,通常の会社の場合に最大の問題となるのが,免除益課税の問題です。学校は,学校経営の他に収益事業も営むことが可能で,その場合には,同様の問題が生じますが,収益事業以外には課税されないため、学校経営に関しての負債であれば、債務免除益の問題は考慮しなくてよいことになります。学校の負債が,どのような趣旨で発生したかにも注意が必要です。
第3 スポンサーの協力
学校経営は,スポンサーになり,経営手法を変えたからといって直ちに利益を生むものではありません。もちろん,経費の合理化や,魅力的な宣伝,新規の授業やカリキュラムの導入によって,収益構造は変えられますが,もともと利益を生むことを目的としていいからです。となれば,篤志家的な発想を持つ人,団体でなければ,スポンサーにはなってくれません。学校存続の重要性をアピールすることも大事ですが,学生,教職員の協力を始め,管轄庁の理解や,民事再生手続き上での工夫も含めた,支援体制が必要と考えられます。
[1] 京都地判平成7年9月22日(判タ902号111頁)は、学校は卒業生に卒業証明書を交付すべき義務を認めて、発行されるまでの慰謝料を認めている。同誌には、このような卒業証明書の交付請求権は、在学契約に由来するとの解説がなされている。
[2]学校法人の寄附行為及び寄附行為の認可に関する審査基準(私立学校法31条、私立学校法施行規則2条による)、これは認可基準と呼ばれており、同基準は、校地・校舎が設置基準を満たしていることを要するとしている。
[3]認可基準第1、1、(2)では、校地校舎は自己所有であることを原則としている。