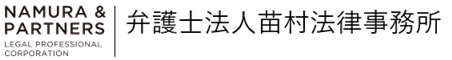アーカイブ
攻める知財―各国の水際対策(1)
弁護士 苗村博子
1.訴えられたら防戦する、かような守りの知財保護だけではなく、近時、皆様の重要な無形財産である知財を用いて、攻めることを始めた日本企業も出てきました。今回は、その方法の中でも比較的安価で、短時間ですむ、水際対策について、ご紹介します。
2.まずは、日本の概略ですが、水際対策は、税関が本来自ら行う手続きで、知的財産の「侵害疑義物品」を調査し、「侵害品」と「認定」するとその物品の日本への輸入を差止めます。侵害品の輸入による消費者の混乱等の防止という公益目的で行います。が、侵害品か否かを最もよく知るのは、その権利者なので、権利者に「認定手続」の申立権を認めています。申立権者は、特許他の知的財産権と不正競争防止法上の周知表示、著名表示
の保有者です。
3.①権利の存在、②侵害の事実の疎明、および③識別可能性が要件です。③については、識別ポイントを示した資料が申立の際の添付資料とします。製品の表示、外観、形状、製品の特徴の分かりやすい記述、写真や比較図面による説明等の工夫を要します。主に商標、著作権などでよく活用されますが、特許権でもこの制度が用いられます。1~2 ヶ月で認定の受理の可否が決まります。
4.米国では、国際貿易委員会が、特許、商標、著作権の他営業秘密やトレードドレスの保有者の申立に従って行います。特許権者が多く利用しますが、デザインパテント(意匠権)も入ります。海外で製造された模倣品が、直接米国に輸入されているような場合に効果的です。決定までには15~18 ヶ月を要します。公益目的と言う点は同じで、国内産業要件という、米国内の産業を破壊または実質的に害する等のような物品の輸入差止めが認められます。外国企業でも、米国で、その知財を用いて活動し(技術的要件)、(A) 工場等への相当な投資、(B) 相当な労働者の雇用や資本投下、(C)研究開発、ライセンス等の知
的財産権の利用のための実質的な投資(経済的要件)をしていれば申立可能です。行政判事が審理を行うため、その結果の予測可能性は、陪審に比してずっと高く、侵害には排除命令(輸入排除)か、停止命令が発令されます。不服申立は、CAFC(知財高裁)に行います。この手続でも和解制度があり、半数ほどは和解で終了します。
会社法改正
弁護士・ニューヨーク州弁護士 佐藤有紀
企業統治(コーポレートガバナンス)の強化を柱とする会社法改正に関する法案が平成25年11月29日に閣議決定され、同日、第185回国会に提出されました。これは法務省の法制審議会会社法部会第一回会議が平成22年4月に開始されてから、同部会による平成24年8月1日付「会社法制の見直しに関する要綱案」の決定を経て、今回法案化されたものです。
今回の会社法改正には実務に影響を与える点がいくつかありますが、そのハイライトのひとつが社外取締役の義務化(するかどうか)という点でした。今回は、この点について概説したいと思います。
1.社外取締役設置義務化見送りと説明義務
結局、改正案によれば、監査役設置会社である上場会社等(正確には、金融商品取引法<以下「金商法」といいます>第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社)において社外取締役を置いていない場合、「取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない」という条項が加わることになりました(会社法第327条の2の新設)。
会社法は、上場会社と非上場会社とを問わず、すべての株式会社に適用される法律ですが、この社外取締役未設置に関する説明義務は上場会社等のみに課される義務ということになります。そこで(上場会社と非上場会社とを区別する)金商法を引用し、会社法に金商法上の概念を持ち込む形で法改正することになりました。
上場会社が社外取締役を置くことが相当でない理由を説明する際には、事業報告書という書面ではなく、定時株主総会において直接株主に説明しなければなりません。これまでの実務に鑑みると、事業報告書という書面のみでの説明となれば、テンプレートのような表現を用いてどの上場会社も同じような説明を行うことになっていただろうと思いますが、取締役が定時株主総会で理由を説明しなければならないとなると、そのような形式的な対応では難しいのではないかと思います。その意味では、社外取締役を設置しない積極的な理由を各社で考えなくてはならないこととなり、社外取締役制度に対する各社の理解が深まるのではないかと期待されます。
また、私の実務経験からすると、毎年株主総会はあるものの、株主の前で報告・説明を行うのが取締役の本業ではないため、説明を担当される取締役も出来る限り株主からの厳しい質問は少なくしたいのではないかと思います。この観点からすると、定時株主総会において社外取締役不設置の理由を説明しなければならなくなる(そしてその質問に対応しなければならなくなる)のであれば、いっそのこと社外取締役を設置した方が無難ではないかと考える上場会社が出てくるのではないかという予想もされます。結果として、社外取締役設置義務規定は見送られたものの、実質的には社外取締役の設置を半ば強制するようなプレッシャーを与える規定が会社法改正案に導入され、社外取締役設置義務と同様の働きをすることを立法者は期待しているのではないかとも推測されます。
2. 社外取締役の定義の変更
技術的な話になりますが、改正案ではそもそも社外取締役の定義が改正されることになります(会社法第2条第15号)。これまでは当該株式会社またはその子会社等の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人である(あった)かどうかで判断されていました。今後は社外取締役の要件に、①株式会社の親会社等またはその取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の使用人でないこと、②株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと、③株式会社の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の重要な使用人または親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者または2親等内の親族でないことが追加されます。
この改正により影響が出るのは、上場会社の社外取締役に、親会社等の取締役が就いている場合です。当該上場会社が、いわゆるオーナー企業であったり上場子会社であったりする場合には、現在の社外取締役が会社法改正後も「社外取締役」に該当するのかチェックが必要になります。
また、社外取締役の要件に係る対象期間についての規律が以下の通り改められることになりました。すなわち、
(1) その就任の前10年間株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人であったことがないこと
(2) その就任の前10年内のいずれかの時において、株式会社またはその子会社の取締役(業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人であるものを除く)、会計参与または監査役であったことがあるものにあっては、当該取締役、会計参与または監査役への就任の前10年間当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人であったことがないこと
という形で対象期間が制限されました。従前の会社法は、対象期間に制限がなかったことから、一度でも取締役等になった場合、社外取締役に就任することはできないことになっており、その点が問題とされていましたので、立法によって解決が図られることになります。なお、親会社の「元」取締役は(10年待つことなく)社外取締役になることができます。
談合と不当利得返還請求
弁護士 貞 嘉徳
はじめに
競争法当局の活発な法執行により、独占禁止法に関わるコンプライアンスの重要性は、現在広く理解されているところです。もっとも、同法違反の行為に対しては、課徴金納付命令などの競争法当局による行政上の手続だけでなく、刑事手続のほか、損害を被った被害者による民事的な手続がとられることがあります。今回は、いわゆる公共調達において談合をした事業者らに対し、国が契約の無効を前提として支払代金の返還を求めた事案(東京地裁平成22年6月23日[1])をご紹介します。
事案の概要
防衛庁(当時)が陸上自衛隊で使用される携帯無線機等に使用する専用の電池を調達するに際し、メーカー4社が、平成9年4月から同12年にかけて、談合の上、受注予定者を決定し、入札においてその受注予定者が落札できるよう調整していました[2](本件談合)。
国は、これら談合の結果として各メーカーと締結した契約(本件契約)は無効であるとして、支払代金額と各メーカーから納入された電池の価格相当額との差額を不当利得(民法704条)として請求しました。
主な争点
① 本件契約は無効か(独占禁止法違反の行為が私法上の行為に与える影響)。
② 本件契約が無効であるとしても、国の担当者が本件談合に関与していたのであるから、国が支払った代金は不法原因給付(民法708条)にあたり、返還請求は認められないのではないか。
③ 本件契約が無効であり、国が支払った代金が不法原因給付でなく、各メーカーがこれを返還しなければならないとしても、他方で、国は各メーカーから納入された電池の価格相当額を返還しなければならず(電池それ自体は既に費消されており、電池自体の返還は不可能であるため、その価格相当額の返還をしなければならない)、これをどのように算定すべきか。
裁判所の判断
① について
判決は、独占禁止法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反する契約の効力が争われた最高裁昭和52年6月20日(岐阜商工信用組合事件)を参照し、「独禁法3条に違反する契約の私法上の効力については、同条が強行法規であることによって直ちに無効であると解することはできず、当該契約が公序良俗に反する場合、民法90条によって無効となる」として、上記最高裁判決以降の裁判所の一般的な判断枠組みを踏襲し、結論として、「談合行為は、性質上、自由競争経済秩序という公の秩序に反する行為」であり、「談合の結果に基づきこれを実現するために締結された契約は、公序に反するものとして無効である」と判示しました。
本判決は、談合行為の悪質性に鑑み、その結果として実現された私法上の行為の効力を否定すべきとの判断を示したものといえます。
② について
判決は、「担当官は、被告ら4社からの要望に応える形で、予定価格を含む本件入札に関する情報を提供し・・・(中略)・・・原告が、本件談合の存在を認識、認容し、むしろ、これを助長する役割を果たしていたことを否定することはできない」と認定して、本件談合に対する国の関与を認めました。
しかしながら、「上記情報提供が一担当官の行う行為の限度を超えて、陸上自衛隊の組織として行われていた行為であると認めるに足りる証拠はなく」、また、「本件談合をするよう指示したり、事実上、本件談合を行うことを強制したなどの事情を認めるに足りる証拠もない」として、国の関与が組織的でなく、かつ、限定的であることを指摘し、これに対するメーカー側の悪質性を強調して、国が「本件談合を主導したと認めることができない以上」不当利得としての返還請求を否定すべきでないと判示しました。
本判決は、組織的な関与の有無及び本件談合を主導したか否かを判断要素として示しました。
③ について
判決は、電池の価額相当額について、「本件電池は、自衛隊専用電池として製造されたものであって、一般に市販されるものではないから・・・(中略)・・・市場価格によることはできない」ことを指摘し、その算定方法について、国が主張する算定方式は調達物品等の予定価格を定める際の旧防衛庁(現防衛省)の内部基準であって妥当でないとして採用せず、原価計算基準を採用しました。
具体的な算定については、数種類の電池があり、紙面の関係上、すべてに触れることはできませんが、判決は、あるメーカーとの関係では、製造原価と販管費に加えて、メーカーから主張された10%の利益を認め、また、他のメーカーからOEM供給を受けていた別のメーカーとの関係では、総利益(販管費及び利益)約30%の加算を認めました。
検討
独占禁止法違反の談合行為の結果として締結された契約については、その効力を否定するのが下級審裁判例の流れであり[3]、本判決の結論に異論はないと思われます。
民間における調達の場合であっても、この結論に差はないと考えられますが、民間の場合には、談合・カルテルの当事者と直接の契約関係にない当事者(例えば一般消費者)が被害者となることも多く、独占禁止法違反行為との関連性が弱いために契約の無効を主張して救済を求めるのが難しい場合には、損賠賠償の請求(民法709条、独禁法25条)によって被害の回復を図ることになります。この損害賠償の請求には、短期の消滅時効の制限があるので、注意が必要です[4]。
日本では、集団訴訟制度や立証上の問題から、独占禁止法違反の事案において、民事的な救済制度はあまり利用されていませんが、米国で民事訴訟が活発に利用されていることは有名ですし、EUでは民事的な救済制度を充実させるよう法案が提出されるなど目指している方向性は明らかです。このような流れの中、日本でも早晩、民事的な救済を求める事案が増えてくることが予想されます。加害者とならないよう注意するだけでなく、今後は、被害者となった場合にどのように対応すべきかという点を含め、独占禁止法の理解を深めていくことが求められています。
[1] 判例タイムズ 1392号
[2] 公正取引委員会による行政手続の詳細は、公正取引委員会HPを参照ください。
[3] 例えば、シール談合事件:東京地判平成12年3月31日、同控訴審東京高判平成13年2月8日。最近のものとして、東京地判平成23年6月27日。
[4] 民法724条:損害及び加害者を知ったときから3年。
独占禁止法26条2項:排除措置命令、課徴金納付命令又は審決が確定したときから3年。
遺言書と遺留分の話
弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村博子
1. 遺言書不作成のススメ
家族の関係が希薄になりつつあり、また一人で老後を迎える人達が増えてきたこともあって、近頃、遺言書作成の色々な案内がありますね。弁護士は、遺言作成のお手伝いも業務の一つですので、本当はこんなことをいってはいけないのかもしれませんが、相続人の一部に財産を集中させるような遺言書は作成しない方がいいというのが私の持論です。
遺言書は、後で相続人同士の争いを避けるためのもの。なぜ反対するの?と思われるかもしれません。しかし、現実には、なかなかそううまくはいきません。遺言書に書いたとおりに財産が分配されるとは限らないからです。
2. 遺留分の制度
(1) 遺留分とは?
日本には、遺留分という制度があり(民法1028条以下)、相続人が父母や祖父母といった直系尊属である場合には相続財産の3分の1,配偶者、子供(子供が先に死亡していた場合は代襲相続人としての孫)には、相続財産の2分の1までが遺留分として認められ、この遺留分を害するような遺言に対しては、遺言書に書かれた遺贈や贈与の減殺を請求できます(民法1031条)。減殺とは、その効力を遺留分額に限って、なくしてしまうとうことです。従って遺言者の思惑とは異なり、遺言どおりに相続財産が分けられるとは限らず、遺留分減殺請求がなされることも多く見られます。
その場合には、なまじ被相続人の意思が遺言書に記載されているがために、いわゆる相続争いは激化しがちです。遺留分減殺請求をする側からすれば、自分の知らないところで自分に不利な遺言書が作成されたということで、遺言者に裏切られたような気持ちになることが多く、かといってその時点では遺言者は既に亡くなっているので、勢いその怒りの矛先は、遺言書で有利に取り扱われている相続人に向かってしまいます。
私もやはり、相続人間での激しい争いをいくつか見てきました。双方共に、大変に消耗されていく様子を見るのは弁護士としてもつらいものがあり、なんでこんな罪作りな遺言書を作ったんだと、お会いしたことのない遺言者(被相続人)を恨みたくなるような気持ちになることもあります。遺言書は、文書として残りますので、遺言者の最後の意思として重く扱われますが、ご高齢の方の場合などは特に、その時々で考えが変わることも多く、確固たる最終意思が記載された遺言書といえるものは、本当は少ないように思います。
というわけで、私はご依頼者には、なるべく、相続人の一部を利するような遺言書は作らないようにとアドバイスしています。自分がいなくなってからのことまで心配せず、後は残った人に任せましょうと。
(2) 遺留分がなぜ認められているのか?
自分が築いた財産なのに、なぜ自分の思い通りに処分できないの?と遺留分の制度自体を不審に思われるかもしれません。この制度は昭和27年の民法改正で導入されました。それまでの家督相続が「家」制度につながるという理由で諸子均分相続制度に変更すべしとの意見に加え、配偶者保護の要請から、このような制度が規定されたのです。また遺言者の財産といっても家族で築いたものという点もあることから、潜在的に相続人は、遺言者の財産に一定の権利を有しているとの考え方もその背景にあります。
私自身は配偶者間では、この点への配慮はもっともだと思います。夫婦間では、一方名義の財産も二人で築き、守ってきたと言える場合が多いからです。しかし、子供に関しては、遺留分の制度が必要かは疑問に思っています。これらの人達が、財産の形成に関与することは現代では稀だからです。
(3) 遺留分減殺請求権の行使方法
このような遺留分の制度ですが、現実にその権利を行使する減殺請求については、相続の開始と減殺ができる遺贈や贈与があったことを知った時から1年以内に請求しなければ時効消滅してしまいます(民法1042条)。遺贈とは相続人や第三者に遺言書で以て財産の一部または全部を贈与することをいいます。遺留分減殺請求の対象になる贈与は死亡前1年以内のものに限られます(民法1030条)。また減殺請求できる贈与と遺贈がある場合、遺贈から先に(民法1033条)、そして時系列的に新しいものから先に減殺請求の対象となります(民法1035条)。
3. 遺留分の放棄と推定相続人の廃除
このように遺留分の制度は複雑で、また上では触れませんでしたが、その計算方法も様々な考え方があり、どうしても紛争化すると長期、深刻なものになってしまいます。それも私が遺言書不作成のススメをする理由です。
それでも,どうしても諸事情で財産を一定の人に集中させる必要がある・・・という場合には、方法がないわけではありません。被相続人の生前の相続放棄は認められていません。被相続人に対して、①虐待をし、②重大な侮辱を加え、または③その他著しい非行がある推定相続人には、被相続人は家庭裁判所に相続人の排除の請求をすることができますが(民法892条)、②、③のような事情については、よほどのことがないと裁判所では廃除が認められません。
そこで、一定の人に財産を相続させる、遺贈するというような遺言書を書き、それに対して遺留分を持つ相続人に、あらかじめ遺留分の放棄をしてもらうことが考えられます(民法1043条)。
しかし、この放棄は、家庭裁判所の許可がなければ効力を生じません。裁判所の許可の基準については、必ずしも明確ではありませんが、①放棄が放棄者の真意に出たものであること、②放棄に合理的・必要的理由があること、③放棄に対する代償財産の提供があること等が要素として検討されているようです。基本的には、真意に基づくものか、裁判所が確認できればよいのではないかと思っています。
フランチャイズ契約における情報提供義務と競業避止義務が問題となった事例
弁護士 西村真由美
【はじめに】
今回は,フランチャイズ契約(以下「FC契約」という)における情報提供義務と競業避止義務が問題となった大阪地判平成22年5月27日(判時2088号103頁)をご紹介します。
フランチャイズにはいくつかの定義がありますが,一般的には,本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)に対して,特定の商標,商号等を使用する権利を与えるとともに,加盟者の物品販売,サービス提供その他の事業・経営について,統一的な方法で統制,指導,援助を行い,これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされます[1]。
【事案の概要】
高齢者向け弁当宅配事業を営むフランチャイザーである原告が,元フランチャイジーである被告に対し,被告との間で締結したFC契約(以下「本件FC契約」という)解除後も高齢者向け弁当宅配事業を継続しているとして,本件FC契約における競業禁止特約[2]に基づき,営業の差止めを求めました(第1事件)[3]。
これに対して,被告は,本件FC契約締結に当たり,原告が誤った売上予測を提供したために,被告において損害が生じたとして, 被告が原告に対し,債務不履行[4]に基づき,加盟金,ロイヤルティ等合計3861万円の損害賠償を求めました(第2事件)。
【争点】
1 被告の競業避止義務違反の有無
2 原告の情報提供義務違反の有無
【判旨】
第1事件請求認容,第2事件請求棄却
争点1(被告の競業避止義務違反の有無)
(1) 結論
義務違反を肯定
(2) 理由
本判決は,「競業禁止特約は,その制限の程度いかんによっては営業の自由を不当に制限するものとして公序良俗に反して無効になる場合がある」とした上で,「本件FC契約における競業禁止特約は,・・原告の経営ノウハウの保護を目的としているものと解される。このような目的に照らすと,期間を5年として,対象者を加盟者及びその関係者とし,区域を定めず,経営だけでなく出資や従事を禁止することも直ちに合理性がないとまではいえず,これに加え,同特約には,期間,業種の限定があり,条項上は地域的限定がないものの,原告の本件請求においては,旧a奈良南店と同一店舗及び奈良県内と区域が限定されており,違反した場合における違約金の定めもないことを併せ考慮すると,同特約は加盟店の営業の自由を不当に制限するものとはいえず,公序良俗に反するものではないというべきである。」として,競業禁止特約を有効とし,被告が,本件店舗と同一の場所において弁当の宅配を行っており,そのメニューや価額がほぼ同一であることから,原告と同一の事業を行っているものと認められるとして,被告の競業禁止特約違反を肯定しました。
争点2(原告の情報提供義務違反の有無)
(1) 結論
義務違反を否定
(2) 理由
本判決は,「フランチャイズ・システムにおいては,一般にフランチャイジーは,店舗経営の知識や経験に乏しく,フランチャイザーから提供される情報に大きな影響を受けるのが通常であり,また,フランチャイズに加盟しようとする者にとって,フランチャイザーから提供される売上予測は,加盟するか否かを決定する際の重要な要素となるから,FC契約締結に向けた交渉の過程において売上予測を提供する場合には,フランチャイザーは,フランチャイジーに対し, 客観的かつ正確な情報を提供すべき信義則上の保護義務を負っているものというべきである。」とした上で,本件FC契約締結前に,原告は被告に対して,当時の被告の収入と同程度の収入を得ることが可能である旨述べただけであって,明確な売上予測として示されたものではない上,被告が営業努力によって顧客を獲得することを前提とした説明であって,その説明において必ず原告提示の35,6万円の収入が得られると誤認させるものであったとは認められず,被告がその収入を得ることはできていないのは,本件店舗における被告の経営の仕方に由来するものであって,原告の売上予測が誤りであったことの根拠にはならないとして,原告の情報提供義務違反を否定しました。
【検討】
1 情報提供義務違反の判断基準
本判決は,「信義則上の保護義務」として,フランチャイザーが,FC契約締結に向けた交渉の過程において売上予測を提供する場合には,フランチャイジーに対し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務を負うと認めた上で,原告にその義務違反は認められないとしています。一般的に,フランチャイザーとフランチャイジーとの間には知識,経験及び情報の格差が存在することから,フランチャイザーが,フランチャイジーになろうとする者がFC契約を締結するか否かについて的確な判断ができるよう正確な情報を提供すべき信義則上の義務を負うことについては,判例法理として確立しています[5]。
もっとも,一般論として,フランチャイズ・システムにおける事業リスクはフランチャイジーが負担するのが原則であるため,売上予測は,実際に予測と異なる結果が発生したとしても,それ故に直ちに義務違反となるわけではありません[6]。これまでの裁判例においては,売上・収益予測に関する情報提供義務違反の判断基準として,①売上・収益予測の手法の相当性・合理性,及び②売上・収益予測の適用過程の相当性・合理性という2点を考慮しているようです[7]。
2 競業禁止特約について
競業禁止特約とは,契約期間中あるいは契約終了後において,相手方に対して,自己と同種の事業を行うこと等の競業行為を禁止する特約であり,これには,自ら競業事業を起こすことのみならず,競業他社へ就職することをも禁じる内容を含まれます。FC契約においては,フランチャイザーは,フランチャイジーに対し,営業秘密,ノウハウ及び内部情報等を提供するため,フランチャイジーがフランチャイザーと同一または類似の営業をしたり,提供を受けた営業秘密等を不正に利用したりすることは,フランチャイザーのみならず当該フランチャイズ・システム全体を脅かすものになりかねません。そのため,FC契約においては,一般的に,フランチャイジーによる競業や秘密開示を防止するために競業避止義務に関する規定が設けられます。
もっとも,契約終了後もフランチャイジーに競業避止義務を負わせることは,フランチャイジーの営業の自由や職業選択の自由を制限し,また,投下資本回収を妨げるなど,フランチャイジーにとって大きな不利益となります。そこで,裁判例[8]では,かかる競業制限が合理的であるか否か,具体的なケースごとに合意の対象となった期間・地域・営業の種類などについてその程度を見極め,公序良俗違反の存否を通して,特約の有効性が判断されています。
本件の競業禁止特約は,期間を5年とし,地域限定がないという点では,相当程度被告の営業の自由を制限しているようにも見えます。しかしながら,かかる場合でも,特約に基づく実際の差止め請求において区域を限定することにより,場所に関する制限の合理性を確保する可能性が肯定されている点は,留意すべきであると考えられます。
[1]「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(平成14年4月24日公正取引委員会)
[2] 本件FC契約においては,「被告又は被告の関係者は,原告の承諾なく,本件FC契約の有効期間及び同契約終了後5年間は,当チェーンの事業の経営,出資,従事等をしてはならない。」旨の特約が存在しました。
[3] 原告は,この他に被告に対し未払のロイヤルティ等合計512万円余りの支払を求め,全額認容されています。
[4] 被告は,本件FC契約締結前の情報提供義務違反の他にも,原告が契約締結後に適切な経営指導等をしなかったとして債務不履行を主張しましたが,判決では,経営改善のための指導等が行われていたとして,原告の経営指導義務違反は否定されています。
[5] 「コンビニエンス・フランチャイズ・システムをめぐる法律問題に関する研究会報告書(1)」NBL948号
[6] 西口元ほか編「FC契約の実務」新日本法規出版株式会社
[7] 前掲「コンビニエンス・フランチャイズ・システムをめぐる法律問題に関する研究会報告書(1)」
[8] なお,FC契約における競業避止義務違反の有無の判断にあたっては,単にフランチャイジーの投下資本回収の必要性が認められるというだけでなく,フランチャイザーによる不適切な勧誘行為を契機として,フランチャイジーが多額の資金を投下することになったという点を重視し,競業避止義務違反を認めた裁判例(大阪地判平成22年5月12日判時2090号50頁)もあり,情報提供義務違反が競業避止義務違反に影響を与えるものとして参考になると考えられます。
労働契約法改正に伴う有期労働契約の取扱
弁護士 西村真由美
1 法改正の経緯
平成24年8月10日,有期労働契約に関する新たなルールの制定を内容とする改正労働契約法が公布されました。有期労働契約は,社会の変化に応じた多様な働き方を選択できるものとして広く利用されていますが,正規雇用の労働者と比べ,雇用の不安定さ,賃金,能力開発の点において格差があるとしてこれまで問題となっていました。特に,リーマンショックに端を発した経済危機の後,雇用情勢が急速に悪化し,「派遣切り」とともに「雇止め」が大きな社会問題として注目されています。このような流れを受け,有期契約労働者の保護を目的とした法改正がなされ,平成25年4月1日より施行されています[1]。
2 法改正の概要
本改正では,有期労働契約の適正な利用のために,主に以下の3点が整備されました。第1に有期労働契約から無期労働契約への転換(法18条),第2に「雇止め法理」の法定化(法19条),第3に不合理な労働条件の禁止(法20条)です。
(1)有期労働契約から無期労働契約への転換
有期労働契約から無期労働契約への転換制度は,本改正の目玉とされるものであり,改正法施行後に締結された有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき[2]は,労働者の申込みにより,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるという制度です。この制度により無期労働契約に転換した労働者には,別段の定めがない限り,契約期間を除いて従前と同じ労働条件が適用されることとなります。もっとも,労働協約,就業規則及び労使間の個別の合意において「別段の定め」を設けることにより,契約期間以外の労働条件について変更することは妨げられません。
(2)「雇止め法理」の明文化
有期労働契約に関し,最高裁判例[3]で確立している雇止めに関する判例法理が明文化されました。雇止め法理とは,当該有期労働契約が,有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態にある場合,または雇用の継続に対する労働者の合理的な期待がある場合には,解雇権濫用法理(法16条)が類推適用され,雇止めが客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないときは,従前の有期労働契約が更新されたとみなす,というものです。改正法では,これに「期間満了日までに労働者が有期労働契約の更新の申込みをした場合」または「期間満了後遅滞なく有期労働契約締結の申込みをした場合」という要件が加えられています。
(3)不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が,期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合,その相違は,職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して,不合理と認められるものであってはならないとされます。これに関しては,具体的にどのような場合に労働条件が不合理であると認められるかは個別具体的事情により様々であり,今後の裁判例の蓄積が待たれるところです。
3 企業にとっての注意点
以上の改正に伴い,企業としては以下の点に注意する必要があります。
(1)就業規則の整備
前述のとおり,無期労働契約転換後の労働者については,別段の定めがない限り,契約期間を除いて従前と同じ労働条件が適用されることとなります。したがって,無期転換申込権を行使した労働者は,直ちに正規雇用の労働者と同一の取扱いを受けるわけではありません。
もっとも,法12条は,「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については,無効とする。この場合において,無効となった部分は,就業規則で定める基準による。」として,就業規則の最低基準効を定めており,無期転換後の労働者の労働条件が正規雇用の労働者の就業規則の基準を下回る場合に,就業規則上の基準が適用されてしまう余地があります。
そこで,企業としては,正規雇用労働者向けの就業規則のみならず,法18条における「別段の定め」として,無期転換後の労働者に適用される就業規則等を今後新たに整備する必要が出てくると考えられます。
(2)無期転換申込権の放棄
本制度はあくまで労働者から使用者に対する申し込みが要件となっており,労働者としては,無期転換申込権を自らの自由意思に基づき放棄することは当然可能です。しかしながら,有期労働契約者には,そもそも雇止めの不安があり,正当な権利行使を控えてしまいがちであることから,無期転換申込権の放棄についても,それが自由な意思表示に基づくものであると認めるに足る合理的理由が客観的に存在する必要があると考えられます。したがって,企業としては,労働者による無期転換申込権の放棄が自由な意思表示に基づくものでなかったと主張されぬよう,書面による十分な説明と熟慮期間を与えるといった措置をとることが後の紛争を防止するために肝要です。
(3)今後の運用
現在,常用労働者に占める有期契約労働者の割合は約22.5%であり[4],非正規労働者の人数は,今年1月からの2カ月間で約65万人増加しています[5]。また,安倍政権下で進められている雇用制度改革においては,今回紹介した法改正とは逆の方向,すなわち労働市場の流動化,解雇規制の緩和や,職務や勤務地を絞った限定正社員制度の普及等が提唱されており,今後,雇用の構造が大きく変わる可能性が高まりつつあります。このような社会変化に伴い,これまで問題とならなかった新たな労使間紛争が生じてくることも考えられます。
改正労働契約法の解釈においては,未だ未確定な部分も存在するため,企業としては,今後の具体的な紛争の蓄積とそれに対する裁判所の判断を注視していかねばなりません。それとともに,多様化する雇用形態の選択肢の一つとして,今後の有期労働契約者の活用を考えた運用の在り方を検討する必要があります。
[1] 本改正のうち,法19条(有期労働契約の更新等)については,従来の雇止めに関する判例法理を明文化したものであり,実質的変更が加えられているわけではないので,改正法の公布日である平成24年8月10日から施行されています。
[2] 5年の通算契約期間を算定する際,原則として前の有期労働契約との間に6カ月以上の無契約期間(クーリング期間)がある場合には,その前の契約期間は通算されません。
[3] 法19条1号に対応する判例として,東芝柳町工場事件(最判昭和49年7月22日民集28巻5号927頁),同条2号に対応する判例として,日立メディコ事件(最判昭和61年12月4日判時1221号134頁)。
[4] 厚生労働省「有期労働契約に関する実態調査」
[5] 総務省統計局「労働力調査」
FRAND宣言と特許権者の誠実交渉義務-アップル対サムスン電子事件-
弁護士 田中 敦
【はじめに】
本年2月28日,東京地裁により,アップルとサムスン電子(以下「サムスン」といいます)との間の特許権侵害に関する訴訟について国内2例目の判決(以下「本判決」といいます)が下されました。
本判決では,サムスンが,問題となったパケット通信技術に関する特許権(以下「本件特許権」といいます)について下記「本判決の検討」にて詳述するFRAND宣言を行っていたことから,本件特許権の行使が権利濫用にあたると判示されました。
今回は,アップルとサムスンという世界規模の巨大企業間の紛争の経緯について若干触れつつ,本判決の判示内容について,FRAND宣言を行った特許権者の誠実交渉義務と権利濫用との関係を中心に解説します。
【両社の紛争の経緯】
アップルとサムスンは,サムスンからアップルへ液晶パネル等の部品供給を行うなど,長年にわたり提携関係にありました。しかしながら,サムスンが,スマートフォン・タブレットPCの市場で台頭するにつれ,同市場の先導者であったアップルとは競争関係に転じるようになりました。今回,アップルがサムスンに対し特許侵害を主張したことは,サムスンをはじめとするアンドロイド陣営への牽制を意図したものという見方もあります。
平成23年4月,カリフォルニア州にて,アップルがサムスンに対しデザイン特許[1]等の侵害を主張して最初の訴訟を提起しました。以降,両社の争いは激化し,現在では計10カ国の裁判所で両社間の訴訟が進行しています。そして,同一のデザイン特許についてカリフォルニア州連邦地裁とソウル中央地裁で侵害・非侵害の判断が分かれるなど,各国の裁判所によってその判断が分かれています。
日本では,平成24年8月31日に東京地裁により国内初の判決が下され,サムスンによる特許権侵害を否定して,アップルの損害賠償請求が棄却されました。
本稿でご紹介する本判決(東京地裁平成25年2月28日判決)は,前述のとおりアップルとサムスンとの紛争における国内2例目の判決であって,国内1例目の事案とは異なり,サムスンが権利を有するパケットデータ送受信についての特許権を,アップルに対して行使できるか否かが問題となった事案です。
【本判決の検討】
1 サムスンによるFRAND宣言
本件特許権にかかるパケットデータ送受信技術についての特許は,アップルとサムスンの両社が加入する第3世代移動通信システム[2]の技術標準化団体である「Third Generation Partnership Project」(以下「3GPP」といいます)により,一定規格に準拠した製品を製造する際の必須特許として指定されています。
サムスンは,3GPPの中心的構成団体である欧州電気通信標準化機構(以下「ETSI」といいます)が定めたESTI知財ポリシーに従い,本件特許権についてはその利用を希望する者に対して「公正,合理的かつ非差別的(Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory)な条件」(FRAND条件)でライセンス許諾する準備があることの宣言(FRAND宣言)を行っていました。
本件の訴訟に先立ち,アップルがサムスンに対しFRAND宣言に従い本件特許権のライセンス許諾を行うことを求め,平成23年7月以降両社間でライセンス契約締結に向けた協議が行われましたが,ロイヤルティ等について意見が一致せず,最終的な契約締結には至りませんでした。
2 東京地裁による判示内容
(1) 争点
本判決では,サムスンからの本件特許権の侵害の主張に対し,アップルが特許権侵害に基づくサムスンの損害賠償請求権の不存在確認を求めて提訴したところ,①アップルの製品に使用された技術が本件特許権の技術的範囲に属するか否かに加え,②サムスンによるFRAND宣言と両社のライセンス契約締結に向けた協議の経過に照らし,サムスンによる本件特許権の行使が権利濫用にあたるか否かが主な争点となりました。
(2) 争点についての判断
裁判所は,まず①の争点につき,アップルの一部の製品に使用された技術が本件特許権の技術的範囲に属することを認定しました。
次に,裁判所は,②の争点につき,FRAND宣言を行った特許権者は,ETSIの加入者か否かを問わずライセンス許諾を希望する者に対しライセンス契約の締結に向けて重要な情報を提供して交渉を誠実に行うべき信義則上の義務(以下「誠実交渉義務」といいます。)を負うとし,サムスンが誠実交渉義務に違反したか否かを検討しました。
裁判所は,1年以上にわたる協議の中で,サムスンが,アップルからの再三の要請にもかかわらず,提示したロイヤルティが「非差別的な条件」であることの根拠資料(他社とのロイヤルティ等)を一切示さなかったこと,ライセンス内容についてアップルからの提案への具体的な対案を示さなったことを主な理由として,サムスンによる誠実交渉義務違反を認めました。
そして,裁判所は,誠実交渉義務違反を含む協議の経過等に鑑みれば,サムスンによる本件特許権の行使は権利濫用にあたり許されないとしました。
(3) 結論
以上の争点についての判断を踏まえ,裁判所は,サムスンがアップルに対し本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認すると判示し,原告であるアップルによる不存在確認請求が認容されることとなりました。
3 検討
本判決は,サムスンによる本件特許権の行使が許されない根拠として「権利濫用」(民法1条3項)を挙げています。これは,両社の協議経過等に照らして本件でのサムスンによる権利行使を否定したもので,FRAND宣言を行った特許権者による特許権行使を一律に否定する趣旨ではありません。
しかしながら,本判決は,FRAND宣言を行った特許権者がライセンス許諾を希望する者に対し誠実交渉義務を負うことを明確にし,当該誠実交渉義務違反の有無を中心に権利濫用の成否を検討するとの判断基準を示したものと理解できます。
また,本判決は,FRAND宣言の効果が及ぶ範囲について,FRAND宣言を行った特許権者は,ETSIの加入者か否かを問わずライセンス許諾を希望する全ての者に対し誠実交渉義務を負うと判断しました。
FRAND宣言を行った特許権者が負うべき義務内容,FRAND宣言の効果が及ぶ範囲については,これまでその解釈に議論があったところです。本判決は,それら論点について日本国内で初めて判断を示した裁判例となります。
【終わりに】
本件特許権についてのFRAND宣言は通信技術の規格標準化のための必須特許について行われたものですが,一つの規格の標準化のためには数百から数千もの必須特許が存在する場合があり,そのうちたった一つの特許権であっても技術全体の使用を妨げるものとなり得ます。そのため,FRAND宣言が行われた必須特許について特許権者の権利行使を認めるか否かは,権利行使を受けた企業の利益のみならず,当該技術の属する産業全体の発展についても影響を与える重要な問題となります。
本判決に対してはサムスンから控訴がなされたと報道されており,今後の動向を注視する必要がありますが,本判決は,FRAND宣言を行った特許権者による特許権行使の可否を初めて判断した裁判例として,重要な先例的意義を持ち得るものと思われます。
[1] デザイン特許(Design Patent)とは,米国特許法により「物のデザイン」について付与される特許権であり,日本における意匠権に相当するものです。
[2] 第3世代移動通信システムとは,国連の専門機関である国際電気通信連合(International Telecommunication Union)が定める「IMT-2000(International Mobile Telecommunication 2000)」規格に準拠した携帯電話の通信システムのことで,現在日本国内で利用される携帯電話の多くが当該通信システムを採用しています。これに対し,最近新たに市場に導入された「Long Term Evolution(LTE)」による通信システムは,「第3.9世代移動通信システム」または「第4世代移動通信システム」と呼ばれています。
紛争鉱物規則-米国Dodd Frank法による一つの証券開示規制
弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村博子
紛争鉱物?米国での証券開示規制?米国で上場していない私の会社には関係無いと思われるかもしれません。しかし、そうとは言えない、日本の会社にも影響を及ぼしかねない規制なのです。
1.規制の概要
この紛争鉱物開示規制は、2008年のリーマンショックを引き起こしたプライムローン問題の後、金融業界、証券業界のいっそうの規制が必要と考えられて、2010年に制定された金融改革法[i]の各種規制の中でも異色の規制ですが、紛争地域(中心はコンゴ民主共和国[ii]で、その近隣諸国も含みます)で産出される特定の鉱物(ここでは、錫(すず)、タンタル、タングステン、金等のレアメタル)を使っているか否かを精査して、報告する義務を米国証券取引所に上場している企業に課すというのが、この開示規制の中心です。その調査については、単に自らの使用状況だけでなく、その製造する製品の部品等に含まれるこれらのレアメタルについても、原産地を調べて報告する義務があります。紛争地域からの物でなければ、その旨報告すれば良いのですが、紛争地域が原産国かもしれないとなるとさらに、精査をし、詳しい報告書を証券取引委員会(SEC)に提出する必要があります。
サブプライムローン問題の前の金融問題であったエンロン事件後に制定されたサーベンス・オクスレー法[iii]が内部統制の調査とその結果の開示を求めているのと似たような規制の方法です。当然、対象企業は、そのサプライチェーンを追いかけて精査をする必要があり、このようなレアメタルを使った部品やOEM製品を納入しているサプライヤーに対しては、同様に紛争鉱物でないかの調査と報告を求めることになります[iv]。
錫はハンダの材料ですし、タンタルはコンデンサ、特に携帯電話やPC等に用いられる小型のコンデンサに。またタングステンは硬度が高いため切削工具や電極、電球のフィラメントなどに使われることが多い金属ですので、これらに関わる企業は、米国の上場企業だけで6000社、その部品納入に関連する企業はさらに膨大になります。
2.規制の影響
米国上場企業に課される、この報告書の第1回目は、2012年中の紛争鉱物の使用に関して、2014年5月に提出義務が定められていますので、日本の会社に対しても米国の上場企業から、これらのレアメタルを使用した製品を納入している会社には、問い合わせが行きはじめているのではないかと思われます。当然米国の上場企業は、紛争鉱物を使用している製品をこれからは購入できなくなりますから、日本の企業も紛争鉱物を用いないようにしなければ取引を停止されかねず、米国証券取引所に上場していないにもかかわらず、同様の精査をする必要が出てきます。
現在のように、日本の企業が他国で原料調達から製造まで行い、米国企業やその子会社に製品を販売するというようなビジネスが展開がされていると、日本の企業も米国での法律の間接的な対象となってしまうのです。
3.規制の趣旨
話が前後しますが、なぜ米国はこのような規制を考えたのでしょうか。米国は、反トラスト法[v]や外国汚職防止法[vi]の例にとどまらず、自国の法をあたかも他国にも及ぼすかのようにして、世界の秩序(FairnessとAccountability)を守ろうとしてきました。米国が世界の警察、世界の監視人であるという態度の是非はともかく、米国の発信するこのような秩序維持の方法は、いずれもグローバルスタンダードになりつつあります。
コンゴについては、隣国ルアンダのジェノサイドほどには報道がされてきませんでしたが、レアメタルの大産出国でありながら、いえ、かえってそれが災いして、また他民族国家であることとも関連して過激な紛争が続き、1998年からの第2次コンゴ戦争では500万~600万人が死亡、その後も治安の悪化は止まらず、女性に対するレイプも頻発していると伝えられます。また、このような紛争鉱物からの資金が、そのまま武装勢力の資金となっているとも言われています。米国としては、その資金源を絶つことで紛争の鎮静化を図りたいとの考えがあるのでしょう。確かに隣国ルアンダは平和を取り戻し、この10年はIT産業の活況が伝えられ、アフリカの奇跡とさえ言われています。平和と安全を取り戻すために、その元を絶つことも一つの方法となり得るのかもしれません。
[i] Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Actの1502条に関連しています。
[ii] コンゴ民主共和国は、英語でDemocratic Republic of theCongoとされ、紛争鉱物規則ではDRCと呼ばれます。
[iii] 余談ですが、金融改革法は、格付機関からのロビー活動もあり、サーベンスオクスレー法が手を付けることができず(「サーベンス・オクスレー法概説」商事法務第1章苗村担当参照)、サブプライムローン問題を引き起こすことともなった格付機関に対する規制を盛り込みました。本年になって司法省がスタンダード&プアーズを同ローン問題で提訴する事態となったのも、この金融改革法での格付け機関への規制の影響によるものと思われます。
[iv] 米国証券取引委員会(SEC)はこの開示規則とその報告書のフォーム(Form SDと呼ばれます)とを https://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf に記載しています。
[v] 米国のSharman Actを中心とするいわゆる反トラスト法は、行為が他国で行われていても、その影響が米国の通商に影響を及ぼす場合には、かような行為についても摘発を行うという姿勢(Extra Territoria Application)を取っています。
[vi] Foreign Corrupt Practices Act、FCPAと呼ばれるこの法律は、外国の企業であっても、外国公務員への賄賂を、米国に有する銀行口座を用いて、または米国の企業と共謀して行った場合に、同法で処罰するという、外国公務員への賄賂を禁止する規定と、Dodd Frank法と同じように証券取引所法(1934年Security Exchange Act)の中で、そのような外国公務員への賄賂を開示していないことについての規制の2種類があります(https://www.namura-law.jp/pdf/tdb110221.pdf)をご参照ください。