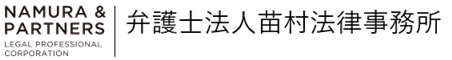アーカイブ
M&A と個人情報保護法
弁護士 佐藤 有紀
個人情報保護法の改正案が本年9月3 日に可決され同9 日に公布されました。今回の個人情報保護法改正は、ビックデータの利活用のための「匿名化情報」のルール整備、個人情報のトレーサビリティ確保、グローバル化への対応を始め非常に多岐に渡りますが、今回は、個人情報保護法とM&A が交わる場面について検討したいと思います。
一般的に、事業譲渡等M&A に係る契約においては、売主側企業が競業避止義務を負うことが明記されることが多いというのは皆様ご存知のとおりです。これに加えて、いわゆるB to C のビジネス形態では、顧客の個人情報や趣向に関するデータが非常に重要であり、事業譲渡、合併、会社分割等により当該ビジネスを買い受ける場合には、買主側企業において、かかる情報を独占的に利用できるよう担保することが不可欠となります(*1)。そのため、顧客の個人情報等が重要な資産となりうるM&A においては、買主側企業から、売主側企業やその親子会社・グループ会社(*2)に対して、M&A 完了後は当該個人情報等は廃棄し、一切の利用を禁止する規定が設けられることがあります。売主側企業は、このような情報等をM&A後も利用する予定なのかを十分に検討した上で、個人情報の取扱いを決めるべきでしょう。なお、M&A を行った前後で、取得時の利用目的から変更される場合には、情報主体である顧客の同意が必要となる場合があります(*3)ので、同意が必要なのか、プライバシーポリシーの変更の公表や通知で足りるのか、対応が全く必要ないのかについて、担当部署、リーガル、外部弁護士等で十分に検討すべきと思われます。
(*1) 個人情報保護法23 条4 項2 号では、事業譲渡、合併等による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合、承継者は第三者提供の制限を定めた同条との関係で「第三者」に該当しないとされています。売主側企業において取得~保管の過程で法令違反や何らかのトラブルがなかったかを、デューディリジェンス、インタビュー等で確認すべきことは言うまでもありません。
(*2) 個人情報保護法23 条4 項3 号に定める「共同利用」により、例えば、プライバシーポリシーで、親子会社で個人情報を共有し当該親子会社のプロダクトの広告送付・送信などに個人情報を利用すると定められているような場合です。
(*3) 「相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」での利用目的の変更のみが認められます(個人情報保護法15 条)。法改正施行後は、「関連性」があれば(「相当」部分の削除)変更が認められます。
Tripp Trapp 事件の波紋 =応用美術の権利性は広がるか?=
弁護士 苗村 博子
平成27 年4 月14 日、知財高裁が、珍しく著作権の範囲で画期的な判決を出した。侵害そのものは認めなかったものの、実用品の最たるものである椅子のデザインについて、著作権を認めたのだ。これまで知財立国と言うにはほど遠く、応用美術にはほとんど目もくれないのが裁判所だった。他の多くの国では、応用美術にも著作権を認めているが、実用品については、特別顕著な創作性がなければだめだという理論で、著作物性すら認めないのが、今までの裁判所の態度だったのである。実用品で認められたのは、ほとんど一刀彫りといえる高級仏壇くらいである。裁判所は実用品のデザインを保護するのは3 年の保護期間しかない意匠権で十分だと考えていた節がある。そしてこの考えを美術以外のもの、たとえば私が一審で敗訴した(二審で相応の和解)建物やその他にまで及ぼし、著作物性の範囲を極端に狭く解するようになってしまい、私たち知財弁護士を悩ませ続けたのである。
知財高裁は言う。「著作権法が『文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的と』している事に鑑みると、表現物につき、実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって、直ちに著作物性を一律に否定することは、相当ではない。」と。そして、絵画、版画、その他の美術の著作物をあげる2 条1 項に、美術の著作物には美術工芸品を含むものとするとある2 項は、単なる例示に過ぎないとして、「例示にかかる『美術工芸品』に該当しない応用美術であっても、同条1 項1 号所定の著作物性の用件を充たすものについては、『美術の著作物』として、同法上保護されるものと解すべきである。従って、X 製品は、上記著作物性の用件を充たせば、『美術の著作物』として同法上の保護を受けるものといえる。」ともいう。待ち焦がれていた認定である。これからはいわゆるそっくりさん製品は姿を消して行くことになり、初めてそのデザインを想起し、表現した人に権利が与えられることになってくれることを切に願っている。
専属的国際裁判管轄合意に関する注目される判例動向
弁護士 渡辺 惺之
平成24 年民訴法改正により新設された国際裁判管轄合意に関して注目すべき判例が現れている。大阪高判平成26年2 月20 日(判時2225 号77 頁)と東京高判平成26 年11 月17 日(判時2243 号28 頁)である。いずれも契約書面上に外国裁判所を専属的管轄合意した条項が明記されていたが、公序に反し無効として日本裁判所の管轄を肯定した事例である。外国裁判所を専属的裁判所とする国際裁判管轄合意の内容が「著しく公序法に反する」場合は無効とし、日本裁判所への提訴を許すことができること自体は、平成24年改正前からチサダネ号事件最高裁判例(最判昭和50 年11 月28 日(民集29 巻10 号1554 頁))が判示し判例法理として確定していた。しかし、国際裁判管轄合意について全く制定規定を欠く状態であった法改正以前と、国際裁判管轄に関する規定が整備された改正後とでは、同一法理でも、適用・解釈に違いが生じ得る。
チサダネ号事件判例法理における「公序」判断のポイントは、専属的管轄合意により取引上の弱者に一方的に不利な管轄裁判所を押しつけられたり、法的知識が充分でない一般人が約款上の管轄合意により提訴を著しく困難にさせられたりする事態を避ける趣旨にあった。このような事態への予防として、管轄合意は書面による合意を要するとか、商法上の商人間に限るとか等の要件規制も外国法には見られる。平成24 年改正法は、このような
事態への対応として、弱者保護の観点から、消費者契約、労働契約については強い制限を課して、不適切な結果の防止を図っている。反面、事業者間の契約に関しては、日本の裁判所を専属的合意裁判所とする合意管轄については「特段の事情」による却下を認めず、管轄合意の有する紛争解決への予見可能性を保護している。この視点との整合性を重視すると上記判例はいずれも議論の余地を残すと思われる。今後の議論の展開に注目したい。
交通事故被害者の破産
弁護士 立川 献
<事案のご紹介>
甲(破産者)は、住宅ローン支払い等により消費者金融から借入を行なっていた。しかし、交通事故に遭い、代理人A により示談交渉を行い、傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料及び後遺障害逸失利益に相当する損害賠償金がA の口座に振り込まれた(以下「本件預り金」)。他方で、甲は上記借入等についての債務整理を経て、破産手続開始の申立を行った。
裁判所により破産手続開始決定がされ、X が管財人に選任されたが、本件預り金について、X は、破産財団を構成するとして引き渡しをA に請求したが、A に本件預り金の引き渡しを拒否されたため訴訟を提起した。
<解説>
1 破産手続と交通事故
事故が破産手続開始決定後に発生した場合、事故による損害賠償請求権は破産者が開始決定後に新しく得た財産=「新得財産」となり、破産管財人による管理・処分の対象にはなりません。
しかし、ご紹介した事案のように、破産手続開始決定前に交通事故が発生した場合には、「破産手続開始決定時の財産が破産財団を構成する」という「固定主義」に基づき、交通事故により発生した損害賠償請求権は、原則破産管財人による管理・処分の対象になると考えられます。
破産者は生活に困窮する可能性が高いといえますが、そのうえ事故による損害賠償金を受け取れないとすると、破産者の生活再建もままなりません。この点が争われたのが、大阪高裁平成26 年3 月20 日付判決です。
2 裁判所の判断と今後の対応
B は、本件預り金については自由財産に該当することなどを主張しましたが、裁判所は、破産手続開始決定前に損害賠償請求権が代理人の預り金に転化した点を指摘し、自由財産に該当しないと判断しました。
現状、事故による賠償金を破産者が利用するために、「自由財産の拡張」という方法が考えられています。また、慰謝料請求権は、行使するかが被害者に委ねられている権利であり、その行使の時期等についての工夫が必要です。
各損害費目の性質や債務者の状況を踏まえ、どの範囲で自由財産の拡張が認められるか、いかなる対応をすべきかにつき、実務的な蓄積が待たれるところです。
中小企業の知的財産を融資につなげる支援の取組み
弁護士 田中 敦
1 制度について
本年5 月、特許庁が、中小企業による知的財産を活用したビジネスについての評価書の作成支援制度(以下「本制度」といいます。)に基づく融資案件の公募を開始しました。本制度は、自社の有する知的財産の価値を利用して資金調達をしたいという中小企業のニーズと、知的財産の適正な評価を行う人材が金融機関に不足している実情を受け、中小企業への融資拡大のために創設されたもので、昨年度に試行的に実施され、本年度から本格的に実施されることとなったものです。
2 支援の仕組み
本制度に基づく支援の仕組みは以下のとおりです。
①支援対象となる融資の公募
特許庁が、金融機関を対象として、本制度に基づく支援を希望する融資案件を公募します。金融機関による応募にあたっては、中小企業等への融資であること、融資対象企業 の内諾を得ていること等の応募資格があります。
②調査会社による調査・評価書の作成
特許庁と提携する調査会社が、融資対象企業が有する知的財産を踏まえたビジネスの価値を評価し、「知財ビジネス評価書」(以下「評価書」といいます。)を作成します。 評価書作成にかかる費用は、特許庁がその全額を負担します。
③金融機関への提供
調査会社から金融機関へ評価書が無償で提供され、当該金融機関は評価書に基づいて融資対象企業への融資判断を行います。
3 今後の課題等
本制度の利用により、金融機関が、中小企業の適正な事業価値を把握できるとともに、経営改善のアドバイスやビジネスマッチングにも評価書を活用できるというメリットがあります。他方で、本制度で評価対象となる知的財産は、特許、実用新案、意匠、商標に限られています。中小企業による特許出願件数は全体の12%程に過ぎず(平成26 年11 月現在、特許庁調べ)、技術流出を防ぐために自社技術を特許出願せず営業秘密(ノウハウ)として管理する中小企業も多く見られます。そのような営業秘密や、登録が権利発生の要件ではなく権利の存否判断が難しい著作権等については、本制度に基づく支援が受けられないことが今後の課題といえます。
EU 競争法の域外適用
弁護士 中島 康平
EU 競争法の適用に関しては、事業者がEU域外においてEU競争法に違反する行為を行った場合であっても、EU 市場で実行された場合(implementation)、または、EU 市場に即時かつ実質的な効果を及ぼすことが予見可能である場合(qualified effects test)にはEU競争法が適用されると考えられています。
現在、グローバルサプライチェーンの深化に伴い、世界各国の複数の企業が製品の供給に関与している場合に自国の競争法をどこまで適用できるかが日本を含めて複数の法域で争われています。液晶ディスプレイ(LCD)パネルカルテル事件において、欧州委員会は、カルテル対象製品について、①EEA 域内において第三者に直接販売された場合(direct EEA sales)、②域外において違反事業者のグループによって最終製品に組み込まれた上で、当該最終製品がEEA 域内の第三者に販売された場合(directEEA sales through transformed products)、③域外の第三者に販売され最終製品に組み込まれた上で、EEA 域内において当該最終製品が販売された場合(indirect sales)という3 つの分類に整理した上で、いずれの場合であっても、事件に対する管轄権を有し、すべての売上額を制裁金の基本額の算定に用いることができることを前提とした上で、抑止力の観点から十分であるとして①及び②の売上額のみを算定の基礎として採用しました。このようなアプローチは後続のブラウン管カルテル事件においても採用されています。
LCD パネルカルテル事件の欧州委員会の処理は普通裁判所において基本的に支持されましたが、上級裁判所において裁判官を補佐する法務官は、2015 年4 月30 日、②の分類について、最終製品のEEA 域内の販売によって、構成部品を対象とするカルテルが実行されたとはいえず、また、EEA 域内における即時的、実質的かつ予見可能な効果が立証されていないとして、②の売上額を制裁金の基本額の算定から除外すべきとの見解を示しました。法務官の意見は、裁判所を拘束しないものの、権威と事実上の影響力を有するとされており、今後、最高司法機関である上級裁判所がいかなる判断を下すかが注目されます。
国際契約における紛争解決条項
弁護士 貞 嘉徳
国際取引交渉においてポイントとなる内容の一つに紛争解決条項があります。任意の履行を期待できない場面では、最終的な紛争解決は執行を通じてしか実現することができないため、執行可能性という観点からの検討が不可欠です。
外国仲裁判断の承認・執行の条件を定めるニューヨーク条約は、140 ヶ国以上の国が締約国となっています。締約国は、外国仲裁判断をニューヨーク条約に従い、承認・執行しなければならず、とりわけ裁判所による判決の相互保証が存在しない国(例えば、中国)の企業との間の契約においては、仲裁による紛争解決を選択することが好まれる傾向にあります。一方当事者の所在国における裁判所による紛争解決では公平性の点でどうしても懸念を払拭できないということが、仲裁を選択する根本的な背景事情となっています。
国際的な仲裁機関としてよく知られているのは、国際商業会議所(ICC)、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)、米国仲裁協会(AAA)、アジア地域では、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、香港国際仲裁センター(HKIAC)、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)があります。仲裁機関の選択においては、政治情勢等も考慮に入れる必要があり、例えば、最近では、一時国内情勢が不安定となった香港を本拠地とするHKIAC を仲裁機関とすることが避けられる傾向がありました。
これら仲裁機関を用いる仲裁のほか、ad hoc 型と呼ばれる仲裁機関を用いない仲裁もあります。
仲裁の最大のメリットは、その手続の柔軟性であり、仲裁人の選定をはじめ、紛争当事者に大幅な自主性が認められます。日本は、現在、環太平洋経済連携協定(TPP)をはじめ、複数の経済協定を交渉中であり、本年2 月には、モンゴルとの間で経済連携協定(EPA)を締結したことが発表されました。今後、益々、国際的な経済活動が活発化する中、紛争解決条項を検討する機会も増えてくることが予想されます。仲裁人の人数、手続・仲裁地・言語・仲裁機関の選択など、検討事項は多岐にわたります。個々の事案に応じた適切な仲裁条項を定めるよう検討することが必要です。
民法改正に伴う『約款』の見直し
弁護士 佐藤 有紀
民法改正案が3 月31 日付で国会に提出されました。今回の民法改正は、従前から
議論されていた債権法改正の集大成であり、実務に与える影響も少なくないものと思わ
れます。今回は、多岐に渡る民法改正のうち、定型約款(民法改正案第548 条の2 以下)に関する取扱い(のごく一部)について取り上げたいと思います。定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」(民法改正案第548 条の2 第1項)と、定型取引とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」(民法改正案第548条の2 第1 項)と定義されています。
定型取引を行うことの合意をした者は、一定の場合(定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたか、定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合)、定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされます(民法改正案第548 条の2 第1 項)。現状広く用いられている約款の法的な位置付けをしたのが今回の定型約款制度と言えるでしょう。
もっとも、そもそも定型取引は、取引の「内容の全部又は一部が画一的であることが」双方に合理的なものとされており、画一的であることが不合理であり定型約款に該当しないと判断される約款も出てくる可能性があります(例えば、約款の内容を相手方との間で特約条項により相当程度変更する場合など。この場合は契約内容自体は有効となれば実際上不利益はないかもしれませんが、それ以外の定型的約款に該当しないとされる場合に約款
が無効として民法の規定に沿って解釈されることもあり得るのではないかと思います)。また、画一的であることの合理性の判断要素は今後の実務の集積を待たなくてはならないように思われます。
なお、相手方の権利を制限し、義務を加重する条項で、定型取引の態様、実情、社会通念に照らし信義則に反するものは、契約内容と認められません(民法改正案第548 条の2 第2 項)。信義則違反となる場合は、「消費者の利益を不当に害することとなる」条項を無効とする消費者契約法上の概念と必ずしも一致するものではないこと、即ちいわゆるB to B 取引における約款が無効とされる可能性がある点には注意が必要です。